要介護認定の基準は?受けるための申請方法や流れについて解説
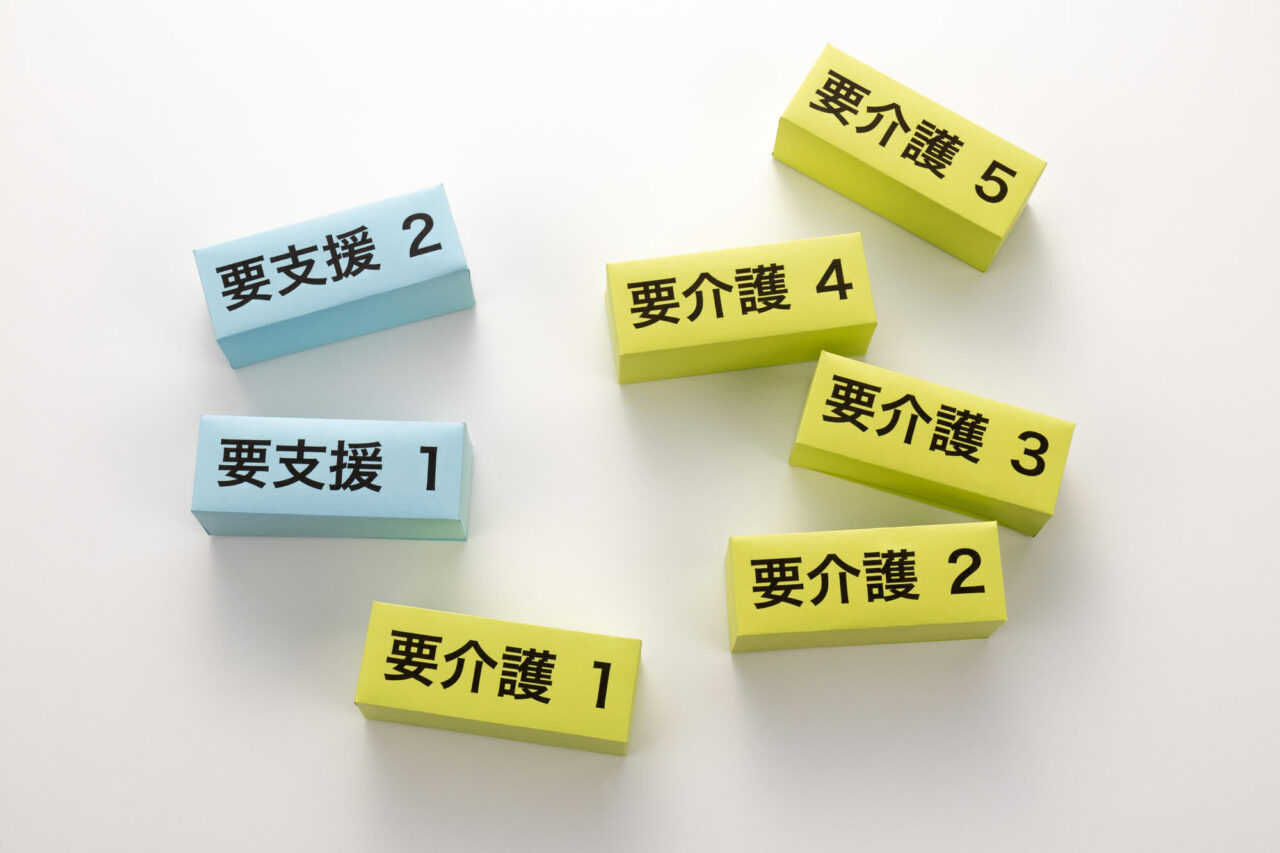
親や同居家族の身体機能が衰えてきたので、介護サービスの利用を検討している方はいませんか。
要介護認定の基準を満たしていれば、介護保険サービスを利用することが可能です。
本記事では、要介護認定の認定基準を早わかり表で紹介しています。
認定を受けるための申請方法についても解説しているため、要介護認定の申請を検討している方は参考にしてください。
要介護認定に関する基礎知識
そもそも、要介護認定とはどのような制度なのでしょうか。
ここでは、要介護(要支援)認定を申請する前に知っておきたい基礎知識について、わかりやすく解説します。
要介護認定とは
要介護度認定とは、対象者がどの程度の介護を必要としている状態にあるのか、要介護の場合は要介護1〜5の5段階、要支援の場合は要支援1〜2の2段階に区分したものになります。
| 要介護度 | 状態 |
| 自立(非該当) | 歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態 |
| 要支援1 | 日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態 |
| 要支援2 | 筋力の低下により、歩行や立ち上がりの動作が不安定になっており、将来的に介護を必要とするリスクが高い状態 |
| 要介護1 | 要支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態 |
| 要介護2 | 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態 |
| 要介護3 | 要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態 |
| 要介護4 | 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態 |
| 要介護5 | 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態 |
介護保険制度では、寝たきりや痴呆が原因で常時介護が必要になった場合(要介護)や、日常生活の支援が必要になった場合(要支援)に、1〜3割の利用料を支払うことで介護サービスを受けることが可能です。
要介護認定の認定を受けた利用者は、給付によって介護サービスが受けられるため、要介護認定の判定には全国一律の基準を設けています。
要介護と要支援の違い
要介護と要支援の違いは、1人で生活ができるかどうか、介助が必要かどうかです。
認知機能が低下している場合、日常生活に支障が生じるため要介護と判断されますが、軽い物忘れなど症状が軽度の場合は要支援になります。
利用できる介護サービスも同じではありません。
要介護の場合は介護保険サービス、要支援の場合は介護予防サービスを利用することが可能です。
介護保険サービスは利用者に必要な介護サービスを提供していますが、介護予防サービスは要介護にならないための、生活機能の維持向上を目的としています。
要介護認定を受けるタイミング
要介護認定を受けた方がよいタイミングは、自宅で生活するのが難しくなったとき、または病気やケガによる退院後の生活に不安があるときです。
家族のサポートがないと生活できない状態であれば、介護サービスの利用で家族の負担を減らすために要介護認定を受けた方がよいでしょう。
突然の病気やケガによる入院で、退院後の生活に不安を覚える場合も、要介護認定を受けておくと安心です。
自宅で生活できない場合は、特別養護老人ホームに入居できる可能性があります。
介護や支援が必要な人の割合
高齢化が進んでいるため、介護や支援が必要な方の割合は上昇傾向にあります。
年代別の人口に占める要支援・要介護認定者の割合は、次のとおりです。
| 年代 | 要支援・要介護認定者の割合 |
| 40歳〜64歳 | 0.4% |
| 65歳〜69歳 | 2.9% |
| 70歳〜74歳 | 5.8% |
| 75歳〜79歳 | 11.6% |
| 80歳〜84歳 | 26.2% |
| 85歳以上 | 60.1% |
出典:公益財団法人生命保険文化センター「介護や支援が必要な人の割合はどれくらい?」
表を確認すると、80代前半では約3割、85歳以上では約6割の方が、要支援や要介護認定を受けていることがわかります。
今後も高齢者の割合が増えていくのは確実です。
高齢者とその家族が安心して生活していくためには、介護サービスや介護予防サービスの利用が必要だと言えるでしょう。
要介護に認定された場合の支給限度額
要介護や要支援の認定を受けた方は、支給限度額内で介護サービスを利用した場合、所得に応じて自己負担額が1〜3割になります。
介護度別の支給限度額(1か月あたり)は、下記表のとおりです。
| 介護度 | 支給限度額 |
| 要支援1 | 5万320円 |
| 要支援2 | 10万5,310円 |
| 要介護1 | 16万7,650円 |
| 要介護2 | 19万7,050円 |
| 要介護3 | 27万480円 |
| 要介護4 | 30万9,380円 |
| 要介護5 | 36万2,170円 |
なお、支給限度額を超えた場合は、超えた分が全額自己負担になります。
介護サービスを利用しない場合は、支給限度額を次の月に繰り越すことはできません。
要介護認定基準の早わかり表
要介護の認定基準は、要介護認定等基準時間(介護にかかる時間)をもとにして判定されます。
ここでは、介護の分類と要介護認定等基準時間の分類を早わかり表にまとめて紹介します。
介護の分類
要介護認定では、介護の必要量に応じて介護度を判定しています。
介護の必要量の目安として時間で換算されるのは、次の5分野です。
| 介護の分類 | 介護の内容 |
| 直接生活介助 | 入浴、排せつ、食事等の介護 |
| 間接生活介助 | 洗濯、掃除等の家事援助等 |
| 問題行動関連行為 | 徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等 |
| 機能訓練関連行為 | 歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練 |
| 医療関連行為 | 輸液の管理、じょくそうの処置等の診療の補助 |
要介護認定等基準時間の分類
要介護度は、上記5分野の要介護認定等基準時間によって判定されます。
介護度別の要介護認定等基準時間は、下記の表のとおりです。
| 介護度 | 要介護認定等基準時間 |
| 要支援 | ・上記5分野の要介護認定等基準時間が25分以上32分未満 ・またはこれに相当する状態 |
| 要介護1 | ・上記5分野の要介護認定等基準時間が32分以上50分未満 ・またはこれに相当する状態 |
| 要介護2 | ・上記5分野の要介護認定等基準時間が50分以上70分未満 ・またはこれに相当する状態 |
| 要介護3 | ・上記5分野の要介護認定等基準時間が70分以上90分未満 ・またはこれに相当する状態 |
| 要介護4 | ・上記5分野の要介護認定等基準時間が90分以上110分未満 ・またはこれに相当する状態 |
| 要介護5 | ・上記5分野の要介護認定等基準時間が110分以上 ・またはこれに相当する状態 |
要介護認定等基準時間が長くなればなるほど、要介護のレベルは上がっていきます。
数字が大きくなればなるほど、介護の負担が重くなることを覚えておきましょう。
要介護度レベルごとの具体例
要支援や要介護の認定を受けた方は、どのような状態なのでしょうか。
ここでは、要介護度別の状態の具体例について解説します。
要支援1とは
基本的な日常動作ができる状態で、部分的な見守りや補佐を必要とする場合が、要支援1になる可能性が高くなります。
要支援1の状態の具体例は、次のとおりです。
- 立ったり座ったりするときにふらつくことがある
- 食事やトイレは自分でできる
要支援1では、訪問介護や通所介護(デイサービス)、短期入居生活介護(ショートステイ)などを利用できます。
基本的な日常生活に問題はないため、要支援1と認定されても、自宅で生活される方も多くいるでしょう。
要支援2とは
要支援1よりも、日常生活に不便がある場合は要支援2に認定される可能性が高くなります。
要支援2の状態の具体例は、次のとおりです。
- 立ち上がりや歩行でふらつく
- 入浴時に背中が洗えない
- 身だしなみを整えることができない
- 意思決定に介助が必要
要支援2では、要支援1と同様の介護予防サービスが利用できます。
身体機能が低下していても認知機能は低下していない状態のため、1人で暮らすことは可能ですが、見守りやサポートは必要と言えるでしょう。
要介護1とは
要支援状態よりも身体機能の低下が認められる場合は、要介護1に認定される可能性が高くなります。
要介護1の状態の具体例は、次のとおりです。
- 立ち上がりや歩行が不安定
- 1人での買い物が難しい
- トイレが1人でできない
要介護1は要介護度の中で最も介護の必要性が低い位置付けのため、一人暮らしをしている方も少なくありません。
日常生活での介助が必要な場面も多いので、老人ホームへの入居を検討される方も多いです。
要介護2とは
日常生活のこと全般に見守りや介助が必要な場合は、要介護2に認定される可能性が高くなります。
要介護2の状態の具体例は、次のとおりです。
- 自分で爪を切ることができない
- 薬が管理できない
- お金の管理が難しい
- 料理のやり方を忘れる
介護1と同じ介護サービスが利用できますが、レンタルできる福祉用具に、車椅子や介護ベッドが追加されます。
訪問介護やデイサービスを利用しながら1人で暮らす人もいますが、生活に不安があると言えるでしょう。
要介護3とは
日常生活全般で介助が必要な場合は、要介護3に認定される可能性が高くなります。
要介護3の状態の具体例は、次のとおりです。
- 自力で起き上がれない
- 歩行が困難
- 自分の名前がわからない
- トイレや入浴、着替えが1人でできない
要介護3以上は、特別養護老人ホームへの入居対象者になります。
介護者への負担が大きくなり、自宅での介護が困難になるため、施設への入所を検討される方が多いです。
要介護4とは
日常生活全般での介助が必要で、認知症の症状が進行して意思疎通が難しい場合は、要介護4に認定される可能性が高くなります。
要介護4の状態の具体例は、次のとおりです。
- 支えなしで座ることができない
- 移動する際には車椅子が必要
基本的に寝たきりの状態になるため、すべての介護サービスの対象となります。
特別養護老人ホームや、介護療養型医療施設など、サポートが手厚い施設に入居しているケースが多いです。
要介護5とは
日常生活のすべてに介助が必要で、1日のほとんどを寝たきりの状態で過ごしている場合は、要介護5に認定される可能性が高くなります。
要介護5の状態の具体例は、次のとおりです。
- 排泄はオムツで行う
- 水や食事を飲み込むのが困難
- 寝返りができない
認知機能が全般的に低下しているため、すべての介護サービスの対象となります。
要介護度4と比較すると、医療の充実している介護療養型医療施設への入居を選択する方が多いです。
要介護認定を受けるメリット・デメリット
要介護認定を受けるべきか、受けないべきか悩んでいる方も多いです。
ここでは、要介護認定を受けるメリットやデメリットについて解説します。
要介護認定を受けるメリット
要介護認定を受けるメリットは、次のとおりです。
- 介護サービスを利用する負担が軽減できる
- 適切な介護サービスを受けられる
- 介護の相談窓口を利用できる
メリットの詳細を、一つひとつ確認していきましょう。
【介護サービスを利用する負担が軽減できる】
要介護認定を受けると、介護保険サービスを利用したときにかかる費用の負担が少なくなります。
負担の割合は、収入状況によって異なりますが1〜3割です。
たとえば1万円の介護サービスを利用した場合の自己負担額が1,000円〜3,000円なので、家計への影響を少なくできます。
そもそも、要介護認定を受けていない状態では、介護保険によるサービスが受けられません。
要介護認定が非該当の場合は、介護保険以外の保健・福祉サービスの利用を検討しましょう。
【適切な介護サービスを受けられる】
利用できる介護サービスは、要介護度によって決められています。
要介護度認定を受ければ、利用者の状態に合った必要なサービスを受けることが可能です。
家族による介護の負担を減らすこともできるでしょう。
【介護の相談窓口が利用できる】
介護認定を受けるためには、介護認定員による面談が必要です。
その際に、要介護者の心身の状態を相談したり、適切な介護サービスの案内を受けたりすることができます。
また、自治体の介護保険相談窓口でも、介護に関する悩みや疑問の相談に対応することが可能です。
介護について相談できる場所があることは、介護を担当する家族にとって大きな支えになるでしょう。
要介護認定を受けるデメリット
要介護認定を受けるデメリットは、次のとおりです。
- 異なる判定結果が出ることがある
- 調査の負担やプライバシーの侵害
- 介護保険料が上がる
デメリットの詳細を、一つひとつ確認していきましょう。
【異なる判定結果が出ることがある】
要介護認定の面談時に、正しい情報を伝えないと、実際とは異なる検査結果が出る恐れがあります。
本当の介護度よりも低く判定されてしまった場合は、適切な介護サービスを受けることができません。
介護者の状態は、できるだけ正確に伝えることが大切です。
【調査の負担やプライバシーの侵害】
介護認定を受けるためには、介護認定員の訪問による面談が必須となるため、ストレスになったり、プライバシーの侵害だと感じたりすることもあります。
人によっては、介護者の状態や住環境をチェックされるのが嫌だと感じる方もいるでしょう。
認定調査を受ける前に、何が調査されるのか把握しておくことが大切です。
【介護保険料が上がる】
介護認定を受けると、介護保険サービスの利用にかかる費用が安くなるという恩恵がありますが、支払う介護保険料は高くなります。
介護保険サービスを利用する方の割合が増えれば、介護保険制度の利用者全体の負担も増える仕組みだからです。
今後も高齢化により介護サービスの利用は増える可能性が高いので、さらなる介護保険料の値上がりが予想されます。
要介護認定を受けるまでの流れ
要介護認定を受けるためには、住んでいる地域の自治体や地域包括支援センターへの申請が必要です。
ここでは、要介護認定を受けるまでの流れについて解説します。
申請書類を提出する
自治体の福祉課や、地域包括支援センターなどの担当窓口に申請書類を提出します。
要介護認定の申請に必要な書類は、次のとおりです。
- 要介護認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 診察券
- 本人確認書類
- マイナンバーが確認できるもの
40歳以上65歳未満の場合は、介護保険被保険者証ではなく加入している医療保険の被保険者証を用意してください。
必要書類は自治体によって異なる場合もあります。
事前に電話で問い合わせるか、ホームページを確認しておきましょう。
訪問審査を受ける
申請が完了したら、自治体の職員や委託されたケアマネージャーが、介護認定員として申請者の自宅を訪問します。
訪問時に確認するのは、全国で統一されている、以下の基本調査項目です。
- 身体機能・起居機能
- 生活機能
- 認知機能
- 精神・行動障害
- 社会生活への適応
- 過去14日間で受けた特別な治療
基本調査項目は、細かく分類すると70項目以上あります。
申請者が適切な要介護認定を受けるために、できるだけ正確な情報を伝えましょう。
主治医に意見書の作成を依頼する
自治体から依頼を受けた依頼者の主治医は、意見書を作成します。
かかりつけ医がいない場合や、複数の医療機関を利用している場合は、自治体が指定した医師の診断を受けることも可能です。
医師が意見書を記入したあとは、自治体に返送するため、家族が内容を確認することはできません。
一次判定を受ける
要介護認定の一次判定は、コンピューターによって行われます。
こちらは二次判定の原案となるため、最終判断にはなりません。
二次判定を受ける
一次判定の結果や医師の意見書をもとにして、保健医療福祉の学識経験者による二次判定が行われます。
まず最初に行われるのが、一次判定結果の修正や確定です。
そのあとに介護の手間にかかる判定を行い、介護認定の有効期限の設定や、介護認定審査会として付する意見を追加する場合があります。
要介護度の結果が通知される
自治体は申請日から原則30日以内に、介護認定結果通知書を申請者の自宅に送付します。
記載されている有効期限は申請日です。
申請後に介護サービスを利用している場合、費用の負担軽減が受けられます。
介護保険サービスの利用方法
要介護認定を受けたあとは、訪問介護や施設への入居、介護予防などの介護保険サービスを利用することが可能です。
ここでは、要介護認定を受けたあとの、介護保険サービスの利用方法について解説します。
訪問介護を自宅で受ける
自宅で訪問介護サービスを受ける場合の手順は、次のとおりです。
- 訪問介護の事業者を選択する
- ケアプランを作成する
- 事業者と契約する
- サービスの利用を開始する
ケアマネージャーに希望を伝えてケアプランを作成したあとは、要介護者と事業者が直接契約を行います。
認知症などの症状があって難しい場合は、代理人を立てることも可能です。
介護施設に入居する
介護施設に入居する場合の手順は、次のとおりです。
- 入居したい介護施設を選ぶ
- ケアプランを作成する
- サービスの利用を開始する
介護施設のケアマネジャーにケアプランを作成してもらわないと、介護施設に入居することはできません。
介護施設に直接問い合わせて、ケアプランの作成を申し込みましょう。
介護予防サービスを受ける
介護予防サービスを受ける場合の手順は、次のとおりです。
- 地域包括支援センターに連絡する
- 介護予防ケアプランを作成する
- サービスを利用する
要支援認定を受けた場合は、要介護のようにケアマネージャーに相談するのではなく、地域包括支援センターの担当相談員に連絡します。
介護予防ケアプランを作成するときは、要望をしっかりと伝えるようにしましょう。
要介護認定に関するよくある質問
最後に、要介護認定に関する疑問について回答していきます。
疑問を解消してから、要介護認定の申請を検討しましょう。
要介護認定の有効期間は?
新規の場合は申請日から6か月、更新の場合は12か月です。
自治体から必要と認められる条件を満たしている場合は、48か月(4年間)の有効期限になります。
要介護認定は自動更新ではありません。
有効期限を過ぎてしまった場合は、介護保険サービスが利用できなくなります。
更新できる期間も定められているため、忘れずに更新を申請しましょう。
要介護度の変更はできる?
急な病気や怪我など、心身の状態に著しい変化があった場合は、更新期間を待つことなく要介護度認定の区分変更申請ができます。
本来の介護度よりも低いと感じたときや、利用できる介護サービスを増やしたいときも申請が可能です。
区分変更申請を行えば、必ず要介護度を変更できるわけではありません。
変更が必要ないと判定された場合は、以前の要介護度のままとなります。
区分変更の必要性をよく見極めてから申請しましょう。
要介護度の結果に納得できない場合は?
要介護度の判定結果に納得できない場合は、ケアマネージャーか地域包括支援センターの担当者に相談してください。
場合によっては、区分変更申請か、介護保険審査会に不服の申し立てができます。
手間と時間がかかりますが、審査をすべて最初からやり直すことが可能です。
まとめ
今回は、要介護認定の基準や申請の流れについて詳しく解説しました。
要介護度認定を受けることができれば、家族の介護の負担や介護サービスの利用にかかる費用の負担を軽くできます。
日常生活の動作に不安があり、介助が必要な状態であれば、要介護認定を受けるメリットは大きいです。
要介護認定を受けるためには、自治体への申請や判定を受ける必要があります。
要介護認定を受けて、適切な介護サービスを受けましょう。







