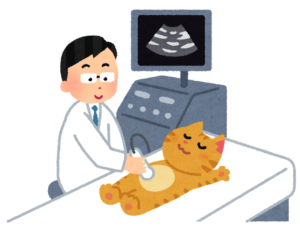介護保険負担限度額認定証とは何?交付の基準や申請手順について解説
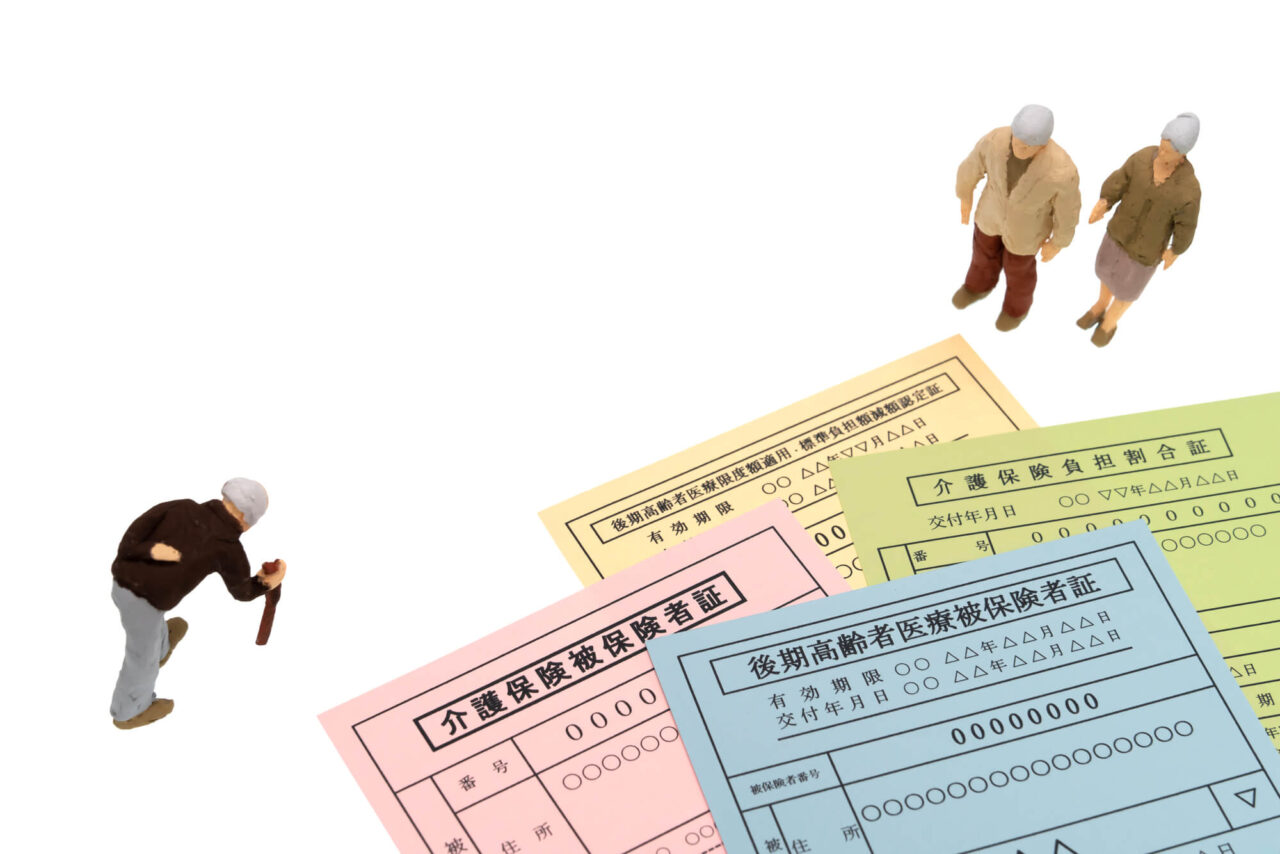
介護保険負担限度額認定証とは、どのような方が対象者で、どのような場合に交付されるのでしょうか。
本記事では、介護保険負担限度額認定制度の仕組みや、介護保険負担限度額認定証の交付基準について解説しています。
申請方法や申請時の注意点についても解説しているので、介護保険負担限度額認定証の申請を検討されている方は参考にしてください。
介護保険負担限度額認定制度とは
介護保険負担限度額認定証の申請を検討しているなら、介護保険負担限度額認定制度について理解を深めておく必要があります。
まずは、介護保険負担限度額認定制度の仕組みをチェックしていきましょう。
介護施設利用の負担が軽減される
介護サービスの負担額は1〜3割ですが、介護保険施設を利用した場合にかかる費用は、原則として全額自己負担となります。
しかし、介護保険負担限度額認定制度の要件を満たしていれば、介護施設を利用した際の食費や居住費の負担を軽減することができます。
対象者に介護保険負担限度額認定証が交付される
介護保険負担限度額認定制度の対象者には、介護保険負担限度額認定証という書類が交付されます。
介護保険負担限度額認定証の交付を受けるには、居住している地域を管轄する自治体への申請が必要です。
すでに施設へ入居している場合でも、施設担当者が代理で申請することができます。
段階ごとに負担限度額が決められている
介護保険負担限度額認定制度の対象者は、本人の収入状況や預貯金によって、5つの段階(第1段階、第2段階、第3段階①、第3段階②、第4段階 )ごとに負担限度額が設定されています。
令和6年8月1日以降の段階ごとの負担限度額(日額)は、次のとおりです。
| 段階 | 多床室(特養等) | 多床室(老健・ 医療院等) | 従来型個室(特養等) | 従来型個室(老健・ 医療院等) | ユニット型個室的 多床室 | ユニット型個室 |
| 第1段階 | 0円 | 0円 | 380円 | 550円 | 550円 | 880円 |
| 第2段階 | 430円 | 430円 | 480円 | 550円 | 550円 | 880円 |
| 第3段階 ①・② | 430円 | 430円 | 880円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 |
介護保険負担限度額認定制度による、食費や居住費の軽減措置が受けられるのは、第1段階〜第3段階までの方になります。
第4段階の方は、負担軽減の対象にはなりません。
【令和6年8月に一部負担額が変更】
介護保険施設等における居住費の負担限度額は、令和6年8月より変更されました。
変更される理由は、近年の高齢者世帯の光熱費や水道費など、在宅で生活する方との公平性を保つためです。
居住費の負担額は令和6年8月から、60円(日額)引き上がります。
なお、現状で負担限度額が0円の利用者負担第1段階の多床室利用者については 、負担限度額が据え置きとなるため、負担限度額の変更はありません。
特例軽減措置が受けられる場合もある
第4段階に該当する方は、食費や居住費の負担軽減がありませんが、特例軽減措置が適用される場合があります。
特例軽減措置の概要と適用されるための要件についてチェックしていきましょう。
【特例軽減措置の概要】
たとえば高齢者の夫婦で、世帯のひとりが施設に入所したケースで、介護費用の負担により経済状況が悪化した場合は、入所した方の食費や居住費に第3段階の負担限度額を適用することができます。
これが特例軽減措置です。
高齢夫婦の世帯だけでなく、同居家族の年収が低くて生活が困難な場合にも適用できます。
【特例軽減措置の対象者になるための要件】
特例軽減措置の対象になる要件は、次のとおりです。
- 世帯人数が2人以上
- 世帯の年間収入から、施設利用者の負担見込額を除いた額が80万円以下
- 世帯の現金、預貯金等の額が450万円以下
- 日常生活に不要な資産を所有していない
- 介護保険料を滞納していない
- 介護保険施設に入所し、第4段階の食費・居住費を負担している
この6つの要件をすべて満たしている場合は、特例軽減措置の対象となります。
自治体に申請して、介護保険負担限度額認定証の交付を受けましょう。
介護保険負担限度額認定証の交付を受けるための基準
介護保険負担限度額認定証の交付を受けるためには、所得と預貯金の要件を満たす必要があります。
交付を受けるための基準をチェックしていきましょう。
対象者
介護保険負担限度額認定証の交付対象者は、次のとおりです。
- 生活保護を受給している
- 本人を含む世帯全員が住民税非課税
- 本人の配偶者が住民税非課税
- 別世帯の配偶者も住民税非課税
住民税が課税される世帯は、介護保険負担限度額認定制度の対象外となります。
所得の基準
介護保険負担限度額認定制度の利用者負担段階は、世帯ごとの所得によって決まります。
段階ごとの所得の基準は、次のとおりです。
| 段階 | 所得の基準 |
| 第1段階 | 生活保護受給者 世帯全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者 |
| 第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税 年金収入金額+合計所得金額80万円以下 |
| 第3段階① | 世帯全員が市町村民税非課税 年金収入金額+合計所得金額が80万円超~120万円以下 |
| 第3段階② | 世帯全員が市町村民税非課税 年金収入金額+合計所得金額が120万円超 |
上記以外の方は第4段階と判定されます。
預貯金の基準、預貯金の対象となる資産
介護保険負担限度額認定証の交付を受けるためには、所得の基準だけでなく預貯金の基準も満たす必要があります。
段階ごとの預貯金の基準は、次のとおりです。
| 段階 | 預貯金の基準(夫婦の場合) |
| 第1段階(生活保護受給者) | 要件なし |
| 第1段階(世帯全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者) | 1,000万円(2,000万円)以下 |
| 第2段階 | 650万円(1,650万円)以下 |
| 第3段階① | 550万円(1,550万円)以下 |
| 第3段階② | 500万円(1,500万円)以下 |
預貯金には、対象に含まれる資産と含まれない資産があります。
それぞれをチェックしておきましょう。
【預貯金等に含まれるもの】
預貯金等に含まれるものは、次のとおりです。
- 銀行に預けている預貯金(普通・定期)
- 株式・債券などの有価証券
- 金・銀など時価が判断できる貴金属
- 投資信託
- 現金(タンス預金を含む)
預貯金等の調査には、預貯金を証明する書類が必要になります。
虚偽を申告した場合は、認定取り消しや不正受給になってしまうため、正確な金額を申告しましょう。
なお、住宅ローンを組んでいたり、借入金があったりする場合は、預貯金等から差し引いて算出できます。
【預貯金等に含まれないもの】
預貯金等に含まれないものは、次のとおりです。
- 生命保険
- 自動車
- 腕時計
- 貴金属
- 絵画・骨董品
- 家財
市区町村で時価の把握が難しいものは、預貯金等に含まれません。
介護保険負担限度額認定証の申請手順
介護保険負担限度額認定証の交付を受けるには、自治体への申請が必要です。
ここでは、申請手順について詳しく解説します。
必要書類を用意する
介護保険負担限度額認定証の申請に必要な書類は、次のとおりです。
- 介護保険負担限度額認定証申請書・同意書
- 預貯金等の証明書類(通帳のコピー等)
- 申請者の確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
介護保険負担限度額認定証申請書や同意書は、自治体の窓口で受け取るか、ホームページからダウンロードして入手できます。
預貯金等の証明書類は、金融機関名・支店名・名義人・口座番号がわかるページをコピーしてください。
ローンや借入金がわかる場合は、残高がわかるページのコピーが必要です。
書類を提出する
必要書類が準備できたら、自治体の介護保険担当窓口に提出します。
窓口に行けない場合は、郵送で書類を提出することも可能です。
また、自治体によっては、オンライン申請に対応している場合もあるので、事前に確認してみましょう。
すでに介護施設に入居中の場合は、施設の担当者に代理で申請してもらうこともできます。
1週間程度で結果の通知を受ける
申請から交付までの期間は、約1週間です。
自宅に郵送されてくるので確認しましょう。
なお、第4段階に該当する場合は介護保険負担限度額認定証が交付されず、結果のみ書面で通知されます。
介護保険負担限度額認定証の対象施設とサービス
介護保険負担限度額認定証が利用できる主な施設は、次のとおりです。
- 特別養護老人ホーム
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 地域密着型介護老人福祉施設
ここでは、対象施設とサービスについて、詳しく解説します。
特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム(特養)とは、常時介護が必要で、在宅での介護が困難な高齢者に対し、生活全般の介護を行う施設です。
特別養護老人ホームの基準費用額(日額)と、負担限度額(日額)を紹介します。
| 基準費用額(日額) | 負担限度額(日額) 第1段階 | 負担限度額(日額) 第2段階 | 負担限度額(日額) 第3段階① | 負担限度額(日額) 第3段階② | |
| 食費 | 1,445円 | 300円 | 390円 (ショートステイの場合:600円) | 650円(ショートステイの場合:1,000円) | 1,360円(ショートステイの場合:1,300円) |
| 居住費(ユニット型個室) | 2,066円 | 880円 | 880円 | 1,370円 | 1,370円 |
| 居住費(ユニット型個室的多床室) | 1,728円 | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,370円 |
| 居住費(従来型個室) | 1,231円 | 380円 | 480円 | 880円 | 880円 |
| 居住費(床室) | 915円 | 0円 | 430円 | 430円 | 430円 |
介護老人保健施設
介護老人保健施設(ろうけん)とは、介護を必要とする高齢者の自立支援や医師による医学的管理、作業療法士や理学療法士等によるリハビリテーション、あらゆる日常サービスを提供する施設です。
介護老人保健施設の基準費用額(日額)と、負担限度額(日額)を紹介します。
| 基準費用額(日額) | 負担限度額(日額) 第1段階 | 負担限度額(日額) 第2段階 | 負担限度額(日額) 第3段階① | 負担限度額(日額) 第3段階② | |
| 食費 | 1,445円 | 300円 | 390円(ショートステイの場合:600円) | 650円(ショートステイの場合:1,000円) | 1,360円(ショートステイの場合:1,300円)
|
| 居住費(ユニット型個室) | 2,066円 | 880円 | 880円 | 1,370円 | 1,370円 |
| 居住費(ユニット型個室的多床室) | 1,728円 | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,370円 |
| 居住費(従来型個室) | 1,728円 | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,370円 |
| 居住費(床室) | 437円 | 0円 | 430円 | 430円 | 430円 |
介護医療院
介護医療院は、長期的な療養が必要な要介護者が、療養の管理や看護、医学的な視点からの介護、リハビリテーションをはじめ、必要に応じた医療や日常生活の支援など、包括的なサービスを提供することを目的としています。
できる限り自分らしく日常生活を送れるよう支援しています。
介護医療院の基準費用額(日額)と、負担限度額(日額)は、次のとおりです。
| 基準費用額
| 負担限度額(日額)第1段階 | 負担限度額(日額)第2段階 | 負担限度額(日額)第3段階① | 負担限度額(日額)第3段階② | |
| 食費 | 1,445円 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 |
| 居住費(従来型個室の場合) | 1,668円 | 490円 | 490円 | 1,310円 | 1,310円 |
短期入所生活介護
短期入所生活介護(ショートステイ)は、常に介護が必要な方の短期間の入所を受け入れ、家族の介護負担軽減を目的に実施されます。
連続利用日数は30日までです。
主に特別養護老人ホームが提供するサービスのため、基準費用額(日額)や、負担限度額(日額)は、特別養護老人ホームと同じです。
短期入所療養介護
短期入所療養介護(医療型ショートステイ)は、在宅での介護が難しくなった場合に、家族の介護負担軽減を目的に医療や介護、機能訓練が行われます。
こちらも連続利用日数は30日までです。
主に介護老人保健施設が提供するサービスのため、基準費用額(日額)や、負担限度額(日額)は、介護老人保健施設と同じです。
地域密着型介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設とは、入所定員が29人以下の特別養護老人ホームであり、「地域密着型施設サービス計画」に基づいてサービスを提供する施設のことです。
地域密着型介護老人福祉施設の基準費用額(日額)と、負担限度額(日額)は、次のとおりです。
| 基準費用額
| 負担限度額(日額)第1段階 | 負担限度額(日額)第2段階 | 負担限度額(日額)第3段階① | 負担限度額(日額)第3段階② | |
| 食費 | 1,445円 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 |
| 居住費(従来型個室の場合) | 1,171円 | 320円 | 420円 | 820円 | 820円 |
介護保険負担限度額認定証を申請する際の注意点
介護保険負担限度額認定証の申請に不備があると、認定証を受け取ることができません。
申請時の注意点について解説します。
不正申告の場合は加算金が発生する
所得を隠す、預貯金等を正確に伝えないなどの不正申告により介護費用の軽減措置を受けた場合、加算金の支払いが命じられます。
加算金は、負担限度額の2倍です。
つまり、不正申告が発覚すると、負担限度額の3倍の費用を負担することになります。
なお、不正申告によって受給した費用は返却も必要です。
預貯金を隠しても残高照会によってバレるので、不正申告は絶対にやめましょう。
施設とショートステイでは記入内容が異なる
介護サービスのショートステイを利用している場合、介護保険負担限度額認定証申請書の「介護保険施設の所在地」と「名称」を記入する必要はありません。
被保険者本人の氏名を記載し、押印してから自治体の窓口へ提出しましょう。
生活保護の場合は必要書類が異なる
生活保護受給者の場合は、申請時に提出する書類が異なります。
たとえば、世帯全員分の預貯金等の証明書類は不要です。
自治体によって提出書類や申請手続きが異なる場合もあるので、申請前に確認しておくようにしましょう。
介護保険負担限度額認定証の更新について
介護保険負担限度額認定証は、更新が必要です。
有効期限や再発行の方法について解説します。
有効期限は1年で毎年更新が必要
介護保険負担限度額認定証が交付された場合は、毎年更新が必要になります。
初めて申請した場合の有効期限は申請月から翌年7月31日までですが、そのあとは8月1日から翌年7月31日までの1年間です。
時期は自治体によって異なりますが、更新の時期が近づいてくると、書類が送付されてきます。
基本的には、期限が切れる前に更新書類が送られてくるので、介護保険負担限度額認定証が利用できない時期は発生しません。
また、自動更新ではないので、忘れずに更新手続きを行いましょう。
紛失や汚損による再発行も可能
介護保険負担限度額認定証の紛失や、汚損が発生した場合でも再交付が可能です。
再交付に必要な書類は、次のとおりです。
- 介護保険負担限度額認定証等再交付申請書
- 本人の介護保険被保険者証
- 本人の代わりに申請される方の本人確認ができる書類
自治体によっては、窓口申請ではなく郵送で申請することも可能です。
段階が変動する場合がある
収入状況や預貯金に変動があった場合は、介護保険負担限度額認定の段階が変更される場合があります。
段階は更新書類に記載されているので、忘れずに確認しておきましょう。
詳しいことは、自治体の担当窓口に確認してください。
介護の負担を軽減できるその他の制度
介護保険負担限度額認定証の交付を申請しても、非該当になる場合があります。
介護費用の負担を軽くできる、その他の制度や補助金をチェックしていきましょう。
高額介護サービス費
介護サービスの自己負担額が一定の基準を超えた場合に、自治体に申請することで超過分の払い戻しが受けられる制度です。
介護サービス費の負担限度額は、前年の所得や市町村民税、生活保護などの区分によって定められています。
| 区分 | 負担限度額(月額) |
| 課税所得690万円以上(年収約1,160万円以上) | 14万100円(世帯) |
| 課税所得380万円〜690万円未満(年収770〜1,160万円未満) | 9万3,000円(世帯) |
| 市町村民税課税〜課税所得380万円未満(年収約770万円未満) | 4万4,400円(世帯) |
| 世帯全員が市町村民税非課税 | 2万4,600円(世帯) |
| 前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下 | 2万4,600円(世帯) 1万5,000円(個人) |
| 生活保護を受給している | 1万5,000円(世帯) |
出典:厚生労働省「高額介護サービス費の負担限度額が見直されます」
払い戻しを受けるためには、自治体への申請が必要です。
申請の期限は、公的介護サービスの利用から2年と定められています。
高額介護合算療養費制度
医療保険と介護保険における、医療費と介護費を合算した1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の自己負担額が、著しく高額であった場合に自己負担額の一部が払い戻される制度です。
限度額は、年齢や年収によって異なります。
| 75歳以上 (介護保険+後期高齢者医療 | 70歳~74歳 (介護保険+被用者保険または国民健康保険) | 70歳未満 (介護保険+被用者保険または国民健康保険) | |
| 年収約1,160万円~ | 212万円 | 212万円 | 212万円 |
| 年収約770万円~約1,160万円 | 141万円 | 141万円 | 141万円 |
| 年収約370万円~約770万円 | 67万円 | 67万円 | 67万円 |
| ~年収約370万円 | 56万円 | 56万円 | 60万円 |
| 市町村民税世帯非課税等 | 31万円 | 31万円 | 34万円 |
| 市町村民税世帯非課税 34万円 (年金収入80万円以下等) | 19万円(※) | 19万円(※) | 34万円 |
※介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。
払い戻しを受けるためには、介護保険者への申請が必要です。
申請手続きの内容や支給額については、加入している医療保険や介護保険の窓口に相談してみましょう。
公的介護保険料の減免・免除
公的介護保険料の減免や免除は、原則として難しいとされていますが、特定の条件に該当する場合は、減免・免除措置を受けられる可能性があります。
公的介護保険料の支払いが免除されるケースは、次のとおりです。
- 日本国内に住所がなく、海外に居住している
- 適用除外施設に入居または入院している
- 日本に短期滞在(3か月以内)している外国人
- 専業主婦を含めた40歳以上64歳以下の被扶養者
- 40歳以上64歳以下の生活保護受給者
また、次の条件に当てはまる方は、公的介護保険料の支払いが減免されます。
- 大幅な収入の減少があった
- 災害による被害を受けた
- 所得が低くて生活が困難
- 各市区町村独自の減免措置制度の条件に該当している
公的介護保険料の減免措置や免除措置の認定条件は厳しいです。
滞納する前に、各市区町村の窓口に相談しましょう。
各種補助金制度
介護に活用できる補助金制度を利用することで、介護費用の負担を軽減することも可能です。
介護中の家族や介護者が利用できる、国や自治体の補助金制度をいくつか紹介します。
- 家族介護慰労金の制度
- 高齢者住宅改修費用助成制度
- 介護手当(家族介護慰労金)
- 福祉用具購入費
- 居宅介護住宅改修費
- 介護休業制度(介護休業給付金)
- 介護休暇制度
介護費用の負担をさらに軽減したい場合は、民間の介護保険も活用できます。
各種補助金制度や民間の介護保険を最大限に活用して、介護の経済的不安に備えましょう。
介護保険負担限度額認定証に関するよくある質問
最後に、介護保険負担限度額認定証の申請に関するよくある質問に回答します。
預貯金額の調査を受けることはある?
預貯金額の調査を受ける可能性は否定できません。
厚生労働省が、保険者が必要に応じて、金融機関等に照会を行う場合があることを示唆しているからです。
つまり、不正受給が疑われる場合、保険者である市区町村は金融機関に対して、残高照会をする権限があります。
申請前に預貯金から多額の引き出しがあった場合、領収書などの支払いの証明がなければ、引き出し前の預貯金額で判定が行われることも把握しておきましょう。
夫婦で世帯分離している場合は?
夫婦で住民票を分けて世帯分離している場合でも、介護保険負担限度額認定証の判定の際に、配偶者の所得は合算されます。
婚姻届を提出していない事実婚の場合でも同じです。
本人と配偶者の世帯が住民税非課税世帯でない場合は、介護保険負担限度額認定証の認定を受けることができません。
ただし特殊なケースとして、配偶者が行方不明になっている場合や、配偶者からDVを受けている場合は対象外になります。
対象外のサービスは?
介護保険負担限度額認定証の対象外となる介護サービスは、次のとおりです。
- サービス付き高齢者向け住宅
- グループホーム
- 有料老人ホーム
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
上記のような民間の介護施設では、居住費や食費の軽減措置を受けることができません。
特別養護老人ホームや介護老人保健施設は、介護保険負担限度額認定証により介護費用の負担を軽くできるため、入所希望者が多く、入所待機となることが多いです。
民間の介護施設によっては比較的安価で利用できる施設もあるので、サービスの内容を比較してから選択することをおすすめします。
介護保険負担割合証との違いは?
介護保険負担割合証は、要介護・要支援認定を受けた介護保険被保険者に交付されるため、介護保険負担限度額認定証とは対象者が異なります。
介護保険負担割合証は、介護サービスの負担割合を示していて、利用者の所得額に応じた負担割合が記載されている書類です。
介護保険負担限度額認定証とは対象者だけでなく、対象となる費用にも違いがあります。
まとめ
今回は、介護保険負担限度額認定制度と、介護保険負担限度額認定証の申請基準、申請方法について解説しました。
介護保険負担限度額認定証は、誰にでも交付されるわけではありません。
所得と預貯金等の基準を両方満たしている場合に交付されます。
申請する前に、条件を満たしているかを確認しましょう。
介護保険負担限度額認定証があれば、介護施設の食費や居住費の負担を軽減することが可能です。
本記事で紹介した国や自治体の補助金制度を利用すれば、介護費用の負担をさらに軽くできるので、上手に活用して生活の安定を図りましょう。