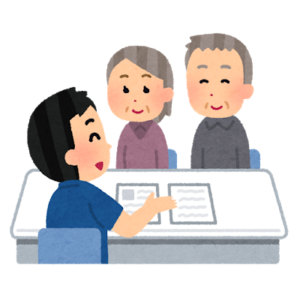ヘルパーができないことを一覧にして紹介!業務範囲や頼まれた場合の対処方法

ヘルパーの業務範囲は、介護保険のルールに基づき、ケアマネージャーが作成するケアプランで決まります。
しかし、現場では「これは引き受けてもいいのか?」と迷う場面もあるかもしれません。
本記事では、ヘルパーができること、できないことの具体例を一覧にして紹介し、対応に迷った場合の対処方法も解説します。
ヘルパーの業務範囲を適切に理解し、迷わず対応したい方は、ぜひ最後までご覧ください。
そもそもヘルパーとは?
初めに、そもそもヘルパーとは何をするのかを解説しておきます。
ヘルパーの正式名称や仕事内容を理解していきましょう。
正式名称は「訪問介護員」
ヘルパーは、自宅で生活しながら介助や支援が必要な方にサービスを提供する人のことです。
「ホームヘルパー」や「介護士」とも呼ばれますが、正式には「訪問介護員」といいます。
以前は「ホームヘルパー2級」と呼ばれていましたが、2013年4月に廃止され、現在は同じ役割を担う「訪問介護員」と呼ばれるようになりました。
訪問介護員として働くには、国が定めた「介護職員初任者研修」を受講する必要があります。
ヘルパーの主な仕事内容
ヘルパーの主な仕事内容は、以下のとおりです。
- 食事や排泄などの身体介助
- 調理や買い物、掃除といった生活介助
- 医師や看護師の指示の下でできる医療行為
- 通院や買い物時の移動支援
基本的には、上記4つの仕事をメインに行っています。
なお、介助や援助を受けられる方は、要介護認定1~5の判定を受けた方で、要支援1~2の方は、介護予防を目的とした支援が提供されます。
ヘルパーが基本的にできないこと
前述したように、ヘルパーの仕事は身体介助や生活支援、移動のサポートが中心です。
しかし、具体的にどのような仕事をするのかを詳しく知っている人は少なく、さらに業務範囲についても理解が十分でない場合があります。
そこで、この章ではヘルパーの具体的な仕事内容を知るために、対応外となる基本的な業務について詳しく説明します。
ケアプランに含まれていないサービス
ヘルパーが要介護者に提供するサービスは、ケアマネージャーが作成するケアプランに基づいて行われます。
ケアプランとは、利用する方が、どの程度のことを自分で行えるのか、どういった援助や介助が必要なのかをまとめた計画書です。
ヘルパーは、この計画書に基づいて支援を行い、プランに記載されていない内容については提供してはいけないと決められています。
要介護者自身でできること
ヘルパーの仕事は、要介護者が自力で行えない部分に対して行われ、要介護者自身ができることに関しては、自分でやってもらいます。
ヘルパーは家事のお手伝いをする人ではありませんので、調理や掃除が苦手といった理由で利用することはできません。
また、本人が家事できない状況でも、同居人ができる場合はサービス提供できませんので覚えておきましょう。
日常生活に関係のないこと
ヘルパーは、要介護者の食事や洗濯など、日常生活に必要なことをサポートします。
そのため、生活に直接関係のないことは対応できません。
例えば、庭の草むしり、ペットの散歩、要介護者とは関係のない買い物などです。
これらは毎日しなくても生活に支障がない、または要介護者の暮らしに直接関係がないと判断されるため仕事には含まれません。
もしどうしても必要な場合は、別の専門サービスに依頼する必要があります。
本人とは関係ない人の介護
ヘルパーの役割は、要介護者が自立した生活を送れるよう支援することです。
そのため、同居人や近所の方への介護や援助を依頼されても、基本的に対応できません。
また、同居人の洗濯や食事の準備、来客対応などもサービスの範囲外となります。
大掛かりな掃除や食事
引っ越しや大掃除、おせち料理といった大掛かりな掃除や食事もサービス提供できません。
これらは、毎日行わなくても要介護者の日常生活に支障はないと判断されるため、ヘルパーの業務には含まれません。
もし必要な場合は、専門の清掃業者や宅配サービスなどを利用する必要があります。
市区町村によってもできない範囲が違う
ここまで、ヘルパーが基本的にできない業務を紹介してきましたが、市区町村によっても業務範囲は変わってきます。
業務を行う中で、「この部分は支援すべき?」「やってよいのか分からない」など少しでも迷ったら、担当のケアマネージャーに確認することをおすすめします。
一般的には対応できない業務でも、市区町村によっては対応可能なケースもありますので、疑問に思ったら一度確認してみましょう。
ヘルパーができること・できないこと一覧
ここまで、ヘルパーの基本的な業務やできないことを紹介してきました。
しかし、サービスを受ける方の中には、「ヘルパー=家政婦さん」と思っている方が多いのが現状です。
ここからは、行える業務・行えない業務をさらに深掘りして紹介していきます。
ヘルパーができること
ヘルパーが提供できるサービスは、大きく分けて「身体介護」「生活援助」「医療行為」「その他」の4つに分類されます。
ここでは、それぞれの具体的な内容について詳しく説明していきます。
【身体介護】
身体介助とは、要介護者の体に直接触れて行う介助のことで、日常生活に必要な動作や移動をサポートするサービスです。
具体的には、以下の内容が含まれます。
| 食事 | ● 食事介助 ● 見守り |
| 入浴 | ● 入浴介助(全身浴・部分浴) ● 清拭 |
| 排泄 | ● トイレ介助 ● おむつ交換 |
| 移動・移乗・体位変換 | ● 歩行介助 ● 車椅子や椅子などへの移乗 ● 外出時の介助 ● 褥瘡(床ずれ)防止のための体位変換 |
| 更衣・身体整容 | ● 着替え介助 ● 洗髪・整髪・口腔ケア |
身体介助は、食事や入浴、排泄といった日常生活の中でも身体的なサポートを行う業務です。
サービス内容によっては専門的な知識やスキルが必要なため、「介護職員初任者研修」を受講し、「訪問介護員」を取得する必要があります。
【生活援助】
生活介助とは、掃除や調理など、要介護者の生活の中で必要な環境を整えるために行うサービスです。
具体的には、以下の内容が含まれます。
| 掃除 | ● 居室内(要介護者が使用する箇所のみ) ● トイレ・キッチン(家族と同居している場合は対象外) ● ゴミ出し |
| 調理 | ● 一般的な調理 ● 食事の片付け・洗い物 |
| 洗濯 | ● 洗濯(洗濯を干す・取り入れ・畳んで収納) ● アイロンがけ |
| 買い物 | ● 買い物(日常生活に必要なことのみ) |
| 整理整頓 | ● 衣類の整理 ● 衣類の補修 ● シーツ交換・ベッドメイキング |
対応できる業務は、基本的に要介護者に関係あることのみです。
要介護者と生活する上で関係のない居室の掃除や調理、洗濯などは行えませんので覚えておきましょう。
なお、郵便物の持ち込みや投函、受け取りは市区町村によって異なるため、確認しましょう。
【医療行為】
基本的にヘルパーが医療行為を行うことは禁止されています。
しかし、医療行為に当てはまらない行為や、医師や看護師の指示の下で行うことに関しては提供できます。
具体的には、以下の内容が含まれます。
| 体調管理 | ● 体温測定 ● 血圧測定(水銀血圧計は不可) ● パルスオキシメーターの装着 |
| 処置 | ● 傷の処置(軽い切り傷、すり傷、やけどなどの処置、ガーゼの交換) ● 市販のグリセリン浣腸の使用 ● インスリン注射の声かけや見守り ● 導尿のサポートのためのカテーテル準備、姿勢保持 |
| 投薬 | ● 指示された内服薬の服薬介助 ● 飲み忘れ確認 ● 湿布を指定箇所に貼る支援 ● 点眼薬の使用サポート ● 座薬の挿入サポート ● 鼻腔へのスプレー薬 |
| 身体ケア | ● 爪切り・爪やすり ● 耳掃除 ● 口腔ケア(歯ブラシや綿棒) |
上記がヘルパーが行える医療行為になりますが、本人の状態によっては医療行為と見なされる場合があります。
そのため、判断に迷ったら自分だけで判断せず、上司やケアマネージャーに相談しましょう。
なお、痰の吸引や経管栄養は医療行為に含まれますのでヘルパーは行えませんが、介護福祉士を取得している方や、必要な研修を修了した方に関しては、行える場合もありますので覚えておきましょう。
【その他】
ヘルパーがサービス提供できることには、そのほかにも通院時の介助や、外出時の付き添いなどがあります。
具体的には、以下の内容が含まれます。
| 通院 | ● 車椅子の準備・移動・乗り降り介助 ● 窓口での手続き ● 薬局への付き添い・薬の受け取り介助 |
| 外出 | ● 公共サービスの申請 ● 納税や選挙の代行 ● 免許更新の付き添い ● 銀行からの引き出し付き添い ● 住民票の代行取得 |
ヘルパーができないこと
ヘルパーが対応できない業務を一覧で紹介していきます。
【身体介護】
業務外となる身体介助は以下のとおりです。
| 身体ケア | ● マッサージ |
| 更衣・身体整容 | ● 散髪 |
身体介助に関しては、基本的に上記2つはできないと決まっています。
マッサージや散髪をする場合は、別のサービスに依頼する必要があります。
【生活援助】
業務外となる生活援助は以下のとおりです。
| 掃除 | ● 要介護者が使用していない居室の掃除 ● 庭の手入れや草引き ● 窓やベランダの掃除 ● 換気扇の掃除 ● ペットの世話 |
| 調理 | ● 同居人のための調理 ● 大掛かりな調理 |
| 洗濯 | ● 同居人の洗濯・洗濯物干し・収納・アイロン |
| 買い物 | ● 時間外となる買い物 ● 遠くのデパートでの買い物 ● お酒やタバコなどの嗜好品 ● お歳暮の購入 ● 来客用の買い物 |
| 整理整頓 | ● 大掛かりな裁縫 |
【医療行為】
業務外となる医療行為は以下のとおりです。
| 体調管理 | ● 水銀血圧計を使っての血圧測定 |
| 処置 | ● 専門的な判断が必要な傷の処置 ● 自己導尿 ● 摘便 ● 血糖値測定、インスリン注射 |
| 投薬 | ● 服薬管理 ● 医師や看護師に支持されていない投薬 ● 市販薬の投与や湿布の貼り付け |
| 身体ケア | ● 爪に異常がある場合の処置 ● 耳垢が詰まっている場合の耳掃除 ● 重度の歯周病がある場合の口腔ケア |
【その他】
業務外となるそのほかのサービスは以下のとおりです。
| 通院 | ● 院内での介助 ● 待ち時間の付き添い(場合によっては可能) ● 転院の付き添い |
| 外出支援 | ● 散歩(※ケアプランに含まれている場合は可能) ● 美容院への付き添い ● 法要や墓参りの付き添い ● 口座からの資金引き出しや管理 ● 教室やドライブ、行事への付き添い |
| その他 | ● 理由のない見守りや留守番、話し相手 ● 関係のない仕事の手伝い ● 車の給油、メンテナンス、清掃 ● 家具家電の移動、修繕、模様替え ● 室内外家屋の修理、ペンキ塗り |
ヘルパーができないことは誰に頼めばいい?
ここまで、ヘルパーが行える業務・行えない業務を紹介してきましたが、「誰に頼めばいいのか分からない」と相談されることもあると思います。
ここでは、ヘルパー業務に含まれないことは、どのようにすればよいのか、また依頼できる場所について紹介していきます。
自身で行う
ヘルパーの役割は、要介護者が自立した生活を送れるよう支援することです。
そのため、できないところはヘルパーが行い、それ以外は自身で行ってもらいます。
例えば、洗濯の際、「洗濯機への衣類や洗剤の投入やスイッチは要介護者に行ってもらい、洗濯物を干すことはヘルパーが行う」というように分担します。
このようにすることで自立につながることもありますので、あえてケアプランに含まれるケースも多いです。
家族が行う
要介護者が家族と一緒に暮らしている場合は、家族の状況も考慮しながらケアプランを作成します。
基本的には、要介護者が自分でできることはできる限り自分で行い、家族がサポートできる部分は家族が担当します。
それでも対応が難しい場合に、ヘルパーが必要な支援を行うという形です。
要介護者の自立を促しながら、家族の負担も軽減できるようバランスをとることが大切です。
ボランティア団体に頼む
要介護者自身や家族、ヘルパーでも行えないことは、ボランティア団体に依頼する方法もあります。
例えば、庭のお手入れや草引き、ペットの散歩などは、依頼するとよいでしょう。
ただし、ボランティア団体は地域によって依頼が難しい場合があり、また、問題が生じても補償してくれない可能性もあります。
そのため、依頼する際は、できる範囲や補償内容を確認するとよいでしょう。
シルバー人材センターに頼む
ヘルパーができないことは、シルバー人材センターに依頼することも可能です。
シルバー人材センターは、高齢者の働く機会や社会参加を支援し、地域への貢献を目指す団体です。
依頼すると、登録している高齢者が来てくれ、仕事を引き受けてくれます。
依頼する内容によっては引き受けが難しいケースもありますが、庭のお手入れや草引き、ペットの散歩、窓拭きといった簡単なことをお願いするとよいでしょう。
ほかのサービスを利用する
ヘルパーができないサービスは、ほかのサービスを利用することで解決できる場合もあります。
例えば、介護保険外のサービスや訪問看護サービスなどが挙げられます。
介護保険外サービスとは、介護保険が適用されない自費負担のサービスで、家事代行や外出支援など幅広い支援が提供できます。
また、訪問看護サービスとは、看護師が自宅を訪問し、医療的ケアや健康管理を行うサービスです。
そのほかにも、家事代行サービスに依頼するといった方法もあります。
これらのサービスは、ヘルパーができないことを行ってくれますが、全額自己負担であったり、医療的ケアが必要だったりするため、料金が高くなることに注意が必要です。
ケアマネージャーに相談する
要介護者やご家族から相談を受けた際に、自分だけでは判断が難しい場合は、迷わずケアマネージャーに相談しましょう。
特に、ご家族の急な用事や入院など、緊急性の高いケースでは、早めの対応が必要になることもあるでしょう。
そのような場合、状況に応じてケアプランの変更が可能なこともあります。
ヘルパーがやらざるを得ない状況もある
ヘルパーは基本的に、ケアプランに沿ってサービスを提供しますが、状況によっては例外的に対応せざるを得ない場合もあります。
例えば、なんらかの理由で廊下が水浸しになっていた場合、「廊下の掃除はケアプランに含まれていない」といって、そのまま帰るわけにはいきません。
このまま放置すれば、要介護者が転倒する危険性があり、安全面から考えても対応が必要です。
ヘルパーの役割は、要介護者の自立を支援することだけでなく、安全で快適に生活できる環境を整えることも含まれます。
そのため、緊急性がある場合や安全に関わる問題が発生した場合には、必要な対応をとることも重要です。
ただし、あくまで一時的な対応であり、根本的な解決が必要な場合は、家族や担当のケアマネージャーに相談し、適切な対処を検討することが大切です。
できないことを頼まれた場合の対処方法
ヘルパーの仕事をしていると、できないことを頼まれるケースは決して珍しくありません。
しかし、実際にできないことを断るだけだと、要介護者に申し訳ないと思い、どのように断ればいいのか悩んでしまうことも多いでしょう。
ここでは、できないことを頼まれるよくあるケースとその対処方法を紹介していきます。
できること・できないことを整理して伝える
できないサービスを断る際は、まず、できること・できないことを整理して、丁寧に伝えることが大切です。
そのためには、ケアプラン作成の段階で、記載されていないサービスや、要介護者に関係のない方へのサービスはできないことをはっきり伝えましょう。
トラブルを避けるためにも、できること・できないことをまとめた書類をもとに、事前に説明することが大切です。
もし、どうしても断れずに行ってしまった場合は、すぐに上司に相談して解決策を一緒に考えましょう。
頼まれることの多いケースと断り方
事前にできること・できないことを伝えていても頼まれることはあります。
頼まれることの多いケースと断り方は次のとおりです。
【ほかの家族の食事や洗濯】
「ついでだからやってほしい」と、ほかの家族の食事や洗濯を頼まれることは、よくあることです。
この場合は、できないことをはっきり説明した後に、「介護保険サービス外でなら対応可能です」と伝えましょう。
その際、料金は全額自費負担であること、具体的な金額も含めて伝えることが大切です。
【範囲外の掃除】
範囲外の掃除もよく頼まれるケースです。
特に多いのは以下です。
- ベランダの掃除
- 窓拭き
- 庭の手入れ、草引き
- 関係のない居室の掃除
- 同居人がいる場合のリビングやトイレの掃除
この場合も、介護保険サービスに含まれていないことをはっきりと伝えた後に、介護保険サービス外でなら対応可能であることを伝えましょう。
また、家事代行サービスなどの清掃業者を提案してみるのもよいでしょう。
【日用品以外の買い物】
「買い物ついでにお酒を買ってほしい」「タバコを買ってほしい」などの嗜好品の購入に関しては、基本的に禁止されています。
断る際は、「ヘルパーは要介護者の生活に必要なものしか買えない」ことを伝えた後に、「もし本当に必要なら介護保険サービス外での依頼になる」ことを伝えましょう。
もしくは「ご家族にお願いするのはどうでしょうか」といった代替案を進めてみるのもよいでしょう。
【冠婚葬祭やお墓参りの援助】
冠婚葬祭やお墓参りの援助も頼まれることが多いケースです。
この場合も、「介護保険サービス外となりますので、別のサービスを利用されてはどうですか」など、ほかのサービスを提案してみるのがよいでしょう。
【リハビリ・マッサージ・散歩】
リハビリやマッサージ、散歩については、専門知識やスキルが必要なため、ヘルパーにはできないサービスとなります。
断る際は、専門的な知識やスキルが必要で、ケガをさせてしまうおそれがあるため、サービス提供できないことを伝えましょう。
【市販薬の投薬や貼り付け】
薬の投薬や貼り付けは、医師や看護師の指示のもとに行ってよいとされますが、それ以外はしてはいけないことになっています。
そのため、断る際も「医師や看護師から指示されていないものに関してはできない」ことを伝えましょう。
また、必要であれば主治医に確認して大丈夫なら可能であることを伝えましょう。
【時間外のサービス提供】
ケアプランには要介護者に必要な援助や介護以外にも、利用する曜日や時間も記載されています。
そのため、ヘルパーは決められた時間内でしかサービス提供できないと決められています。
もし、予定外の時間のサービスを依頼された場合は、原則として対応できないことを伝え、介護保険外サービスや別の支援制度を活用する方法があることを提案しましょう。
ただし、緊急時や特別な事情がある場合は、ケアマネージャーに相談し、ケアプランの見直しや追加対応が可能か検討することが重要です。
まとめ
本記事では、ヘルパーができること・できないことや頼まれることの多いケース、断り方を紹介しました。
ヘルパーは要介護者の自立を支援し、決められた範囲内でサービスを提供します。
そのため、ケアプランにない業務や家族のサポートなど、対応できないこともあるのです。
しかし、状況によっては例外的に対応が必要な場合もあり、判断が難しいときはケアマネージャーに相談することが大切です。
ヘルパーが適切に役割を果たせるよう、利用者や家族もサービスの内容を理解し、必要に応じてほかの支援を活用しましょう。