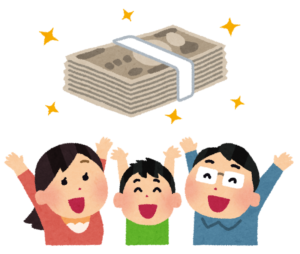認知症の4つの種類とは?症状や対応方法のポイントについて解説!

認知症にはいくつかの種類があり、それぞれに特徴や対応の仕方が異なります。
この記事では、代表的な4つの認知症の種類について、分かりやすく解説します。
身近な人の言動に変化を感じている方や、介護に関わる仕事をしている方は、ぜひ参考にしてください。
認知症とは
まず認知症はどのような症状が見られるのか、物忘れとの違いから解説します。
脳の認知機能が低下する症状
認知症は記憶力や判断力、理解力、注意力などの「認知機能」が徐々に低下していきます。
例えば、最近の出来事を思い出せなかったり、道順が分からなくなったり、簡単な計算や言葉の理解が難しくなったりといった症状が見られ、これらの変化が積み重なることで日常生活に支障をきたすようになります。
年齢を重ねるほど認知症の発症リスクが高いと言われていますが、若い年齢で発症するケースもゼロではありません。
進行すると家族や周囲の人の顔や名前を忘れることもあり、周囲の理解とサポートが必要となります。
物忘れとの違い
年齢とともに誰でも物忘れは起こりますが、認知症による物忘れとは性質が異なります。
物忘れとの違いについて詳しく紹介します。
【物忘れを自覚しているか】
通常の物忘れでは、本人が「忘れてしまった」と自覚していることが多いのが特徴です。
例えば「あの人の名前が思い出せない」と感じたり、自分で忘れたことに気づいてメモを取ったりするなどの対策をとります。
しかし、認知症の場合は忘れていること自体に気づかないケースが多く、家族や周囲の人が変化に気づいて初めて発覚することもあります。
【物忘れの範囲】
物忘れの範囲が広がることは、認知症の初期段階を示す兆候である場合があります。
日常的に使う物の場所を忘れたり、最近の出来事を繰り返し忘れたりする場合は、認知症の可能性も考えられるでしょう。
通常の物忘れでは、過去の出来事や知識はしっかり覚えているのが一般的ですが、認知症が進行するとその日の食事や自身の体験など、広範囲の記憶が薄れていくことがあります。
忘れている内容や頻度に注目し、早期発見に努めることが大切です。
認知症の4つの種類とは
認知症にはさまざまな種類があり、症状や進行具合が異なります。
ここでは、最も一般的な4つの認知症の種類について解説します。
①アルツハイマー型認知症
アルツハイマー型認知症は認知症の中で最も多く、全体の約半数を占めます。
この病気は、脳の神経細胞に「アミロイドβ」や「タウ」といったタンパク質が蓄積することで発症し、脳の機能が徐々に低下していきます。
初期は名前が出てこないなどの物忘れや、家事などこれまでできていたことができなくなる、簡単な計算ができなくなるといった症状です。
進行すると怒りっぽくなる、言葉が出にくくなる、失禁が起こるなどの症状が現れ、日常生活にも支障をきたすようになります。
②血管性認知症
血管性認知症は脳梗塞や脳出血などの脳卒中により、脳の血管に障害が生じ、脳への血流不足が原因で発症する認知症です。
また、発症部位によって症状が異なるため、「まだら認知症」とも呼ばれています。
認知症全体の約2割を占めるとされ、女性よりも男性に多くみられる傾向があるのも特徴です。
初期の症状は歩く速度が遅くなる、歩幅が狭くなるなどの歩行障害や意欲の低下がみられ、進行すると嚥下障害、構音障害、記憶障害、排尿障害、麻痺といった症状を伴い、感情の起伏が激しくなることもあります。
③レビー小体型認知症
レビー小体型認知症は、脳内に「レビー小体」と呼ばれるタンパク質が蓄積することで引き起こされる認知症であり、アルツハイマー型認知症の次に多いとされています。
この認知症の特徴的な症状は、認知機能の変動が激しく、日によって症状が良くなったり悪くなったりすることです。
症状として初期の段階では幻視や幻覚、認知機能の低下がみられ、進行すると運動障害(手足の震え、筋肉の硬直)がみられ、転倒しやすくなる場合や、パーキンソン病を発症するのも特徴です。
④前頭側頭型認知症
前頭側頭型認知症は、前頭葉や側頭葉の萎縮によって引き起こされる認知症で、平均発症年齢は55歳前後と比較的若年層に多いのが特徴です。
主に人格や行動の変化が見られ、社会的な判断力や感情のコントロールが難しくなり、自己中心的な行動を取ることが増える場合や、他者への配慮が欠けて無関心や冷淡な態度が目立つこともあります。
初期の段階から、万引きなどの反社会的な行動が現れるほか、同じ場所を何度も行き来したり、決まった時間に同じ行動を繰り返したりすることがあります。
認知症の中核症状と周辺症状について
認知症には中核症状と周辺症状があり、それぞれ異なる特徴を持ちます。
ここでは、それぞれの症状について詳しく解説します。
中核症状
認知症における中核症状は、脳の認知機能が低下することに伴って現れる症状です。
以下のような症状が、中核症状として現れることがあります。
- 記憶障害:新しいことが覚えられず、過去の出来事も忘れてしまう
- 見当識障害:時間や場所、自分がどこにいるのかが分からなくなる
- 実行機能障害:計画を立てたり、順序立てて行動したりすることができなくなる
- 理解力・判断力の障害:物事の意味を理解したり、適切に判断したりするのが難しくなる
- 失行:道具の使い方や身の回りの動作がうまくできなくなる
- 失認:見たり聞いたりしても、それが何であるか認識できない
- 失語:言葉がうまく出てこない、相手の話が理解できない
中核症状が進行することで、本人は日常生活の中で困難に直面するようになり、家族や介護者の支援が必要になります。
周辺症状
周辺症状は認知症に伴う心理的・行動的な変化であり、本人の性格や心理的ストレスや環境などが重なって、引き起こされるのが特徴です。
代表的な周辺症状には、以下のようなものがあります。
- 徘徊:家の中を歩き回ったり、外出しようとしたりする行動
- 幻覚:実際には存在しないものを見たり、聞いたりする症状
- 妄想:被害妄想など、事実とは異なる思い込みによって不安や混乱が生じる
- 暴力・暴言:介護者や周囲の人に対して暴力的な行為や言動をとる
- 介護抵抗:入浴や排泄、着替えなどに対して強く拒否する
- 抑うつ・不安・無気力:気分が落ち込み、意欲の低下が見られる
- 睡眠障害:昼夜逆転や不眠、夜間の覚醒などが起こる
- 不潔行為:排泄物を触る・壁に塗るなど、衛生的に問題のある行動
- せん妄:急に混乱し、興奮や錯乱状態になる
- 過食・異食:大量に食べたり、食べ物でないものを口に入れようとする行動
これらの周辺症状は、本人の不安や混乱が背景にある場合が多く、対応を間違えると症状が悪化することもあります。
認知症の予防と治療
認知症の進行を遅らせるためには、早期の診断と適切な治療が欠かせません。
治療には薬物療法や非薬物療法があり、それぞれの症状に合わせた対応が求められます。
ここでは、認知症の予防策と治療法について解説します。
予防について
認知症の予防には生活習慣を整えることが非常に重要であり、それが結果として認知症の予防にもつながります。
ここでは、生活習慣病の予防にも効果的とされる、食事・運動・コミュニケーションという3つの重要な要素について解説します。
【生活習慣病の予防をする】
生活習慣病(高血圧・糖尿病・脂質異常症など)は、特にアルツハイマー型認知症や脳血管性認知症の発症リスクを高める原因となります。
それぞれの生活習慣病に対しては、以下のような対策が予防に効果的です。
- 高血圧:塩分の摂りすぎを控える
- 糖尿病:血糖値のコントロールを心がける
- 脂質異常症:脂肪分の多い食事は避け、バランスの取れた食生活にする
このように、健康的な生活習慣を維持することは、認知症予防にもつながります。
【運動をする】
認知症の予防には日常的な運動の習慣が効果的で、特にウォーキングやジョギングといった有酸素運動は脳への血流を促進し、記憶や判断力などの認知機能を維持するうえで有効とされています。
また、筋力トレーニングやバランス体操などの無理のない運動も、身体機能の維持に役立ちます。
このように、運動は単なる体力作りにとどまらず、認知症予防や生活の質の向上を支える重要な要素といえるでしょう。
【栄養バランスの良い食事を摂る】
認知症予防には、脳に良い栄養を摂ることが大切です。
特に、DHAやEPAを含む青魚やビタミンEを多く含むナッツ類や野菜、抗酸化作用のあるフルーツなどが推奨されます。
また、食物繊維が豊富な食事を摂ることで血糖値の急激な上昇を防ぎ、認知症リスクを低下させる効果が期待できます。
食事は栄養バランスを重視しつつ塩分や脂肪分を控えめにし、適切なカロリー摂取を心がけましょう。
【人とコミュニケーションをとる機会をつくる】
認知症予防には孤独感を減らし、社会的な交流を持つことが大切です。
友人や家族との定期的な会話は脳を活性化させ、認知機能の低下を防ぐ効果があります。
特に、地域のサークル活動やボランティア活動への参加は、認知症予防だけでなく、心の健康にも良い影響を与えます。
治療について
認知症の治療は、進行を遅らせることを目指します。
薬物療法としては、認知症の進行を遅らせる作用がある薬が使用されますが、完治を期待するものではありません。
また、非薬物療法も重要で、認知症リハビリテーションや運動療法などが行われます。
ここでは、2つの治療法について解説します。
【薬物療法】
薬物療法は、認知症の進行を遅らせるために重要な役割を果たします。
主に中核症状が見られる場合に用いられ、症状の改善や安定を目的としていますが、完治を目指すものではなく、あくまで進行を遅らせるための治療法です。
薬物療法は医師の指示に従い、適切に使用しましょう。
なお、副作用が現れることもあるため、定期的な経過観察や調整が必要です。
【非薬物療法】
非薬物療法は主に周辺症状がみられる場合に用いられる方法で、以下のものが挙げられます。
- 脳トレ(認知訓練)
- 運動療法
- 音楽療法
- 回想法
これらの治療法は、薬物療法と併用することが一般的です。
認知症が進行する原因
認知症の進行を早める要因としては、脳への刺激が少ないことや病気の合併、周囲の理解不足などが挙げられます。
ここでは、認知症が進行する原因について詳しく解説していきます。
脳への刺激が少ない
認知症の進行を早める一因として、脳への刺激が少ない生活が挙げられます。
例えば、社会的な交流が少なかったり認知活動が少なかったりする場合、脳は十分に活性化されずに神経細胞の結びつきが弱くなり、認知機能が低下します。
日常的に頭を使うことや趣味を持ち、積極的に他者とコミュニケーションを取ることが認知症の進行を遅らせるために重要です。
病気が合併している
認知症の進行には、ほかの病気が影響を与えることがあります。
たとえば、高血圧や糖尿病、動脈硬化といった生活習慣病は脳の血流を悪化させ、神経細胞への酸素や栄養の供給を妨げるため、認知症の進行を早める要因となります。
また、心筋梗塞や脳卒中などの脳血管疾患も、認知症を悪化させる一因です。
こうした病気が合併している場合、認知症の進行を抑えるためには、病気の管理が非常に重要です。
本人に対して周りの理解が薄い
認知症が進行する原因の一つに、本人に対する周囲の理解不足があります。
認知症の症状は外からは分かりにくく、周囲の人がその変化に気づかないことも少なくありません。
症状が進んでいるにも関わらず、異常な行動として責められたり、適切な支援が受けられなかったりする場合、本人は強い不安やストレスを感じ、認知症がさらに進行しやすくなります。
そのため、周囲が認知症の症状を理解し、本人を思いやって接することがとても大切です。
早期に支援を開始し、安心できる環境を整えることが、認知症の進行を防ぐために役立ちます。
認知症の4つの種類に該当する症状がみられた場合の相談先
認知症の症状が現れた場合、早期に適切な相談先にアクセスすることが重要です。
認知症の診断には専門的な知識が必要であり、精神科や脳神経内科の医師による診断を受けることが基本です。
また、地域包括支援センターやかかりつけ医も、認知症の早期発見や対応方法についてサポートしてくれます。
ここでは、3つの相談先について解説していきます。
精神科や脳神経内科
認知症の診断と治療を受けるためには、精神科や脳神経内科に相談しましょう。
これらの医療機関では、脳の画像検査や認知機能の検査を通じて、認知症の症状を詳しく診断してもらえます。
前述の4つの認知症の種類によって治療法が異なるため、専門的な診断を受けることが不可欠です。
薬物療法や非薬物療法についても、患者の状態に応じた治療法のアドバイスを受けることができます。
地域包括支援センター
地域包括支援センターは、認知症のサポートを提供する地域の重要な拠点です。
ここでは、認知症の進行に関する相談や、要支援・要介護認定の手続き、日常生活の支援についてアドバイスを受けることができます。
また、認知症の本人とその家族に対して介護サービスや福祉サービスの利用方法、地域での支援制度に関する情報を提供しています。
専門スタッフが親身に対応してくれるため、認知症の症状に気づいた際に相談する場所として非常に便利です。
かかりつけ医
かかりつけ医がいる場合はまず最初に相談し、必要に応じて専門医への紹介を受けるのが一般的です。
認知症は本人に自覚がないことも多く、いきなり見知らぬ精神科や脳神経内科を受診することに抵抗を示す場合があります。
その点、かかりつけ医は本人と信頼関係を築いており、既往歴や生活習慣、健康状態をよく理解しているため、認知症の兆候にも早期に気づきやすい存在です。
さらに、認知症の進行を見守りながら、本人に合った治療や生活支援を提案してくれるため、長期的なケアを行ううえでも重要な役割を担っています。
認知症の人に接する際の3つのポイント
認知症の人に接する際は、適切な対応が大切です。
認知症の方は記憶や判断力が低下しているため、ストレスを感じやすく、誤解を招くこともあります。
続いては、認知症の方と接する際に気をつけるべき3つのポイントをご紹介します。
驚かせないこと
認知症の方には予測できない行動や言動が見られることがあるため、驚かせないよう配慮することが大切です。
本人の行動に対して周囲が戸惑った様子を見せたり、思わず声を上げてしまったりすると、認知症の方に不安や混乱を与え、症状が悪化する可能性があります。
何かが起きた場合でも焦らず冷静に対応し、優しく説明することで安心感を与えることができます。
また、認知症の方は生活の中での急な変化にも敏感なため、環境や状況を予測して整えて安定した気持ちで過ごせるように配慮しましょう。
自尊心を傷つけないこと
認知症の方は記憶や判断力の低下により、日常生活で困難を感じることが増えていくため、自尊心を傷つけないよう配慮することが大切です。
できたことを認めて褒めたり、サポートを自然な形で提案したりすることで、本人の自尊心を守ることにつながります。
ただし、子どもをあやすような声かけは避け、あくまで一人の大人として尊重する姿勢が大切です。
また、本人が間違ったことを言った場合も否定せずに、傾聴する姿勢が大事です。
急がせないこと
認知症の方に接する際は、急がせないことが大切です。
認知症の進行により行動や思考に時間がかかることがありますが、急かすことは認知症の方にプレッシャーを与え、不安を募らせてしまいます。
時間に余裕を持って対応し、急がせずにゆっくりとしたペースで支援を行いましょう。
急がせることなく本人が自分でできる範囲を見守りながら、手助けが必要な場合は優しく声をかけることが大切です。
認知症の方にとって無理に急かされないことで安心感を得ることができ、穏やかな日常生活を送ることができます。
その他の認知症について
認知症には、これまでにご紹介した4つの主要なタイプのほかにも、さまざまな種類があります。
ここでは、それら一般的な認知症以外のタイプについて、いくつかの例を挙げながら解説します。
認知症の種類を理解し、それぞれに合った対応を早期に取ることが、進行を防ぐうえでも非常に重要です。
若年性認知症
若年性認知症とは、65歳未満の人に発症する認知症を指します。
通常の認知症とは異なり、仕事や家庭での役割が大きい時期に発症するため、生活への影響が深刻になりやすいのが特徴です。
症状は、アルツハイマー型や血管性認知症といった一般的なタイプと同様のケースが約6割を占めるといわれていますが、若さゆえに「疲れのせい」や「ただの物忘れ」と誤解されやすく、発見が遅れやすいというリスクもあります。
そのため、若年性認知症は早期発見・早期対応が非常に重要です。
アルコール性認知症
アルコール性認知症は、長期間にわたる過度なアルコール摂取が原因で発症する認知症です。
大量のアルコール摂取は脳にダメージを与え、脳血管障害やビタミンB1欠乏などの栄養障害を引き起こし、これが記憶力や認知機能の低下を招きます。
アルコール性認知症の特徴として、記憶障害や判断力の低下に加え、情緒の不安定や精神的な症状が現れることもあります。
この認知症を予防するためには、アルコール摂取を控えめにし、適切な飲酒習慣を身につけることが重要です。
進行性核上性麻痺
進行性核上性麻痺は、パーキンソン症候群に分類される病気の一つです。
主な症状には、歩行の困難や眼球の上下運動の障害があり、さらに認知機能の低下や嚥下障害(飲み込みづらさ)といった問題も現れるようになります。
主に「すくみ足」や「加速歩行」といった特徴的な歩行の変化が目立ち始めてから、ようやく異常に気づかれるケースが少なくありません。
この病気はパーキンソン病と比べて進行が早く、現在のところ根本的な治療法は見つかっていないのが現状です。
なお、進行性核上性麻痺は、厚生労働省の特定疾患治療研究事業の対象となるパーキンソン病関連疾患として認定されています。
大脳皮質基底核変性症
大脳皮質基底核変性症は、パーキンソン症状と大脳皮質の障害による症状が同時に現れる、まれな神経変性疾患です。
発症頻度は人口10万人あたり約2人と非常に低く、遺伝的な傾向や男女差も確認されていません。
この病気は典型的な症状のパターンが少ないため、ほかの神経疾患との区別が難しいという課題があります。
代表的な特徴としては、症状が体の片側に偏って現れることが挙げられます。
手足の動きがぎこちなくなる、筋肉のこわばりが出る、歩行に支障をきたすといった運動障害が見られ、そこから病気に気づくケースも少なくありません。
進行は比較的ゆっくりとしていますが、発症から5〜10年ほどで寝たきりの状態になることが多いとされています。
神経原線維変化型老年期認知症
神経原線維変化型老年期認知症は、認知症全体の中では非常にまれなタイプで、特に90歳以上の高齢者に多く見られます。
この認知症は、記憶障害がゆっくりと進行するのが特徴で、他の認知機能は比較的保たれていることが多いです。
そのため、言語障害や異常な行動などの症状が現れることは少なく、他の認知症と比べると比較的穏やかな進行が見られます。
しかし、診断時にはアルツハイマー型認知症と誤診されることもあり、正確な診断と注意深い対応が求められます。
正常圧水頭症
正常圧水頭症とは、脳脊髄液が脳の周囲に異常に溜まり、脳を圧迫する状態のことです。
通常、脳脊髄液は脳の保護や栄養供給、老廃物の除去、脳内の圧力調節といった重要な役割を果たしていますが、何らかの原因でこの液体が特定の場所に過剰に溜まることで、脳への圧力が増加します。
正常圧水頭症は厳密には認知症ではありませんが、その症状が認知症に非常に似ているため、詳細な検査を行わなければ誤診されることがあります。
症状としては、記憶障害や認知症に似た認知機能の低下に加え、歩行の障害や排尿の問題が見られることが特徴です。
この疾患は認知症とは異なり、早期に適切な治療を開始すれば、改善または完治が可能とされています。
嗜銀顆粒性認知症
嗜銀顆粒性認知症(しぎんかりゅうせいにんちしょう)は、主に70~80代の高齢者に発症し、記憶障害をはじめ、興奮、妄想、不機嫌などの症状が現れます。
アルツハイマー型認知症と比較して、怒りっぽさや、それに伴う攻撃的な行動異常が目立つのが特徴です。
このような感情の変化や行動の制御が難しくなることが多いため、周囲とのトラブルが増えることがあります。
認知症全体の5%~10%を占めるとされる嗜銀顆粒性認知症は、発症初期にはほかの認知症、特にアルツハイマー型認知症や精神疾患と誤診されることが多いのが課題です。
炎症
細菌やウイルスが原因で脳炎を発症すると、その後遺症として記憶力や判断力の低下など、認知機能に障害が残ることがあります。
このような場合、認知症と似た症状が見られることがありますが、多くは進行性ではなく、ある程度のところで症状が落ち着くのが特徴です。
ただし、自己免疫性脳炎や進行性のウイルス感染など、慢性的かつ進行性に脳に炎症が生じる疾患では、認知症のような症状が次第に悪化するケースもあります。
そのため、症状の経過や原因疾患を正確に把握し、適切な治療と経過観察を行うことが重要です。
脳腫瘍
脳腫瘍が原因で認知症のような症状が現れる場合、手術で腫瘍を除去したり、縮小させる治療を行うことで、症状の改善が期待できることがあります。
また、転倒によって頭部を強く打ったあとに認知症のような症状が現れる際には、「慢性硬膜下血腫」や「硬膜外血腫」といった出血性の疾患が関係しているケースもあります。
さらに、脳脊髄液が過剰に溜まることで脳を圧迫し、正常な機能が妨げられる「正常圧水頭症」の場合は、認知機能の低下だけでなく、歩行障害や尿失禁などの症状が同時にみられることがあるので注意しましょう。
まとめ
認知症は主に、アルツハイマー型認知症・血管性認知症・レビー小体型認知症・前頭側頭型認知症の4つの種類に分けられます。
認知症の予防には運動やバランスの良い食事、社会参加が効果的であり、進行を遅らせるには薬物療法と非薬物療法の併用が有効です。
気になる症状が見られた場合は早めに医療機関や支援センターに相談しましょう。