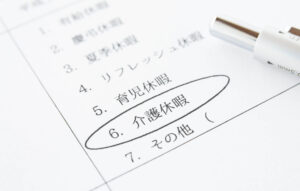介護と介助の違いとは?定義や業務内容、注意点もそれぞれ解説!

介護と介助の違いについて、詳しく知らない方も多いでしょう。
介護業界に興味を持つ方は、それぞれの違いを押さえておくことは大切です。
本記事では介護と介助の違いを分かりやすく解説し、それぞれの業務内容も詳しく紹介していきます。
介護業界を目指している方は本記事を参考にして、知識を深めておきましょう。
介護と介助の言葉の違いとは?
介護と介助は似たような言葉に見えますが、違いがあります。
それぞれの意味や定義を解説していくため、専門用語の違いに対する理解を深めましょう。
介護:生活に必要な支援全般をサポートする
介護とは、何らかの理由で自立した生活が難しい方へのサポート全般のことです。
年齢による筋力の衰えや病気、もしくは先天的・後天的な障がいによる身体の不自由により、自立支援が必要な方への世話や看護などを指します。
被介護者によってサポートしてほしい内容は異なるため、一人ひとりに合わせたサポートを行うことが大切です。
介助:日常生活をサポートする
介助とは、日常生活で必要な起居動作をサポートする行為そのものを指す言葉です。
起居動作とは寝返りや歩行の保持などの動作を指します。
介助の具体的な内容としては食事や入浴の手助け、着替えのサポートなどさまざまです。
介護と同様に、被介助者がどのようなサポートを求めているか確認したうえで、対応することが重要です。
その他の言葉との違い
介護と介助以外に、介護業界で利用される言葉との違いも解説していきます。
とくに介護士を目指している方は覚えておくと役に立つため、チェックしておきましょう。
【介助と援助の違い】
介助はサポートの行為そのものを指す用語であるのに対し、援助は「困った方を助ける」「手を差し伸べる」という意味です。
介護業界では「生活援助」という言葉がありますが、これは利用者ができないことを代わりに行うことを指します。
たとえば重い荷物を持てない利用者に代わって、買い物に付き添い荷物の持ち運びを手伝う行動が援助に該当します。
介護以外にも、資金を援助するなどの意味で使用される言葉です。
【介助と補助の違い】
介助と補助に、明確な意味の違いはありません。
もともと補助とは「足りない部分を補う」ことを指す言葉です。
たとえば食べることはできるが口に食べ物を運べない利用者に、介護士が口まで食べ物を運ぶ行為は「補助」に該当します。
しかし、この行為自体は「食事介助」と呼ばれるため、補助は介助に含まれるともいえます。
介護と介助の業務内容の違い
言葉の意味を整理したところで、続いては介護と介助の業務内容の違いを解説していきます。
理解を深めるためにも、じっくりと目を通しましょう。
介護の業務内容
介護に含まれる業務内容には、大きく「身体介護」と「生活援助」があります。
それぞれの実施目的や業務範囲を、詳しく解説していきます。
【身体介護】
利用者の身体に直接触れて介助を行う行為が「身体介護」です。
自立支援のサポートや身体機能低下の重症化防止、生活の質の向上などが主な目的です。
すべての介助を行うわけではなく、利用者に応じて必要な介助内容を決めて、作成されたケアプランに沿って行います。
介護士や家族、利用者などが変更を要すると判断した場合は、プランが見直される場合もあります。
【生活援助】
利用者の身体には直接触れずに、身の回りの世話・サポートをする行為を「生活援助」と言います。
援助対象は本人となるため、同居家族は含まれません。
加えて庭の手入れやペットの世話といった、利用者に直接関わらない援助も対象外です。
訪問介護において、同居家族から「一緒にご飯も用意してほしい」などと要望をもらう事例があります。
しかし介護保険外のサービス提供となるため、注意しましょう。
介助の業務内容
身体介護の主な業務内容は、以下のとおりです。
- 食事介助
- 排泄介助
- 入浴介助/清拭・陰部洗浄
- 更衣介助
- 移乗介助
- 歩行介助
1つずつ業務内容を見ていきましょう。
【食事介助】
1人で食事することが困難な方に行うのが「食事介助」です。
たとえば、口まで食べ物を運んだり、食事の様子を観察したりします。
一人ひとり嚥下力や咀嚼力が異なるため、介助の際は様子を見ながら食べ進める必要があります。
加えて、食事の様子から「噛みにくそう」「飲み込みにくそう」といった状態を読み取ることも重要です。
生活の質を向上させたり、訓練の必要性を判断したりするためにも観察は欠かせません。
【排泄介助】
排泄動作ができない方や、排泄機能に障がいがある方に行うのが「排泄介助」です。
たとえば、オムツ交換やトイレへの誘導などが該当します。
ただ単に援助するだけではなく、排泄物や皮膚の状態から体調の変化をチェックする目的もあります。
排泄援助は非常にデリケートな内容であるため、自尊心を傷つけないように配慮が必要です。
【入浴介助/清拭・陰部洗浄】
入浴介助や清拭・陰部洗浄は、一人での入浴が困難な方や、入浴そのものが困難な方に行います。
体を清潔に保つほか、体を温めてリラックスさせる目的があります。
入浴介助では、衣類の着脱や洗髪などのサポートを行うのが主な業務です。
もしも入浴が難しい場合は、温かいタオルで全身を拭き取る「清拭」や、温かいお湯で汚れを洗い流す「陰部洗浄」を行う場合もあります。
要介護度やそのときの体調によって、入浴方法を検討することが大切です。
【更衣介助】
一人で着替えを済ませるのが困難な方に行うのが「更衣介助」です。
筋萎縮や関節の可動域が狭い方や、体に麻痺があり手足をスムーズに動かせない利用者が対象です。
更衣介助では着替えを手伝うほか、季節にあった衣服を選んだり、伸縮性がある生地を探したりします。
要介護者は衣服を選ぶのが難しいため、利用者の状態に合わせて着やすい衣服を考えるのも業務の一つです。
【移乗介助】
1人で別の場所への移動が困難な方に行うのが「移乗介助」です。
ベッドから車椅子へ移ったり、車椅子からトイレへ行ったりする行為を手伝います。
移乗介助は腰に負担がかかりやすいため、ボディメカニクスを活用したり利用者に協力してもらったりしましょう。
たとえば利用者に腕を首に回してもらう、てこの原理を利用する、腹筋に力を入れるなどの工夫が必要です。
不安な方はスクワットや腹筋・背筋トレーニングをして、筋力を上げると良いでしょう。
【歩行介助】
スムーズな歩行が難しい方に行うのが「歩行介助」です。
筋力の低下や片麻痺がある方は、通常の歩行でも転倒リスクが高まるため、転倒リスクを軽減するために行われます。
主に、寄り添って歩行を援助したり、階段の上り下りをサポートしたりします。
介助方法には種類があり、利用者の状態や補助用具の使用有無によって介助方法が異なるのが特徴です。
その他の介助業務
上記で紹介したのは主な介助業務ですが、その他にも該当する業務があります。
業務内容や実施内容を確認していきましょう。
【移動介助】
移動介助とは、歩行や移動そのものが難しい方を手助けする行為です。
たとえば、車椅子を押す行為が該当します。
とくに車椅子を押す際は、スピードや段差に注意しなければいけません。
スピードが速いと利用者は恐怖を感じてしまうため、ゆったりとしたペースを心がけてください。
また段差がある場合は、ティッピングレバーを踏み込む必要があります。
踏み込む際は力加減に注意し、前輪が過度に上がらないようにしてください。
【外出介助】
外出介助とは、一人で外出が難しい方をサポートする介護サービスの一環です。
病院への通院やデイサービスへの付き添い、日用品の買い物など、生活を支えるための外出をサポートします。
また、外出することで気分転換を図る目的もあります。
ただし日用品以外の買い物や外食、趣味に関する外出などは対象外であり、必要性や対象範囲を考慮することが重要です。
介助の4段階の違いとは?
介助では、介助が必要とされるレベルに応じて以下の4つの段階に分けられます。
- 自立
- 一部介助
- 半介助
- 全介助
自立は、日常生活の動作をすべて自力で行える状態を指します。
この段階では直接的な介助は必要なく、利用者が自分らしい生活を送れるよう見守ることが主な役割です。
必要に応じて、福祉用具や環境整備のサポートを行うことがあります。
一部介助は、基本的に自分で行動できるものの、特定の動作に不安があり部分的な支援が必要な状態です。
ふらつきを防ぐための見守りや、手を添えた誘導が該当します。
半介助は、ある程度は自力で行えるものの、特定の部分で介助が必要な段階です。
排泄時に便座への移乗はできても、衣類の上げ下げにサポートが必要な場合などが該当します。
ただし、過剰介助にならないよう注意しましょう。
全介助は、利用者がすべての動作において介助を必要とする状態です。
たとえ全介助が必要であっても、利用者が可能な範囲で自分の力を発揮できるようサポートすることが大切です。
利用者の声に耳を傾け、自立支援を目指した介助が求められます。
介助・介護する際の3つの注意点
介助・介護する際は、以下の3つに注意しましょう。
- 動作を急がない
- 一声かけてから行う
- 体の構造・動きに合わせて介助する
では、1つずつ解説していきます。
動作を急がない
身体介護の際は突然体を持ち上げたり、急いで歩かせたりしないようにしましょう。
体を痛めたり転倒リスクが高まったりする恐れがあるからです。
とくに関節に痛みがある方や麻痺がある方、筋力が低下している方などに、急激な動作を行うのは危険です。
動きのスピードは利用者一人ひとりに合わせて、適度に行いましょう。
一声かけてから行う
高齢者や障がい者を問わず、人は突如とした動きに弱く身体の反応が遅れます。
頭で理解したのちに行動をしなければ、ケガのリスクを上げるだけでなく、恐怖や不安を持たせてしまう恐れがあります。
「今から〇〇します」などと、宣言してからの行動を意識しましょう。
体の構造・動きに合わせて介助する
体の可動域や動く向きは決まっているため、それに反する動きをするのは危険です。
最悪の場合、骨折や脱臼を発症する可能性があります。
また、怪我まではいかなくとも痛みが伴い、介護士に対する不満や不信感が生まれる原因にもなります。
介護士にとっても、無理に体を動かすのは怪我に繋がるためよくありません。
双方にとって負担が少ない介助スキルを身に付けましょう。
まとめ
介護は生活に必要な支援全般を指し、介助は日常生活をサポートすることを表します。
似たような意味の専門用語の違いを正確に理解し使いこなすことができれば、利用者に適した介護サービスの提供に繋がるでしょう。
また介護と介助は業務内容にも違いがあるため、それぞれ理解しておくことが重要です。
言葉の違いを整理しておきましょう。