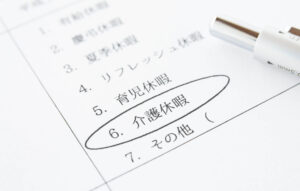介護で欠かせないアセスメントとは?実施する際の手順や把握すべきポイントを解説!

介護をするうえで利用者がどのような生活を送っているかや、どのようなサポートを希望しているかを把握することは非常に重要です。
ケアマネジャーは、介護を必要とする人の生活状況などから求めるサポートなどを把握して、ひとりひとりに合ったケアプランを立てます。その際に重要な役割を果たすのが介護におけるアセスメントです。
今回は、「アセスメントとはどのようなものか」や、「アセスメントを実施する際に気をつけるべきこと」などを紹介しています。利用者に満足してもらえるケアプランを立てたいなら、アセスメントについてしっかり把握しておきましょう。
介護に欠かせないアセスメントとは?
介護を必要とする人はどの程度のサポートが必要かを判断するために、レベルがわけられています。しかし、介護レベルが同じだからといって介護職員が同じサポートを提供しているわけではありません。
それは、介護を必要とする利用者ひとりひとりに合ったサービスを提供することが重要だからです。レベルが同じ人たちすべてに決まったサービスを提供していると、利用者ができることまで支援してしまい自立する力を奪ってしまいかねません。
ここでは、ひとりひとりに適した介護サービスを提供するために欠かせないアセスメントや、サポートするために必要なことを紹介しています。
利用者が納得できるケアプランを立てるために欠かせないもの
介護職員は身の回りのことすべてをサポートするわけではなく、できることは利用者本人で取り組んでもらう方がよいこともあります。QOLを向上させるためにも、利用者がおこなう部分と介護職員がおこなう部分を利用者ごとに把握しなければなりません。
介護に欠かせないアセスメントとは、介護職員によるサポートを受ける利用者の状況や希望に合ったサービスを提供するために必要なものです。このアセスメントがしっかりと機能していないと利用者が満足できるサービスは提供できません。
納得してもらえる介護を提供するには、利用者の状況に合っていて希望にもマッチしているケアプランを立てる必要があります。介護を提供する職員は利用者本人やその家族の状況や希望を理解することから始めますが、ケアプランを立てるためには情報収集がマストです。
“アセスメント=評価・査定”などの意味を持ちますが介護分野に当てはめると、最適なサービスを提供するために立てるケアプラン作成に不可欠なものといえます。現在の状態や希望などの情報を総合的に判断して、適切な介護プランを作成するという流れです。
そのためには、まず情報収集が必要ですが、具体的にチェックする内容は以下のとおり。
- 身体機能
- 心身の状態
- 悩み
- 環境
- 生活歴
- 価値観
身体機能などに加え、悩みや価値観など心の状態にも着目します。介護を受けることについてどのような想いがあるかを理解しなければ、介護サービスの利用に納得してもらうことは難しいです。
介護を受ける本人はもちろん、家族がどのように思っているかや、利用者が家族に対して抱いている想いなども把握しなければなりません。家族だからといって想いが同じではなく、考えが異なることや認識の違いが生じていることもあります。
そこで大きなズレがあると介護を利用するときも不満が生じる可能性があるため、それぞれが納得できる形を目指すのが望ましいです。また、さまざまな情報を集めて問題や課題を明らかにすることで必要な介護サービスがわかるため、利用者が納得できるケアプランを立てるためにもアセスメントは非常に重要なものといえます。
アセスメントをもとにケアプランを作成するのはケアマネジメントの専門家であるケアマネジャーがおこなうことが一般的です。
アセスメントとモニタリングはどのような違いがある?
アセスメントの重要性を紹介しましたが、意味合いが似ていることもあり混合されやすいのが“モニタリング”と呼ばれるものです。モニタリングは、作成されたケアプランをチェックする意味合いを持ちます。
情報収集をしてアセスメント、ケアプランの作成という流れですがケアプランが作成されて利用者が納得すると実際に介護サービスが提供されます。サービスが提供されたらそのまま利用者が希望するまでサービスを提供し続けるだけではなく、適切なサービスが提供されているかをチェックしていきますがこれがモニタリングです。
介護サービスを提供していくなかで見えてくる改善点や、課題や気づきなどがあればそれに応じて対応していきます。また、利用者や家族が介護サービスを利用してから感じることもあるでしょう。
想像と体験してからでは感じ方も異なるため、そのような想いも汲み取ります。利用者の身体機能や心身の状態などが変わってくることもあるため、そのようなときは変化に合わせて再度ケアプランを練り直します。
1度考えた介護サービスを提供し続けて終わりではなく、その後も状況を確認し問題がないかモニタリングしてくれるとわかると利用者も安心して介護サービスを受けようと感じられるでしょう。
アセスメントをおこなう手順を紹介
アセスメントをおこなうときは、準備することや面談当日までにしておくことがあります。スムーズに進められるように必要な事前準備や自宅へ訪問した日の流れなどを紹介します。
前述したようにアセスメントは今後の介護サービスの提供においても非常に重要な役割を果たすものなので、利用者が満足して介護サービスを受けられるように手順を把握しましょう。
アセスメントをおこなう事前準備
介護サービスを利用しようと考えている人が生活している自宅に訪問してアセスメントをおこないます。アセスメントをおこなうためには、段階的に準備しておくものがあります。
まず、インテークと呼ばれる初回面談をおこない介護サービスなどについて説明を実施。面談をしてから介護サービスを利用したいという意志が確認できたら、アセスメントで自宅訪問という流れです。
アセスメントをおこなう前にも、ステップがあることを把握しておきましょう。初回面談のインテークをおこなうには、利用者や家族の都合がよい日時を聞き取り面談を設定することから始めます。
日時調整の連絡を入れるときは、おおよその面談に要する時間や、必要なもの、面談をおこなう目的などを伝えておくとよいです。また、初回面談までにわかる範囲で面談者の情報をまとめておくと、インテーク当日により充実した会話がおこなえます。
初回面談は本人や家族も緊張していることも珍しくないため、ケアマネジャーがいかに安心させられるかにかかっています。気持ちに寄り添ったり、提供している介護サービスなどをわかりやすく説明したりと知りたいことなどを把握できると安心して任せられると評価してもらえるはずです。
そのため、まずは意向を確認したり信頼関係を築いたりすることを意識しましょう。インテークが終了するとアセスメントですが、それまでに主治医などから情報収集しておくことも必要です。
アセスメント実施当日の流れ
アセスメント当日は利用者の生活している自宅に訪問してどのような状況で生活を送っているかを目で見て、体感して確認します。具体的な流れは以下のとおり。
- 自宅周辺の環境をチェック
- 家のなかをチェック
- 集めた情報を総合して確認
- 大まかな方向性を提示
- 今後の流れを確認
家のなかだけではなく自宅周辺の環境や、玄関ドアのタイプ、家のなかに入るまでの段差なども生活するうえで関わってくる部分なのでしっかりチェックします。家のなかはおもに生活している自室だけではなく、お風呂場やトイレ、階段などもそれぞれ確認。
段差や扉など危険となりうる可能性のある場所やものなども、抜かりなくチェックしておきます。家のなかを案内してもらいながら並行して気になっている箇所などがないか聞き取りをしていくと、その場で確認でき本人や家族も実際の生活をイメージしやすいので普段感じていることを忘れずに話してもらえます。
全体の部屋のチェックが終わったら、再度認識していることに間違いがないかひとつひとつ確認していきましょう。その際も困っていることや気になっていることがないか聞き取りをおこないます。
これらの情報を持ち帰って適切なプランを作成していきますが、アセスメントをおこなった現時点で大まかな方向性を提示すると今後の流れが掴めて安心してもらえます。ただし、細かい内容は別日に改めて説明することを伝え問題がなければ、今後の流れを説明し訪問での確認は終了です。
長時間の訪問や説明は体力面や精神面でも負担になるため、1時間程度を目安にしておきましょう。
アセスメント実施後にするべきこと
自宅訪問のアセスメントを実施したら、そのときに集めた情報などをもとにケアプランの作成に移ります。ケアプランができあがったら利用者や家族に説明し、同意を得ることが必要です。
ケアプランに同意が得られると、介護職員による介護サポートの提供が可能です。実際に利用者が介護サポートを受けてみて想像と違った、こうしてほしいなどの要望が出てくることもあると思います。
そのようなことを聞き取る面談がモニタリングで、介護サポートを開始してからおよそ1ヵ月のタイミングでおこなわれます。その面談で挙がった問題点や改善点があればケアプランを再度見直し、修正や変更を加え新たなサポートを提供していくという流れです。
モニタリングも1回で終了ではなく、数ヵ月に1回など利用者の状況や状態などに合わせておこなわれます。アフターフォローも万全だと利用者も安心して介護サービスを受けられます。
インテーク、アセスメント、ケアプラン作成、定期的なモニタリングを通して、しっかりサポートしてくれるとわかると利用者や家族の不安も減らせるので、順を追って万全の対応をしてサポートしていきましょう。
アセスメントをおこなうときの5つのポイント
アセスメントは今後の介護サポートを提供するときに非常に重要なものですが、実施するときは5つのポイントに沿って対応すると質の高いサービスが提供できます。専門的な知識やスキルをもとに説明することも重要ですが、まずは利用者や家族に寄り添うことが最も必要なことです。
利用者のなかのひとりという立ち位置になりがちですが、利用者にとっては今後の人生を預ける重要な選択でもあります。そのようなことを忘れずしっかりと向き合う姿勢を忘れないようにしましょう。
アセスメントシートに沿って状況を把握する
アセスメントではケアプランのもととなる情報を集めることが必要ですが、集めるべき情報は厚生労働省のアセスメントシートによって項目が決められています。アセスメントシートは基本情報に関する9つの項目と、課題分析に関する14の項目の計23項目が提示されています。
詳細は以下のとおり。
基本情報に関する項目
- 基本情報(受付、利用者等基本情報)
- これまでの生活と現在の状況
- 利用者の社会保障制度の利用情報
- 現在利用している支援や社会資源の状況
- 日常生活自立度(障害)
- 日常生活自立度(認知症)
- 主訴・意向
- 認定情報
- 今回のアセスメントの理由
課題分析(アセスメント)に関する項目
- 健康状態
- ADL
- IADL
- 認知機能や判断能力
- コミュニケーションにおける理解と表出の状況
- 生活リズム
- 排泄の状況
- 清潔の保持に関する状況
- 口腔内の状況
- 食事摂取の状況
- 社会との関わり
- 家族等の状況
- 居住環境
- その他留意すべき事項・状況
引用:https://www.mhlw.go.jp/content/001157205.pdf
繰り返しおこなってきた業務であっても23もの項目があると何もない状態だと聞き漏れることもあるため、アセスメントシートを使用すれば確認漏れも防げます。アセスメントは1時間程度で済ませると紹介したように長時間になるのは避けたいです。
23項目すべてを1度で確認するとなると、1時間では収まらない可能性もあります。また、1度に質問攻めにすると利用者や家族が話したいと思っていることを充分に伝えられないと感じてしまうことも少なくないので、アセスメントシートを埋めることばかりを意識するのはやめましょう。
インテーク、アセスメントが終わっても定期的なモニタリングなど今後も継続して関わっていく機会はあるため、時間をかけて項目を埋めればよいです。アセスメントシートを埋めることも必要ですが、それよりも目の前にいる利用者や家族が伝えたいと感じていることがあればその内容に耳を傾けるようにしましょう。
信頼関係を築くことを忘れない
介助サポートは体に触れたり、プライベート空間である自宅に介護職員が訪れたりと密接に利用者と関わります。そのため、信頼できる相手でないと不信感を抱いた状態では適切な介護サービスが提供できないことも。
自分に置き換えればわかると思いますが、信頼できない相手には体に触れてほしくない、近くにいてほしくないと感じるはずです。相手が大切にしていることや価値観などを把握して少しずつ信頼関係を築いていきましょう。
利用者の気持ちに寄り添う
介護サービスを受ける利用者は、自分の大切な将来や時間を介護職員に任せると決めて利用しています。体が不自由になっていく現実を受け止める辛さなどもあり、介護サービスを利用すると決心するまでにはさまざまな葛藤もあったはずです。
そのような利用者の気持ちを理解して、言葉や態度で寄り添うことが重要です。専門的な知識があるとこのようにした方がよいと感じる部分もあるかもしれませんが、そのような考えや行動を強制するのはよくありません。
提供する介護サービスはあくまでも納得してもらう必要があるため、いくらよい介護サポートであっても拒否されては本末転倒です。価値観などの違いなどから理解しづらいと感じる部分があるかもしれませんが、気持ちに寄り添うことは忘れてはいけません。
素直な気持ちを引き出せるような話し方や聞き方を意識する
アセスメントは介護サービスを提供するうえで不可欠なものなので、ここでいかに利用者や家族の想いを汲み取れるかが肝要です。利用者と家族では想いが違う可能性もあります。
それぞれの素直な気持ちが引き出せる話し方や聞き方ができるように工夫するとよいです。話を聞いてほしい人や、質問されたことには答える人など人によって違いがあるためどのような人なのか見極めるのがおすすめです。
わかりやすいように説明をおこなう
介護サービスを初めて利用する人にとっては聞きなれないことや知らないことが多く、すぐに理解するのが難しいものもあります。また、耳が遠いなどで話が聞き取りづらい人などもいます。
そのため、初めての人でもわかりやすいように伝えることが重要です。専門用語ではなくイメージしやすい言葉や例えを使ったり、ゆっくり大きな声で話したりなど伝え方や話し方を工夫するだけでも大きく印象が異なります。
相手の反応を見ながら、理解できているか確認することもおこないましょう。
まとめ
介護をおこなう際にはアセスメントが重要な意味を持ちます。安心して介護サービスを受けてもらうにはケアマネジャーがいかにわかりやすく伝え、信頼関係を築けるかが重要です。
適切で利用者にぴったりの介護サービスを受けてもらうためにも、アセスメントに必要なことを把握しておくこともマストです。また、紹介したポイントを押さえ、利用者や家族に寄り添った対応を実践していきましょう。