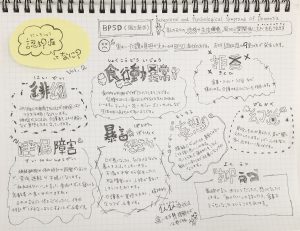高齢者向けのレクリエーション17選|レクリエーションする上での注意点

老人ホームやデイサービスでレク企画をすることになり悩んでいる方に向けて、高齢者向けのレクリエーションを17個厳選しました。
道具なし・座ってできる・テーブルゲーム・ホワイトボード別に紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
高齢者向けのレクリエーションの効果と目的
ここでは、高齢者にとってレクリエーションは楽しむ以外にどのような効果と目的があるのかをご紹介します。
効果や目的を知ることで、企画する際の考え方や選び方が変わるでしょう。
心身の健康
高齢者向けのレクリエーションは、積極的に手足を動かすものが多いです。
そのため、心身の健康を維持する効果があります。
体を動かすとストレスが発散され、気分がリフレッシュされます。
加えて運動は、筋肉量の維持や血行促進など、健康に欠かせない機能向上や効果を得られるため、積極的に実施しましょう。
高齢者同士のコミュニケーション促進
高齢者向けのレクリエーションは、一人で楽しめるものから利用者全員で楽しめるまであります。
複数人で参加するレクリエーションを行えば自然と会話が生まれるため、コミュニケーションを促せるでしょう。
会話には、孤立感を緩和させたりストレス発散したりする効果があるため、気分をリフレッシュさせられます。
認知機能の維持
高齢者向けのレクリエーションには、脳のトレーニングができるものが多いです。
具体的には、記憶力や思考力、想起力などを刺激できるクイズや、連想ゲームなどのレクリエーションがあるため、認知症予防や物忘れ予防に役立ちます。
また、指先を使ったレクリエーションも脳に刺激を与えることが可能です。
健康寿命を延ばして長生きしたいと考える利用者も多いため、そのような方は特に楽しんで参加してくれるでしょう。
高齢者向けのレクリエーションは4種類
高齢者向けのレクリエーションは大きく4種類あります。
レクリエーションを考える際の参考にしてください。
【種類1】頭脳を使うもの
頭脳を使うレクリエーションは、脳の活性化に役立ちます。
内容によって得られる効果が異なりますが、以下のトレーニングが可能です。
- 記憶力のトレーニング
- 思考力のトレーニング
- 集中力を養うトレーニング
- 判断力を養うトレーニング
現在の日本は超高齢化社会に進み、認知症の発症者も増えていくと予測されています。
認知症は本人にとっても、周囲の人にとってもつらい病気です。
そのため、認知症予防のレクリエーションは積極的に参加してくれやすいでしょう。
【種類2】手先を使うもの
手先を使うレクリエーションは、行動につなげる脳の機能を活性化させるのに役立ちます。
手先を使うものは、以下のようなトレーニングができます。
- 指先の器用さを維持するトレーニング
- 集中力を養うトレーニング
- 想像力を養うトレーニング
- 運動機能に関わる脳機能のトレーニング
調理や編み物など、形になって完成するものは、達成感も得られ楽しんでもらいやすいでしょう。
【種類3】視覚・聴覚を使うもの
視覚や聴覚を使うレクリエーションは、脳機能の活性化とリフレッシュ効果があります。
実施する内容にもよりますが、以下のようなトレーニングができます。
- 想起力のトレーニング
- 心肺機能のトレーニング
音楽鑑賞やカラオケなどは想起力が働くため、脳の活性化が期待できます。
また、カラオケは呼吸をして声を出す動きがあるため、心肺機能を鍛えることが可能です。
さらに、音楽や映画鑑賞はリラックス効果もあり、リフレッシュできたり情緒が安定したりします。
【種類4】体を使うもの
体を使うレクリエーションは、身体機能の向上や維持、リフレッシュ、運動不足による病気の予防などに役立ちます。
実施内容によって異なりますが、以下のようなトレーニングができます。
- 筋肉のトレーニング
- 心肺機能のトレーニング
- 柔軟性を養うトレーニング
- 協調性を養うトレーニング
軽い運動を交えているため、運動不足による病気の予防やリフレッシュ効果も期待できます。
高齢者に合ったレクリエーションを考える5つのコツ
どのようなものであれば高齢者の方でも楽しんでもらえるのでしょうか。
レクリエーションを考える際のコツは以下の5つです。
安全性の高さを考える
高齢者の方でも安心して楽しめるものを企画することが大切です。
そのためには、安全に実施できるかを考えましょう。
大きな危険が伴うようなレクリエーションはないでしょう。
しかし、実施する場所に物が多く置いてあったり、ぶつかってケガをするような物があったりすると危険です。
安全にレクリエーションを開催できるよう、実施環境の安全確保や配慮も大切です。
身体・認知機能に合うか考える
個々によって身体機能が異なるため、その方に合わないものに参加させるとケガのリスクが高まります。
そのため、体力や体を動かせる範囲などを考えて、レクリエーションの内容を選びましょう。
複数を一度に企画して、参加できるものを利用者本人で選べるようにするのもおすすめです。
チーム戦を行う場合は、バランスがよいようにチーム分けしましょう。
また、様子をうかがって交代を促すなど、臨機応変に対応することも大切です。
コミュニケーションを促進できるか考える
高齢者の方の中にはコミュニケーションをとるのが苦手な方がいるかもしれません。
しかし、コミュニケーション不足になると、性格が内向的になりやすかったり、メンタルが落ちやすくなったりします。
そのようなことにならないよう、レクリエーションでコミュニケーションを促進させることが大切です。
孤立させないために、グループ・チームで行うものを積極的に企画するとよいでしょう。
興味を引き出せるようテーマや季節感を考える
利用者の方に楽しんでもらうためにも、興味を引き出せるようなテーマを考えましょう。
人によっては、性格的なものでレクリエーションに興味がない方、消極的な方もいます。
無理強いをするのはよくありませんが、自然と「参加したい」という気持ちが湧くように考えることが大切です。
例えば、夏は七夕の短冊作り、冬はクリスマスリースを作るなど、季節を感じるテーマも企画するとよいでしょう。
分かりやすいルールかを考える
参加しやすいと感じてもらうレクリエーションの特徴は、以下の3要素がそろっているものです。
- 単純なルール・遊び方
- 気分がすっきりする
- 偶然性のある遊び
自分でレクリエーションを考える場合は、高齢者の方もすぐに理解できる分かりやすいルールや、答えが分かってすっきりするようなゲームを心がけましょう。
老人ホームでのレクは実施内容・レベルに注意!
老人ホームでのレクは実施内容・レベルに注意しなければなりません。
施設別に詳しく解説します。
要介護度が低い老人ホームの場合
要介護度が低い老人ホームでレクリエーションを実施する際は、できる内容の範囲が広がります。
いつまでも若い自分を保ちたい、元気でいたいといった思いを持つ方が多い傾向があるため、運動系や頭脳を使う系に積極的に参加してもらいやすいです。
ヨガや散歩、将棋や囲碁などを企画すると楽しんでもらえるでしょう。
要介護度が重い方が多い老人ホームの場合
要介護度が重い方が多い老人ホームでレクリエーションを実施する際は、運動量や強度に気を付けましょう。
麻痺があり体を自由に動かせない方、寝たきりの方なども楽しめるレクリエーションを考える必要があります。
視覚や聴覚を使うもの、頭脳を使うものであれば、楽しんでもらえるでしょう。
リーズナブルな有料老人ホームの場合
リーズナブルな有料老人ホームは予算が限られているため、その中で楽しめるようさまざまな工夫が施されているのが特徴です。
ボランティアの方や幼稚園生、小学校生が遊びに来ることも多々あるため、子どもたちと一緒に楽しめるレクリエーションを考えるのもおすすめです。
高級有料老人ホームの場合
高級な有料老人ホームは、仕事で高い位に就いていた方や富裕層の方が住んでいるため、こだわりが強い方が多いです。
自分たちで考えるよりも、専門の方を呼んでレクリエーションを行う傾向があります。
道具なしでも盛り上がるレクリエーション5選!
利用者に道具を作ってもらったり、使用してもらったりすることなく、道具を使わずに気軽に遊べるものを5つご紹介します。
しりとり連想ゲーム
このゲームは、しりとりをしながら回答した言葉で連想したものを説明するレクリエーションです。
6~8人くらいでグループを作って円になって行います。
進行係は、利用者が回答した後に「どんな色だった?」「どんな香りがする?」「どんな味?」など、その回答にまつわる質問をして、連想させます。
都道府県クイズ
このゲームは、進行係が都道府県に関するヒントを出し、それをヒントに利用者にどの都道府県なのかを当ててもらうレクリエーションです。
利用者全員で参加してもよいですし、人数が多ければ10人くらいのグループを作ってもよいでしょう。
ヒントにする内容は、特産品や芸能人や有名人の出身地、観光名所など分かりやすいものがおすすめです。
イントロクイズ
このゲームは、曲を数秒流し、曲名を当ててもらうレクリエーションです。
利用者全員で参加するのもよいですし、人数が多い場合は6人くらいのグループを作って行うのもよいでしょう。
流す曲を決める際は、利用者が知っている懐かしい曲を採用してください。
最近の曲だと分からないことが多く、また懐かしい曲のほうが思い出す力を鍛えられるためおすすめです。
じゃんけん列車
このゲームは、じゃんけんをして勝った人が先頭につき、負けた人が後ろにつき、列車のように連なるレクリエーションです。
利用者全員が参加できます。
集まった方々で円になり、進行係の合図に合わせて隣の人とじゃんけんをします。
最終的に長い列を作った利用者がチャンピオンです。
数字の足し算ゲーム
このゲームは、最終的に20になるよう、数字を言い合うレクリエーションです。
2人以上のグループを作り、向かい合わせもしくは円になって行います。
言える数字は1~3と決まっており、20を超えてしまう数字を言った方は負けです。
合計数字を進行係が伝えてもよいですし、次の方に利用者がバトンタッチする際に言ってもらうルールにしてもよいでしょう。
座ってできるレクリエーション4選!
利用者が椅子や車椅子に座った状態のまま遊べるレクリエーションを4選ご紹介します。
うちわと風船のバレー
この企画は、風船を膨らませてボールにし、利用者の方にうちわであおいでもらい、落とさないようにするレクリエーションです。
机と椅子を準備し、2~4人のグループになって向かい合わせに座り、机の真ん中にテープやティッシュ箱などでしきりを作ります。
最終的にラリーが長く続いたグループが勝ちです。
スタッフは、進行役と落とした風船を拾う補助係の2人が必要です。
輪投げ
この企画は、ペットボトルや洗濯バサミなどを的にし、そこに向かって輪を投げるレクリエーションです。
ペットボトルで行う場合はマジックで点数を書いておくと、ゲーム性が高まります。
洗濯バサミの場合は色ごとにポイントを設定しておくとよいでしょう。
ペットボトルのボーリング
この企画は、ペットボトルをボーリングのピンに見立てて、ボールを転がして倒すレクリエーションです。
150mlのペットボトルに5cmくらい水を入れ、三角になるように並べていきます。
直線上に椅子を準備して座ってもらい、ボールを転がしてもらい、本数を多く倒した方が勝ちです。
ペットボトルにポイント数を書いたポイント制もよいでしょう。
テーブルゲームのレクリエーション4選!
ここでは、高齢者が懐かしいと思うものも含めた、テーブルゲームのレクリエーションを4選ご紹介します。
花札
このゲームは昔からあるため、知っている利用者が多い傾向です。
遊び方は通常の花札と変わりません。
実施する際は、長机を1つ用意し、座れる人数だけの椅子を置いて座ってもらいます。
ルール表を用意したり、得点計算は電卓を使うかスタッフが計算したりするとよいでしょう。
ピンポン玉入れゲーム
このゲームは、机に紙コップを起き、それに向かって利用者にピンポン玉を投げ入れてもらうレクリエーションです。
紙コップに得点を書いて、ポイントの合計点が高い方が勝ちです。
カラーコップを使い、カラーごとに点数を設定する方法もあります。
個人戦にしてもグループ戦にしても盛り上がります。
カードビンゴ
このゲームは、トランプと数字が書いてある紙を使って行うビンゴです。
用意した長机に座ってもらい、1~13までの数字が書いてある紙とペンを渡します。
進行係が出したトランプの数字に合わせて数字をマジックで消してもらいます。
ビンゴを達成した方が勝ちです。
健康すごろく
このゲームは、すごろくマップを作り、サイコロの数に合わせて止まったマスにある軽い運動を、利用者にしてもらうレクリエーションです。
参加人数が多すぎると回す速度が遅くなるため、時間内でゴールできるよう2~5人くらいがよいでしょう。
マスに設定する運動は、利用者の方の状況を見て選びます。
例えば、足踏み3回、手をたたくのを5回などでかまいません。
かるた
このゲームは、机に札を並べ、読んだ上の句に合った下の句を選んでもらうレクリエーションです。
遠くて手を伸ばせないとなると立ち上がる必要があるため、小さめの机を用意しましょう。
それを囲むように椅子を並べて座ってもらいます。人数は2~4人だと遊びやすいでしょう。
百人一首や料理いろはかるた、日本史かるた、落語かるた、ことわざかるたなど、さまざまなものが販売されています。
ホワイトボードを使ったレクリエーション4選!
ここでは、脳のトレーニングができたり偶然性の笑いが起きたりする、ホワイトボードを使ったレクリエーション4選をご紹介します。
漢字の分解クイズ
このクイズは、一文字の漢字を部首ごとに分解し、どの漢字かを当ててもらうものです。
例えば、答えの「晶」を「日」「日」「日」に分解し、その漢字を当ててもらいます。
一度に書いたものを見て回答してもらう方式、制限時間を設けて順番に一つずつ書いて回答してもらう方式のどちらでもよいです。
どちらの方法でも回答の制限時間を設け、分かった方は答えを聞くスタッフもしくは出題者に耳打ちをして伝えます。
何人正解者が出てもかまいません。
言葉探し
このクイズは、ホワイトボードにバラバラに書いてある「ひらがな」もしくは「カタカナ」から、利用者に言葉を探してもらうものです。
制限時間を設け、単語を作れた数を競います。
挙手制で回答してもらうか、机を用意して紙とペンを渡し、時間が来たら作れた単語を発表する方法もあります。
個人戦、チーム戦どちらも盛り上がりやすいです。
連想ゲーム
このゲームは、出題者がまずホワイトボードに単語を入れ、利用者がそれに続いて連想する言葉を書いていくものです。
立ち歩くことが難しい場合は、その場で利用者が回答した単語をスタッフが書いていく形にしましょう。
連想ゲームを進めていくのも楽しいですが、会話がないこともあります。
そのような場合は、回答した単語に関する質問をして会話を作りましょう。
例えば「犬」と答えが来たら「どんな犬が好きですか?」といった簡単な質問をします。
福笑い
この企画は、ホワイトボードに貼ってある顔に、磁石の付いた目や鼻、口、眉毛、耳のパーツを、目隠しして貼り付けるものです。
一般的には、介護職員が目隠しをして、利用者のヒントをもとに貼り付けていきます。
できそうであれば、利用者の方にしてもらうのもよいでしょう。
ただし、転倒リスクもあるため、安全に配慮して行ってください。
高齢者向けのレクリエーションを行う上での注意点
施設やデイサービスなどでレクリエーションを行う際の注意点を3つお伝えします。
利用者の方に楽しんでもらうためにも大切なことですので、目を通しましょう。
参加は自由にする
利用者の方にはなるべくレクリエーションに参加してもらいたいところですが、無理に誘ったり強制参加にしたりするのはよくないです。
参加したくない理由には、身体的な不安があったり、人見知りだったりと、さまざまな理由が考えられます。
「参加させる」ではなく、「参加したいと思ってもらう」ことに焦点を当てて、レク内容を考えましょう。
高齢者への気遣い
楽しんでもらうために、親近感のある接し方で行うのはよいことです。
ただし、最低限のマナーや言葉遣い、かける言葉に気を遣いましょう。
中には、提案したレクリエーションができないことに恥ずかしさを感じる方もいるため、自尊心を守るような言葉かけを意識するのがポイントです。
実施時間を考慮
高齢者の方は若いときよりも体力や筋力が減っており、疲れやすくなっています。
疲労を感じたまま長時間のレクリエーションを行うのは、ストレスや病気の悪化、ケガの原因となり危険です。
短時間で終わるように時間を考え、また、適宜タイミングを見て体調や疲労を聞いて、休めるようにしましょう。
まとめ
利用者の方に楽しんでもらうレクリエーションは、競うものや頭を使うもの、五感を使うものなど多岐にわたっています。
気分がスッキリするものや、懐かしさを感じられるものは喜んでくれる傾向がありますので、実施してみるとよいでしょう。
また、少人数から大人数に対応しているものや、準備物がなくてもできるレクリエーションもありますので、上記に応じて企画してみてはいかがでしょうか。