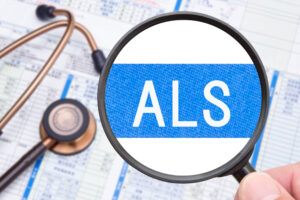介護業界が人手不足といわれる10の理由|引き起こす問題や対策を紹介

「介護業界は人手不足」とよく耳にしますが、なぜこれほどまでに深刻なのでしょうか。
介護職の離職率が高い理由、求職者が少ない背景を知ることで、業界の課題が見えてきます。
本記事では、介護業界が人手不足といわれる9の理由を詳しく解説し、その影響や解決策を紹介していきます。
介護の現状を理解して今後の対策を知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
介護業界はどれくらい人材が不足している?
介護業界は人手不足とよく耳にしますが、実際にどれくらいの人材が不足しているのでしょうか。
人手不足といわれる理由を紹介する前に、実態から詳しく紹介していきます。
実際の人材不足数
厚生労働省の「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」によると、2026年度には約240万人、2040年には約272万人の介護職員が必要だと公表されました。
しかし、2023年時点で働く介護職員は約212万人のため、2026年には約28万人不足することが分かります。
高齢者の人口推移も2040年ごろまで増加する一方といわれており、この先数十年以上介護職員が不足すると予想されています。
参照:厚生労働省「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」
参照:厚生労働省「介護職員数の推移の更新(令和5年分)について」
特に都心部では深刻な人手不足が起こっている
東京で2026年に必要な介護人材数は212,525人とされていますが、現状推移を見込んだ介護職員数は184,367人と出ており、28,158人不足しています。
2040年になると、必要介護人材数258,191人に対し、現状推移を見込んだ介護職員数は184,718人と、その差は73,473人に広がっています。
一方で郊外の状況を確認すると、介護人材必要数は増加しているものの、その差は都心部と比べても少ないのが特徴です。
栃木県を例に挙げると、2026年に必要な介護人材数は35,271人に対し、現状推移を見込んだ介護職員数は27,196人と、その差は8,075人です。
2040年では必要人材数が39,664人に対し、現状推移を見込んだ介護職員数は24,964人と、その差は14,700人となっています。
人手不足であることは共通しているものの、都心部のほうがより深刻な状況に陥っていることが分かります。
参照:「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数(都道府県別)」
介護業界が人手不足といわれる9の理由
介護業界では慢性的な人手不足に直面しており、その背景にはさまざまな要因が関係しています。
ここからは、介護業界が人手不足といわれる9の理由について紹介していきます。
高齢化が進むから
内閣府が2024年に発表した「高齢社会白書」によると、2023年10月現在の国の総人口1億2,435万人に対して、65歳以上の人口は3,623万人と、その割合は29.1%にまで達しました。
そして、国全体の高齢化率はまだまだ伸びるといわれており、2040年には34.8%にまで達するといわれています。
2023年の65歳以上の割合と2040年の割合を比べてみると、約5%増加すると予想されていますが、これは3人に1人が65歳以上の高齢者になるということです。
この数値からも分かるように、日本国内の高齢化は歯止めが効かないほど増加傾向にあり、その分高齢者を支える人材も必要になります。
参照:内閣府「高齢社会白書」
少子化が進むから
日本国内では高齢化率が増加傾向にありますが、反対に若い世代の人口割合は年々減少しています。
内閣府が2024年に発表した「高齢社会白書」によると、2023年の15歳~64歳の人口は7,395万人ですが、2040年になると6,213万人まで減少すると推測されています。
つまり約1,182万人減少すると予想されており、若い世代が高齢者を支える負担はこれからも増えるでしょう。
参照:内閣府「高齢社会白書」
要介護認定者が増加しているから
高齢者の増加に伴い、要介護認定者も増加傾向にあります。
厚生労働省が発表した「介護保険を取り巻く状況」の要介護度別認定者数の推移によると、2015年度末が620万人に対し、2020年度では682万人と増加傾向です。
介護度の高い方が増える分、介助する方の人数も必要になるため、より人手が不足することが予想されます。
参照:厚生労働省「介護保険を取り巻く状況」
競争率が高く採用が難しいから
厚生労働省の「有効求人倍率(介護関係職種)の推移」によると、2021年の介護関係職種の有効求人倍率は3.65倍であり、全職種の1.03倍と比較すると求人倍率が高いことが分かります。
これは、求職者1人に対して3~4件の求人があることを意味しており、介護業界全体で人手不足が深刻であることを示しています。
多くの事業所が人材を必要としている一方で、限られた人材を取り合う状態が続いているため、求人を出しても応募が来ない、面接に進んでも内定を辞退されるといったケースが後を絶ちません。
特に経験者や資格保有者の採用は難易度が高く、より競争が激化しています。
参照:厚生労働省「有効求人倍率(介護関係職種)の推移」
介護へのマイナスイメージが強いから
介護業界未経験者や、他業種からの転職を考えている方の介護へのイメージは、まだまだマイナスなイメージが強い傾向です。
代表的なイメージとしては「体力的にきつい」「給与が低い」「汚い仕事が多い」といったネガティブな声が挙げられます。
さらに、夜勤やシフト勤務による不規則な生活や、精神的な負担が大きいと感じる人も多いのが現状です。
このようなイメージが定着してしまっていることで、応募の段階で敬遠されるケースが目立ちます。
施設によっては働き方を工夫していたり、支援制度が整っていたりする場合もありますが、その実態が広く知られていないのが課題です。
介護職の離職率が高いから
介護職の離職率は減少傾向ではありますが、ほかの業種と比べるとまだまだ低いとはいえません。
公益財団法人介護労働安定センターの「令和5年度介護労働実態調査結果の概要について」によると、2019年の介護職の採用率が18.2%、離職率が15.4%でした。
一方で2023年の採用率は16.9%に対し離職率が13.1%という結果となっており、介護職の離職率は減少していることが分かります。
また、厚生労働省が発表した「令和5年雇用動向調査結果の概況」の主要産業の入職率と離職の推移によると、令和5年の入職率が16.4%に対し離職率が15.4%となっています。
介護職と全体の離職率を比較すると大きく変わらず、むしろ介護職のほうがやや離職率が低いのです。
定着率は上がっているものの、依然として人手不足と感じる事業所も少なくありません。
参照:公益財団法人介護労働安定センター「令和5年度介護労働実態調査結果の概要について」
参照:厚生労働省「令和5年雇用動向調査結果の概況」
仕事内容に対して給与が低いから
介護の仕事は、高齢者や障がいを持つ方の生活を支えるというやりがいのある仕事ですが、日々忙しかったり、身体的・精神的に負担がかかったりするのが現状です。
例えば、利用者の入浴や排せつの介助では腰に大きな負担がかかり、腰痛に悩むスタッフも少なくありません。
また、夜勤がある職場では、生活リズムの乱れから疲労を感じやすくなることもあります。
しかし、厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査」によると、介護職員(医療・福祉施設等)の月給は約271,000円という結果が出ており、全体の約330,400円と比較して決して高いとはいえません。
参照:厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」
業務がきついから
業務がきついことも介護業界の人材不足の要因となっています。
実際に行われた公益財団法人介護労働安定センターの「令和5年度介護労働実態調査結果の概要について」によると、労働条件・仕事の負担に係る悩み・不安・不満等について「身体的負担が大きい」と回答した方の割合が29.3%、「精神的にきつい」は22.5%と発表されました。
また、「人手が足りていない」と感じる方は、全体の約50%いることが分かっています。
人手が足りていないという現状も、精神的・身体的にきついと感じさせる要因になっているのでしょう。
参照:公益財団法人介護労働安定センター「令和5年度介護労働実態調査結果の概要について」
評価制度が整っていないから
介護の仕事は、社会的に大切な仕事であるにもかかわらず、その評価は低いのが現状です。
公益財団法人介護労働安定センターの「令和5年度介護労働実態調査結果の概要について」を見てみると、労働条件・仕事の負担に係る悩み・不安・不満等について「業務について社会的評価が低い」と答えた方が、全体の20.4%いることが判明しています。
また、職場内での仕事ぶりや能力などの評価制度も整っておらず、正しく評価されない不満もあるようです。
参照:公益財団法人介護労働安定センター「令和5年度介護労働実態調査結果の概要について」
介護業界の人手不足が引き起こす問題
冒頭で介護業界の人手不足は、今後ますます深刻化すると紹介しましたが、それによりさまざまな問題が起こる可能性があります。
ここでは、介護業界の人手不足により引き起こされる問題について紹介していきます。
施設の入居(利用)待ちが増加する
人手不足によって事業所に適切な人数を確保できなければ、入居待ちの方が増加する可能性があります。
必要な介護サービスを受けられず、自宅での生活が困難になる高齢者が増えるリスクも考えられます。
また、家族の負担も大きくなり、介護疲れという社会問題に発展する可能性もあるでしょう。
介護事業所の倒産が起こる
人材を確保できない状況が続くと、業務がまわらず経営に深刻な影響を与え、最悪の場合は介護事業所の倒産につながります。
特に小規模な施設や地方の事業所は人材確保が難しく、倒産リスクがさらに高まるでしょう。
倒産が相次いだ場合は介護サービスが縮小し、利用者やその家族が必要な支援を受けられなくなるかもしれません。
労働環境が過酷になる
人手不足が深刻になると、限られた職員に多くの業務が集中し、労働環境はさらに過酷になります。
例えば休憩時間を確保できなかったり、残業や夜勤の回数が増えたりと、心身への負担が大きくなることもあるでしょう。
このような状態が続くと、スタッフのモチベーション低下やケアの質の低下を招くなど、利用者への影響も避けられません。
さらには職員同士の人間関係にも悪影響を及ぼし、施設全体の雰囲気が悪化することもあります。
離職が加速する
劣悪な労働環境や低賃金が続くと、離職を選択する職員も増えるでしょう。
特に経験の浅い若手職員や生活に余裕がない人ほど、他業種への転職を考える傾向があり、結果として残されたスタッフの負担はさらに増します。
介護の質が低下するリスクがある
人手不足が深刻化すると、一人のスタッフが担当する業務量が増加し、十分なケアを提供することが難しくなります。
結果として、介護が必要な方へのサービス提供はもちろん、食事や入浴の介助が不十分になったり、利用者とじっくり向き合う時間が減少したりする可能性があります。
また、経験の浅い職員への教育が行き届かず、スキルの低下を招くことにもなりかねません。
こうした状況が続けばサービスの質が低下し、利用者の満足度や安全性に影響を与えるでしょう。
家族介護の負担が増加する
施設や訪問介護のサービスが十分に提供されないと、本来プロの手に委ねるべき介護を家族が担うケースが増えます。
特に、共働き世帯や高齢者のみの世帯では介護負担が重くのしかかり、仕事と介護の両立が難しくなることもあります。
介護疲れが原因で心身の健康を損なう人や、離職に追い込まれる人も少なくありません。
介護事故やトラブルの増加
職員の負担が増えることで業務の効率が低下し、事故やトラブルが発生するリスクが高まります。
例えば、転倒や誤嚥といった利用者の事故が増えたり、服薬ミスなどのヒューマンエラーが発生しやすくなったりします。
また、職員の疲労やストレスが蓄積されることで、利用者・家族とのコミュニケーション不足や、クレームが増えるおそれもあるでしょう。
介護の人手不足を改善するための対策
介護業界の人手不足を解消するためには、労働環境の改善や人材の確保が不可欠です。
ここでは人手不足を改善するための対策を9つ紹介していきます。
働きやすい環境を整える
人手不足の改善や離職率を低くするには介護の現場をよくする必要があり、人間関係はもちろん働きやすい環境を整えることが大切です。
具体的には業務を効率化できるITの導入や、規模を縮小したユニットケアが勧められています。
業務を効率化できるITでは、勤怠管理やシフト管理、介護記録などをアプリやタブレットで行うことで、業務の効率化が可能です。
ユニットケアは規模を縮小することで、利用者一人ひとりに充てるケアの向上や、風通しをよくして人間関係の改善を図る目的があります。
人間関係をサポートするための相談窓口の設置
介護職を離職された方に多い理由に、「人間関係がよくなかった」という結果が出ています。
現場では利用者や家族との関係だけでなく、職員同士の連携も重要であり、その中でストレスや摩擦が生じることは少なくありません。
そのため、悩みを気軽に相談できる窓口を設けることで、職員の不安や不満を早期に解消することが可能になります。
第三者が関与する外部の相談機関や、施設内の信頼できる相談員を配置するのも有効です。
介護職員の処遇改善
厚生労働省は、今後の介護業界の人手不足を懸念し、介護職員の処遇改善加算の見直しを決めています。
具体的には、介護職員処遇改善加算、特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算の3つの加算を「介護職員等処遇改善加算」に一本化し、加算率を引き上げると発表しています。
3つの加算を合計して2%以上のベースアップを目指しており、これにより給与アップが期待できるでしょう。
「待ち」から「探しに行く」の採用へとシフト
就職や転職エージェントや人材派遣サービスといった、登録するだけで求職者を探してくれるサービスもありますが、そのような「待ち」の採用では人材が集まらないことも非常に多いです。
また、登録するにはコストがかかる場合もあり、事業所にとっては結果的に損するケースもあるため、最近ではSNSなどのWeb媒体を活用して積極的に「探しに行く」採用も増えてきています。
特に若い人材は、SNSに使い慣れている世代であるため、積極的に使用するのがよいでしょう。
介護へのイメージ改善
介護業界は「きつい」「汚い」「給料が低い」のイメージを持つ方が、まだまだいるのが現状です。
介護職へのイメージを改善することは、人手不足を解消するための必須項目といえるでしょう。
求人でできる限りプラスのイメージを載せることも大切ですが、SNSを活用し「面白そう!」「自分もやってみたい!」と思われるような発信を積極的に行うことも効果的です。
資格取得をサポートし、スキルアップの促進
介護に関する資格は豊富に存在するため、資格によっては資格手当や業務手当などの待遇がアップする場合もあります。
特に介護福祉士やケアマネージャーといった資格を、資格手当や役職手当の対象にすれば、職員のモチベーションも向上するでしょう。
資格を取得した職員は、職場内でリーダー的存在として活躍できるようになり、全体の業務効率化やサービスの質向上にも貢献します。
スキルアップを促す環境を整えることで、離職防止や長期的な人材確保にもなるでしょう。
人材派遣業者とのつながりを確保
人材派遣業者は、すぐに人手が欲しいときや、次の方が就職するまでの穴埋めとして人材を紹介してくれるサービスです。
このように急な人手が必要になるときのために、人材派遣業者とのつながりを確保するのもおすすめです。
どのような方が欲しいかを日々のやり取りで伝えておくと、求めていた人材を紹介してもらいやすくなるでしょう。
介護に特化したサイトの導入
求人サイトには介護に特化したサイトも存在しており、一般的なサイトよりも求人が埋もれにくく、介護用の細かい検索も可能です。
また、求職者向けに介護職の魅力や具体的な仕事内容を発信しているサイトもあり、ミスマッチを減らす効果が期待できます。
ただし、サイトによって登録時に費用がかかる場合もあるため、コストをかけたくない場合は、成果報酬型の求人サイトを利用するのがよいでしょう。
外国人を積極的に雇用する
最近では、外国人を積極的に雇用することも、人手不足を解消する対策として取り入れられています。
実際に日本国内では外国人介護人材の受け入れを進めており、今後増加するのではないかといわれています。
しかし、現状では「介護の仕事を業務とする外国籍労働者を受け入れていない」と答える事業所が82.5%だったという結果もあり、まだまだ外国人が介護業界で働くイメージができていない事業所も多いようです。
参照:公益財団法人介護労働安定センター「令和5年度介護労働実態調査結果の概要について」
【外国人を雇用するメリット】
しかし、介護業界で外国人を雇用するメリットがないわけではありません。
具体的には、以下の3つのメリットが挙げられます。
- 若い人材を確保できる
- 郊外でも採用しやすい
- 採用すると助成金を受け取れる場合がある
外国の方は「日本で働いてみたい」「生活してみたい」と思う方が多い傾向があり、「働けるならどこでもよい」と思っている方も多く、郊外でも採用しやすいのが特徴です。
場合によっては採用できると助成金を受け取れるケースもあるため、積極的に活用することをおすすめします。
【外国人を雇用する方法】
外国人を雇用するためには、就労ビザや身分系などの在留資格が必要です。
就労ビザにもいくつか種類がありますが、介護業界で働くための在留資格は以下の4つがあります。
- 在留資格「介護」
- EPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士
- 技能実習
- 特定技能
それぞれ、取得するための条件などが異なるため、しっかり調べてから雇用しましょう。
介護の人手不足を解消できた成功事例
介護業界が人手不足になる理由と対策について紹介してきましたが、実際に介護業界の人手不足に対して取り組みを行い、改善に成功した事例があります。
ここからは、具体的な成功事例を6つ紹介していきます。
外国人の受け入れ
1つ前の章で紹介しましたが、実際に外国人を受け入れて人手不足を解消できた例はいくつかあります。
当初は受け入れることに不安や抵抗はあったものの、実際に働く姿を見てみると想像以上に働いてくれたようです。
また、利用者からの評判もよく、現場職員の刺激にもなるので、採用してよかったとの声もあります。
見守りシステムの導入
見守りシステムは、利用者の居室の状況をモニターで確認できるシステムです。
居室の多い入所施設では、夜間の見回りの際に客室を一つひとつ確認する必要があり、非常に手間です。
しかし、見守りシステムを導入すればモニターを見れば状況が分かるので、夜間徘徊がある方でも安心できます。
また、見守りシステムは一人暮らしの高齢者用もあり、いつも使用している電気に設置すれば、電気の点灯や消灯により生存を感知できるので、家族や介護事業者が遠隔で安否を確認することも可能です。
このような見守りシステムを導入した事業所では、業務効率につながり仕事が少し楽になったとの声もあります。
働きやすい職場や制度の整備
介護業界では、妊娠や子どもがいるといった状況から、職場に迷惑をかけないように辞める方もいます。
そういった方のために、つわり休暇や生理休暇、子どもが病気になった場合の制度などを設けている事業所も存在します。
また、男性が育休を取れるように検討したり、取得しなければ評価を下げるといった仕組みを検討したりしている事業所もあるようです。
資格の取得支援
介護の資格は豊富にあり、資格によってはキャリアアップやスキルアップが可能ですが、資格取得はほとんどが本人任せとなっているのが現状です。
しかし、事業所の中には講師出張型の研修や助成金などを活用し、資格の取得支援を行っているところもあります。
出張型であれば、職員がわざわざ研修先に出向かなくても資格取得ができるので、スキルアップがしやすくなります。
積極採用へのシフト
ハローワークや転職エージェントに登録し、求人を待っている事業所はまだまだ多く、待ちの採用ではよい結果にならないケースばかりです。
しかし、介護の魅力の発信や定期的な施設見学、オンライン面接などを取り入れることで、採用できたケースもあります。
手間がかかる場合もありますが、続けることでよい結果となるでしょう。
離職を防ぐ取り組み
離職を防ぐためには、現場の職員と管理職が積極的にコミュニケーションを取ることが大切です。
職場の人間関係が良好であれば、ストレスや不満がたまりにくく、働きやすい環境が整います。
具体的には、人間関係や業務の悩みを相談できる窓口を設置したり、定期的な面談を実施したりと、職員の声をしっかりと拾い上げることが重要です。
中には、コミュニケーション向上のためにグループワークを採用した事業所もあり、取り入れることで現場のやり取りがスムーズになったとの声も挙がっています。
まとめ
本記事では介護業界が人手不足といわれる9の理由を紹介し、引き起こす問題や対策を解説しました。
人手不足は介護業界全体の大きな課題ですが、適切な対策を講じることで改善できる可能性があります。
具体的には見守りシステムの導入や働きやすい環境づくり、人材確保の工夫など、さまざまな取り組みが求められます。
また、離職防止策や介護の魅力を発信して、長く働ける職場づくりも重要です。
今後も業界全体で課題解決に取り組み、よりよい職場環境を目指していくことが必要となるでしょう。