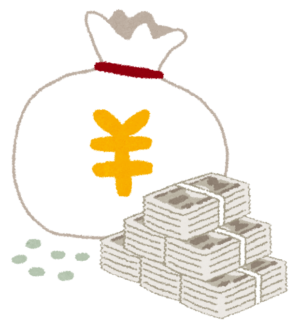とろみ剤にはどのようなデメリットがある?危険や事故を回避するための注意点について解説

嚥下機能が低下した高齢者の飲み物に、誤嚥や窒息を防ぐ目的で使用されるのがとろみ剤です。
とろみ剤にはさまざまなメリットがありますが、使用するデメリットや危険性はないのでしょうか。
本記事では、高齢者の食事にとろみ剤を使用するメリットとデメリットについて、分かりやすく解説していきます。
とろみ剤を安全に使用するための注意点や、使用時のポイントについても解説しているので、とろみ剤の使用を検討している方はぜひ参考にしてください。
とろみ剤の特徴・メリット
とろみ剤には、どのような効果が期待できるのでしょうか。
まずは、とろみ剤の特徴やメリットについて解説していきます。
誤嚥のリスクが軽減できる
とろみ剤を利用して水分に粘度を加えれば、高齢者の誤嚥リスクを最小限にできます。
水分は流動性があるため、食道ではなく気管に入ってしまう誤嚥のリスクが高いです。
加齢によって飲み込む力が低下すると誤嚥が起こりやすくなるため、リスクがある場合にはとろみが必要といえるでしょう。
また、水分にとろみをつけることで誤飲が起こりにくくなり、唾液や飲料に含まれる細菌が気管から肺に侵入して起こる、誤嚥性肺炎の予防もできます。
介護以外の場面でも使用されている
とろみ剤が活用されているのは医療や介護の現場だけではなく、離乳食や幼児食にも使用されています。
さらに、麻婆豆腐やシチュー、あんかけなどの温かい料理にも利用されます。
とろみ剤は食材本来の味を損なうことがないので、栄養補助食品や栄養補助ゼリーなどの市販の商品にも幅広く使用されています。
減塩の効果が期待できる
水分にとろみをつけると、舌の上を通過する時間が長くなるため、通常よりも味を濃く感じるようになります。
そのため、とろみ剤を利用すれば、塩分が少なくても料理をおいしく感じやすいのがメリットです。
嚥下障害で気管や咽頭に炎症がある方に塩分の多いスープや味噌汁は向きませんが、とろみ剤を活用すれば、誤嚥の予防だけでなく減塩の効果も期待できます。
とろみ剤の危険性・デメリット
とろみ剤に直接的な害はありませんが、使用方法によっては副作用が出ることもあります。
とろみ剤の危険性や、使用する場合に起こり得るデメリットをチェックしていきましょう。
消化不良や便秘になる
とろみ剤は消化器系にさまざまな影響を与えることもあります。
適切に使用すれば消化を助ける作用がありますが、過剰に摂取すると消化不良や便秘を引き起こす可能性があるため、注意しなければいけません。
高齢者は加齢による消化機能の低下や運動不足が影響し、便秘のリスクが高まります。
そのため、とろみ剤を使用する際は食べる方の体調や食事内容を考慮し、適切な量に調整することが大切です。
嚥下障害がある方にとって、とろみ剤は安全に食事をとるためのサポートとなるため、体調に合わせて使用して、消化器系への負担を軽減する工夫をしましょう。
アレルギー反応を引き起こす
とろみ剤の成分に危険性はありませんが、人によっては含まれている天然成分にアレルギー反応が出る可能性があります。
アレルギーを持っている方の料理にとろみ剤を入れる場合は、事前に原材料を確認することが大切です。
特にとろみ剤を初めて使用する方へは、少量から試すようにしましょう。
水分の摂取量が減り脱水になる
とろみをつけた飲料は味や口当たりが変化するため「飲みにくい」と感じ、摂取を拒否する方もいます。
その結果、水分摂取量が減少して脱水症状を引き起こす可能性があります。
高齢者は喉の渇きを感じにくくなるため水分補給が不足する傾向があり、脱水が進行すると倦怠感やめまい、意識障害などの症状が現れて、重度になると入院治療が必要です。
水分不足を防ぐためには、とろみの濃度を調整して飲みやすくしたり、ゼリー状の水分補給食品を活用したりするといった工夫が求められます。
必要に応じて医師や専門職と相談しながら、とろみ剤の使用方法や適切な水分補給の方法を検討しましょう。
誤嚥や窒息のリスクがある
とろみをつけすぎてしまうと粘度が高くなるので、咽頭残留が発生しやすくなります。
咽頭残留とは飲み込んだ水分や食塊が、咽頭の部分に残ってしまうことです。
粘着性の高いとろみが咽頭部分に残ってしまうと、窒息や誤嚥を引き起こす危険性があるため、過剰なとろみづけや不要なとろみ剤の使用は避けるようにしましょう。
健康に害を及ぼす可能性がある
とろみ剤には人工的な化学成分が含まれているため、長期間使用すると体内に蓄積して心身の健康に害を及ぼす可能性があります。
飲料に混ぜるだけで簡単に使用できるとろみ剤ですが、使用期間については医師と相談しながら慎重に決めていく必要があるでしょう。
高齢者への使用リスク
とろみ剤の使用により栄養バランスの偏りが生じると、免疫力の低下や感染症リスクの増加につながる可能性があり危険です。
とろみ剤自体には栄養価がほとんどないため、過剰に使用すると必要な栄養素の摂取が不足してしまうことがあります。
また、一部の食品と組み合わせることで栄養の吸収を阻害する場合もあるため、適切な使用を意識することが重要です。
高齢者の健康を維持するためには必要な栄養素をしっかり摂取できるよう、とろみ剤の種類や使用量を調整しながら、食事全体のバランスを考えることが大切です。
とろみ剤を使用する際の注意点
とろみ剤の使用方法を誤ると、健康に影響を及ぼす可能性が高まります。
ここでは、とろみ剤を使用する際の注意点について解説していきます。
片栗粉で代用すべきではない
料理にとろみをつける場合は片栗粉を使用することが多いですが、誤嚥を防ぐ目的であれば適切ではありません。
片栗粉の場合でも作りたての状態であれば十分なとろみがありますが、冷めてしまうと水のようにサラサラになってしまいます。
さらに、片栗粉は口の中の唾液に含まれるアミラーゼにより分解されてしまうため、口の中でとろみがなくなってしまうのです。
とろみがなくなると誤嚥のリスクが高まるので、片栗粉ではなく、とろみ調整食品を使用することが推奨されます。
ダマになっていないかを確認する
とろみ剤が完全に溶けきっていないと、食事にとろみがつかなくなります。
ダマになったとろみ剤を飲み込んでしまうと、窒息や誤嚥につながるおそれがあるので注意が必要です。
とろみ剤を使用する際は、とろみが安定するまでしっかりかき混ぜるようにしてください。
通常、とろみの状態が均一になるまで数分はかかるとされており、使用量をしっかりと計量して、とろみの状態を確認してから与えるようにしましょう。
服薬時に濃いとろみは使わない
とろみをつけた水を服薬時に使用すれば誤嚥を防ぐことができますが、濃いとろみだと錠剤が食道に張り付いてしまうおそれがあります。
食道にとどまってしまった場合は薬の効果が正しく発揮されないほか、誤嚥のリスクも高くなるので、服薬の際に濃いとろみを使用するのは避けてください。
できるだけ薄いとろみを使用し、長時間薬を浸漬させないことがポイントです。
嚥下反射に問題がない場合は不要
嚥下機能が低下しているからといって、必ずしもとろみをつける必要があるとは限りません。
とろみ剤の使用は、医師や言語聴覚士などの専門家による適切な評価が必要です。
嚥下反射が正常に働いている場合は、とろみ剤を使用しても誤嚥の予防にはつながらず、反対に飲み込みにくさを感じることがあります。
とろみ剤の使用が適切かどうかは専門家の診断を受けた上で判断し、自己判断で使用を決めないことが重要です。
とろみ剤を使うときのポイント
とろみはどのようにしてつければいいのでしょうか。
ここでは、とろみ剤の正しい使い方を解説していきます。
対象者に合ったとろみを選ぶ
とろみは対象者の嚥下機能に合わせて薄いとろみ・中間のとろみ・濃いとろみを使い分ける必要があります。
とろみの強さは、下記を参考にしてください。
- 薄いとろみ:ストローで吸える
- 中間のとろみ:フォークの間からゆっくりと落ちる
- 濃いとろみ:フォークの間から落ちない
どのとろみの強さが適切なのかは、専門の医師や言語聴覚士が判断します。
とろみの濃さを調整するときに、とろみ剤の粉末をそのまま追加してはいけません。
溶けきらずにダマになってしまうため、とろみが薄い場合は別のコップで作った濃いとろみを足して混ぜてください。
濃い場合は、同じ飲み物を足して混ぜるのが正しい調整方法になります。
市販のとろみ剤を活用する
とろみ食を作るときは、市販のとろみ剤(とろみ調整食品)を使用しましょう。
市販のとろみ剤を使用するメリットは、次のとおりです。
- ドラッグストアやコンビニで簡単に手に入る
- 混ぜるだけで溶ける
- 唾液や温度の影響を受けない
- 味や見た目が変わらない
- 短時間でとろみがつけられる
市販のとろみ剤なら失敗することが少ないので、とろみをつけるのが初めてでも安心して使うことができます。
食品に合わせてとろみを調整する
とろみ剤には食品ごとの相性があり、適切に調整することが重要です。
水やお茶はとろみがつけやすく、時間が経過しても均一な状態を保ちやすい特徴があります。
一方で塩分を含む味噌汁や、牛乳・ヨーグルトなどの乳製品、ジュースなどはとろみがつきにくい傾向があります。
とろみを加える際は、しっかりと混ぜながら状態を観察し、ダマができないように注意しましょう。
また、混ぜた直後だけでなく、時間が経過してからのとろみの状態を確認することも大切です。
正確に計量する
とろみ剤は商品ごとに適切な使用量が決められているため、正確に計量することが必要です。
目分量で使用すると、ダマになったり適切なとろみがつかなかったりすることがあります。
計量カップやスプーン、クッキングスケールを活用して適量を守り、食事の安全性を確保しましょう。
作り置きはその日のうちに使い切る
毎食ごとにとろみをつけるのは手間がかかりますが、とろみ付きの飲料であれば作り置きが可能です。
ペットボトルやプロテインシェーカーに水分ととろみ剤を入れて混ぜ合わせておけば、冷蔵庫に保管しておくことができます。
ただし、とろみ飲料の作り置きを何日もかけて飲むのは衛生的によくないため、当日中に消費しましょう。
とろみ剤に関するよくある質問
最後に、とろみ剤に関するよくある質問に回答していきます。
とろみの作り方は?
市販のとろみ剤の使用方法は、次のとおりです。
- とろみ剤の粉をコップに入れる
- 飲み物を注ぐ
- スプーンでしっかりとかき混ぜる
- 時間を置いてからとろみを確認する
冷たい飲み物を使用する場合は、泡立て器を使用したほうが混ざりやすくなります。
とろみが均一かを確認するため、とろみ飲料を作ってから5~10分の放置時間が必要です。
初めて作った場合は、試飲してとろみの状態を確認しましょう。
すべての飲み物に使うことはできる?
基本的に、とろみ剤の使用でとろみがつかない飲み物はありませんが、牛乳や果汁100%のジュースは水と比較するととろみがつきにくいです。
とろみがつきにくい飲み物を使用する場合は、とろみ剤を入れてから10分待ち、再びかき混ぜる「二度混ぜ」をするのが有効な対処法です。
この方法であれば普通に混ぜるよりも均一に混ざるので、ぜひ試してみてください。
とろみ剤の選び方は?
市販のとろみ剤には溶かすタイプから液状のものまで、さまざまな種類があります。
とろみ剤を選ぶときに注目したいポイントは、次のとおりです。
- ダマになりにくい
- ベタつかない
- 再調整しやすい
- 食材の色や味、香りを変えにくい
- 飲料の種類や温度の影響を受けにくい
とろみ剤の主成分は、でんぷん系とグアガム系、キサンサンガム系の3種類です。
現在はキサンタンガム系が主流で、飲みやすくなるように改よされています。
とろみ剤とゲル化剤の違いは?
とろみ剤は飲み物やスープなどの液体にとろみをつけ、喉をゆっくりと通るようにすることで、誤嚥を防ぐ目的で使用されます。
一方でゲル化剤は、水分や食品をゼリー状やムース状に固めることで、飲み込みやすくする役割を持ちます。
最大の違いは「固形化するかどうか」という点で、とろみ剤は液体の粘度を調整できますが固形化することはありません。
どちらも介護食づくりに役立つ調整食品ですが、使用者の嚥下機能に応じて適切に使い分けることが大切です。
初めて使用する場合はケアマネージャーや看護師、栄養士などの専門家に相談しながら導入しましょう。
まとめ
本記事では、とろみ剤を使用するメリットとデメリットについて解説しました。
とろみ剤は介護食など、水分にとろみをつけたいときに活用され、嚥下障害がある方の誤嚥の防止や誤嚥性肺炎の予防に役立つ便利なアイテムです。
基本的にとろみ剤は安全なものですが、使い方を誤ると副作用を引き起こしたり、誤飲や窒息のリスクが高くなったりするデメリットがあります。
とろみ剤の効果を正しく発揮させるためには、とろみ剤を使うときの注意点とポイントを理解しておくことが大切です。
介護関係者のサポートを受けながら、食事に取り入れましょう。