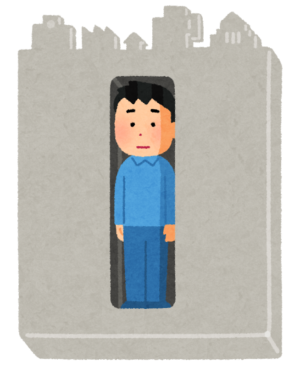実務者研修の費用はどれくらい?保有資格での違いや補助制度についても解説!

介護の仕事でキャリアアップを目指す中で、実務者研修の受講を考えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、実務者研修にかかる費用の目安や、費用を抑える方法、利用できる制度などを解説します。
これから受講を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
実務者研修の費用は保有資格によって異なる
実務者研修の受講費用は、一律ではありません。
受講者が持っている資格によって、必要なカリキュラムの内容や時間数が異なるため、それに応じて費用にも違いが出てきます。
以下では、資格別の費用目安について詳しく解説します。
無資格の場合
無資格の方が実務者研修を受講する場合、既に資格を持っている人と比べると多くのカリキュラムを履修する必要があります。
そのため、費用はほかの資格保有者よりも高くなる傾向にあり、おおよそ14万円〜22万円程度が相場ですが、スクールによっては分割払いに対応していたり、キャンペーンで割引があったりする場合もあります。
無資格からのチャレンジは不安もあるかもしれませんが、こうした制度やサポートを上手に活用することで、費用負担を軽減できる可能性があります。
ホームヘルパー1級を取得している
ホームヘルパー1級は、現在の「実務者研修」に相当するものです。
ホームヘルパー1級をすでに取得している方は、一部の科目が免除されるため、費用の相場は7万円〜10万円程度とやや安くなります。
事前に受講予定のスクールに、ホームヘルパー1級の資格がどのように扱われているかを確認しておくと安心です。
喀痰吸引等研修を修了している
喀痰吸引等研修をすでに修了している場合の費用は、7万円〜10万円程度ですが、加えて介護職員初任者研修(ホームヘルパー2級)の取得が受講の条件となっています。
そのため、すでに喀痰吸引等研修を修了していても、実務者研修の受講料が安くなるケースはあまり多くないのが現状です。
ただし、料金が変わらない場合でも喀痰吸引等研修で学んだ知識を実務者研修に活かせるため、学習の負担が軽減される可能性はあります。
介護職員初任者研修を修了している
介護職員初任者研修は、実務者研修と同様に2013年度以降に新設された資格で、以前は「ホームヘルパー2級」と呼ばれていました。
介護職員初任者研修を修了している場合も、いくつかの科目が免除となり、費用の相場は3万円〜5万円程度です。
初任者研修の修了者は、すでに基本的な知識や技術を習得しているため、学習の負担も比較的少なく済むというメリットもあります。
さらに、研修期間も短縮されることがあるため、効率的に実務者研修を修了することが可能です。
実務者研修の費用はスクールによっても異なる
実務者研修の費用は保有資格だけでなく、通学するスクールによっても大きく異なります。
スクールごとにカリキュラム内容やサポート体制、設備、通学スタイルなどが異なるため、それが受講費用に反映されているのです。
ここでは、スクール選びで費用に影響を与えるポイントについて解説します。
スクールの立地の影響
スクールの所在地が都市部にある場合、施設維持費や人件費がかさむため、地方よりも受講料が高くなる傾向があります。
しかし、交通アクセスが良く、通いやすい点はメリットです。
一方で、駅から離れた地方で開講されているスクールは、都市部に比べて受講料が安い場合もありますが、場所の特定が難しかったり、通学に不便を感じたりする場合があります。
費用面だけでなく通いやすさや自宅からの距離なども総合的に考慮し、自分にとってのバランスを見極めることが大切です。
通学か通信かコースによる影響
スクールによっては、通学型・通信型・通学と通信の併用型など、さまざまな受講スタイルを選べる場合があります。
通信型は教材を使った自宅学習が中心となる一方で、通学型は講師の指導や研修場所の維持に人件費がかかるため、一般的に通信型の方が費用は安く、通学型はやや高めになる傾向です。
ただし、通学型は実技指導が充実していたり、直接質問しやすかったりと、学びやすい環境が整っている点は大きなメリットです。
自分のスケジュールや学習スタイルに合わせて、無理なく続けられるコースを選ぶことが、結果的に費用対効果の高い選択となります。
スケジュール変更が可能か否か
実務者研修は長期間にわたって行われるものであり、基本的に遅刻や早退は認められません。
よって、急な予定変更に対応できるかどうかも、スクール選びの重要なポイントです。
振替授業の日程の再調整に柔軟なスクールは、その分サポート体制が充実していることが多く、費用がやや高めになる場合があります。
なお、振替が無料のスクールもあるため、事前に確認しておくと安心です。
仕事や家庭と両立しながら学ぶ方にとっては、多少費用が高くてもスケジュール調整がしやすいスクールのほうが安心できるでしょう。
キャンペーンやサポートが充実しているか
スクールによっては、期間限定のキャンペーンや早期申し込み割引、学生割引、友人や知人からの紹介割引などを実施していることがあります。
また、就職サポート付き、分割払い対応など、サポート内容が費用に含まれている場合もあります。
こうしたキャンペーンや付帯サービスの有無も、費用を左右する大きな要因のひとつです。
申し込み前に必ず公式サイトや資料で確認し、自分に合ったスクールを見つけることが大切です。
人材採用のためのスクールの場合
なかには、介護施設や人材紹介会社が運営しているスクールもあり、そうしたスクールでは受講後に特定の施設へ就職することを前提に、受講料が割安になるケースもあります。
その代わり、一定期間は紹介先での勤務が条件となることもあるため、自分のキャリアプランと照らし合わせて判断する必要があります。
「なるべく費用を抑えて早く現場で働きたい」という方には、非常に有効な選択肢のひとつですが、就職先が限られてしまう場合もあるので、よく考えてから受講しましょう。
実務者研修を修了するまでの日数と学習時間
実務者研修を受けるうえで気になるのが、「どれくらいの期間と時間が必要なのか」という点です。
仕事や家庭と両立しながら通う方も多いため、スケジュールを把握しておくことは重要です。
ここでは、修了までにかかる日数と学習時間について詳しく解説します。
修了までの日数
実務者研修の修了には、一般的に約6か月(半年)ほどの期間が必要です。
ただし、保有している資格やスクールごとのカリキュラム内容によって、修了までの期間は短縮できる場合があります。
例えば、介護職員初任者研修やホームヘルパー1級を取得している方は、一部の科目が免除されるため、4か月程度での修了が可能なケースもあります。
スムーズに進めるためにも、事前にカリキュラムや自分の生活スタイルに合ったスケジュールを確認し、計画的に受講を進めましょう。
学習時間
実務者研修では、受講時間にして450時間が必要とされています。
通信課程では自分のペースで進められるものの、課題提出や期限が決まっているため、計画的に取り組むことが求められます。
効率的に学習を進めるには、1日2時間程度は確保したほうが良いでしょう。
また、通学が必要な「医療的ケア」などの一部科目では、スクールでの実技指導を受ける必要があるため、勤務日との調整も重要です。
仕事をしながらの学習は大変ですが、少しずつ着実に進めていけば、無理なく修了することができます。
実務者研修の費用を抑えられる制度
実務者研修の費用を全額自己負担するのは大きな負担ですが、各種制度を活用することで、費用を大きく抑えることができます。
ここでは、代表的な支援制度を紹介しますので、自分が対象になるものがないかチェックしてみてください。
一般教育訓練給付金制度
ハローワークが実施している「一般教育訓練給付金制度」は、働く能力のある人の再就職を支援するために作られた国の制度です。
厚生労働大臣が指定する教育訓練の修了という条件を満たすことで、受講費用の20%が支給されます。
受講前にハローワークで申請手続きを行う必要があるため、必要書類の用意を余裕を持って準備するなど、スムーズに制度を活用していきましょう。
なお、上限が10万円までであり、4,000円以下の場合は支給されません。
求職者支援制度
雇用保険の受給資格がない方は「求職者支援制度」を利用できる場合があります。
この制度では、実務者研修を無料で受講できるうえに、生活支援金(月10万円)も支給される可能性があり、訓練実施機関への通所手当や寄宿手当を受けることも可能です。
職業訓練校などで行われる講座が対象で、前述の「一般教育給付金制度」と同様にハローワークを通じて申し込みます。
条件に合えば手厚い支援のため、検討してみてください。
市町村などの自治体での支援制度
実務者研修の受講に対して、自治体が独自に補助金や助成制度を設けている場合があります。
支援内容は地域によって異なりますが、受講料の一部を補助してくれる制度や、修了後に一定額が返金される制度などが一般的です。
制度の詳細や申請方法は自治体ごとに異なるため、住んでいる地域の福祉課や公式サイトで確認するのが確実です。
また、ハローワークでも同様の支援情報を案内していることがあります。
情報を探す際は「実務者研修 補助 〇〇市」など、地域名を入れた検索を行うと見つけやすいでしょう。
自分の地域で利用できる制度があるか、早めに調べておくと安心です。
母子家庭・ひとり親世帯の場合に利用できる制度
実務者研修を受けたいと思っていても、家庭の事情でシングルマザーやシングルファーザーとして子育てをしている方もいるのではないでしょうか。
ひとり親家庭を対象にした支援制度として、こども家庭庁と各自治体が連携して運営している「母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業」というものがあります。
支援の内容は以下の2つに分けられています。
【自立支援教育訓練給付金】
この制度では、対象講座の受講料の60%が支給されます。
ひとり親世帯の経済的自立を支援するためのもので、対象者には大きな助けになります。
ただし、実際に給付金が支給されるのは受講終了後であり、一時的に自己負担をする点に注意しましょう。
また、以下の条件を満たしている必要があります。
- 所得制限:児童手当を受給している。または同等の所得水準である。
- 雇用保険:受講開始時に雇用保険の一般被保険者ではない。
- 過去の受給:過去に自立支援訓練給付金を受給していない。
- 対象講座:国や自治体が指定する講座である。
受講前に自治体への事前相談が必要であり、上限が20万円で下限が1万2,001円となっています。
【高等職業訓練促進給付金】
ひとり親家庭が実務者研修を含む対象資格の職業訓練中に、月額最大10万円(住民税非課税世帯の場合は7万500円)の支援金が毎月支給される制度です。
さらに修了後には、月額5万円(住民税非課税世帯の場合は2万5,000円)が支給されます。
長期間にわたる学習が必要な場合でも、この制度を利用すれば負担が大きく軽減されます。
支給を受けるには以下の条件が必要です。
- 対象者:20歳未満の子どもを扶養する母子家庭の母、または父子家庭の父である。
- 所得制限:児童手当を受給している。または同等の所得水準である。
- 受講資格:対象となる養成機関で6ヵ月以上の訓練を受け、資格取得が見込まれる。
- 訓練内容:介護福祉士、保育士、理学療法士、看護師などの国家資格や就職に結びつく職業訓練である。
- 修了後の資格:訓練を終了し、資格取得後に就職が見込まれる。
【利用時の注意点】
実務者研修に関する補助制度を利用する際には、いくつか注意すべき点があります。
まず、ほとんどの制度は事前申請が必須であり、講座の受講前に対象となるかどうかを確認する必要があります。
申請のタイミングや必要書類、申し込み先などには期限や条件が設けられているため、余裕を持って準備しましょう。
また、給付金は申請すれば必ず受け取れるわけではなく、条件を満たしていない場合や不備がある場合は、支給されないこともあります。
特に注意したいのが、受講申し込み前に制度利用の相談をしていないケースであり、事前相談がないと補助制度の対象外となる可能性があるため、目安としては受講の1か月以上前には連絡しておくのが望ましいです。
少しでも受講を検討しているなら、早めに情報収集と相談を始めておくと安心です。
実務者研修を無料で受講できる制度
実務者研修の費用は決して安くありませんが、実は条件を満たせば無料で受講できる制度もあります。
これらの制度は、介護人材の確保や育成を目的としており、受講後の就業を前提とすることで、費用を支援してもらえる仕組みです。
ここでは、代表的な「無料で受講できる制度」について紹介します。
介護福祉士実務者研修受講資金貸付制度
各都道府県の社会福祉協議会が実施している「介護福祉士実務者研修受講資金貸付制度」は、最大20万円までの受講資金を無利子で借りることができる制度です。
この制度の最大の魅力は、「受講後、1年以内に介護福祉士資格を取得し、その後2年間介護の仕事を続けることで、返済が免除される」という点です。
利用には申請が必要で、募集期間が限られていることもあるため、早めに確認しておきましょう。
また、返還が免除される条件については各都道府県によって違うので、注意が必要です。
職業訓練
ハローワークが紹介する「職業訓練」でも、実務者研修を無料で受講できる場合があります。
- 公共職業訓練:雇用保険の受給資格がある求職者が対象
- 求職者支援訓練:雇用保険の受給資格がないフリーランスなどが対象
申し込み後の筆記試験や面接に合格することで無料での受講が可能であり、要件を満たす人は訓練期間中に失業保険や職業訓練受講給付金を受給することができます。
まずは、最寄りのハローワークで、実務者研修を含む職業訓練講座があるかを確認してみましょう。
実務者研修の費用を制度で補うメリット
実務者研修を受講する際、制度を活用することで得られる具体的なメリットを見ていきましょう。
受講費用が抑えられる
一番のメリットは、なんといっても経済的負担が軽くなることでしょう。
実務者研修の受講費用は比較的高めに設定されているため、受講したくてもためらってしまう人も少なくありません。
しかし、制度を活用することで、数万円から数十万円の費用が免除または補助されるため、自己負担額を抑えることができます。
特に無資格・未経験から介護福祉士を目指す方にとっては、初期投資を減らせることが大きな後押しになり、その後のキャリアアップに対しても大きな助けとなるでしょう。
精神的な負担が減る
費用面での不安が軽減されることで、受講者の心理的な負担も和らぎ、精神的にゆとりを持って学びに取り組めるというのは、大きなメリットのひとつです。
金銭的な心配が少なくなる分、カリキュラムの内容や実技の習得により集中しやすくなり、前向きな姿勢で学習に臨むことができます。
結果として、モチベーションを維持しやすくなり、学習効果の向上にもつながることが期待できます。
さらに、「せっかく制度を活用して支援してもらえるのだから、自分もできる限り頑張ろう」といった前向きな気持ちを後押しするきっかけになるかもしれません。
ほかの資格取得や研修も視野に入れられる
制度を活用して費用を節約できれば、その分の資金を今後のスキルアップやキャリアアップにまわすことも可能です。
例えば、介護福祉士の受験費用や参考書代、次の研修や講座の受講費用などにあてることができます。
将来を見据えたキャリア設計の一歩としても、支援制度の活用は非常に有効です。
このように、制度を活用することで得られるメリットは、金銭面だけでなくモチベーションや将来の選択肢にもつながっていきます。
使える制度があるのであれば、ぜひ積極的に活用していきましょう。
実務者研修の費用を制度で補うデメリット
制度を利用することで実務者研修の費用を補助してもらうことができますが、デメリットも存在します。
これらのデメリットを理解したうえで、制度を活用することが重要です。
ここでは、制度で費用を補う際に考慮すべきデメリットを解説します。
手続きが難しい
制度を利用するためには、さまざまな手続きが必要です。
例えば、申請書類の準備や必要な証明書の提出、申請先とのやり取りなど、事前に確認しておかなければならないことが多いです。
特に、自治体やハローワークなどの窓口が混雑している場合、手続きに時間がかかることや、給付金の種類によっては手続きの終了自体も1か月ほどかかってしまう場合があります。
そのため、早めに必要な情報を収集し、計画的に進めることが大切です。
自治体によって利用条件が異なる
実務者研修の費用を補助してくれる制度は、制度ごとに設けられている特定の条件を満たす必要がありますが、自治体ごとでも内容や条件が異なります。
例えば、ある自治体では条件を満たしていて補助金が支給されるものの、ほかの地域ではまったく支援がない場合や、条件を満たしていても書類審査や面接が必要なケースもあります。
そのため、自分が現在どの制度を利用することができるのかを事前に確認しておかなければなりません。
このように、必ずしも全員が利用できるわけではないことも理解しておきましょう。
立替が必要な場合がある
制度によっては、受講費用を一度立て替える必要があります。
その場合、申請が承認される前に自分で受講料を支払い、後日補助金が支給されるという流れであり、一時的に自己負担で受講を始めることに対する金銭的な不安が生じることもあります。
そのため、自己負担分を準備できるかどうかを事前に確認しておくことが重要です。
これらのデメリットをしっかり理解したうえで、制度を活用する方法を考えることが大切です。
手続きが煩雑であることや、支援が受けられない場合もあるかもしれませんが、それでも制度をうまく活用すれば、経済的な負担を大きく減らすことができます。
実務者研修の費用を抑えるそのほかの方法
実務者研修の費用を抑える方法として公的制度の利用だけではなく、自身が勤めている介護施設などの職場の支援制度や、実務者研修を実施しているスクールの割引制度を活用する方法もあります。
ここでは、2つの方法について詳しく解説します。
職場の資格取得支援
多くの介護施設や事業所では、職員の資格取得を支援する制度を設けている場合があります。
例えば、実務者研修の受講費用を一部または全額負担してくれることがあります。
このような制度を利用すれば、実務者研修の費用をほとんど負担せずに受講することができるため、職場の人事担当者に確認してみましょう。
スクールの割引制度
実務者研修を提供しているスクールや専門学校では、割引やキャンペーンを実施していることがあります。
例えば、早期申し込み割引や、キャッシュバックなど定期的に行われるキャンペーンで、受講料が割引されることがあります。
スクールのウェブサイトやパンフレットで、現在のキャンペーン内容を確認して、費用を抑えられるチャンスを見逃さないようにしましょう。
自分に合った方法を活用し、より経済的に研修を受けることができるので、積極的に情報を集めるのが大切です。
まとめ
実務者研修は介護福祉士を目指すうえで欠かせない資格ですが、費用面で不安を感じる方も少なくありません。
受講費用は保有資格やスクールの立地・カリキュラムによって大きく異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
また、一般教育訓練給付金や求職者支援制度、自治体独自の補助などを活用することで、費用負担を軽減することが可能であり、条件を満たせば職業訓練などで無料で受講できるケースもあります。
一方で、支援制度には申請の手間や条件の確認といった負担もあるため、早めに情報収集し、計画的に進めることが大切です。
自分の状況や目的に合った支援制度を選び、費用を抑えながらキャリアアップを目指しましょう。