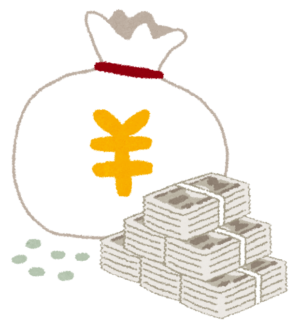胃ろうとは何か?メリット・デメリット、後悔しないためのポイントを詳しく紹介
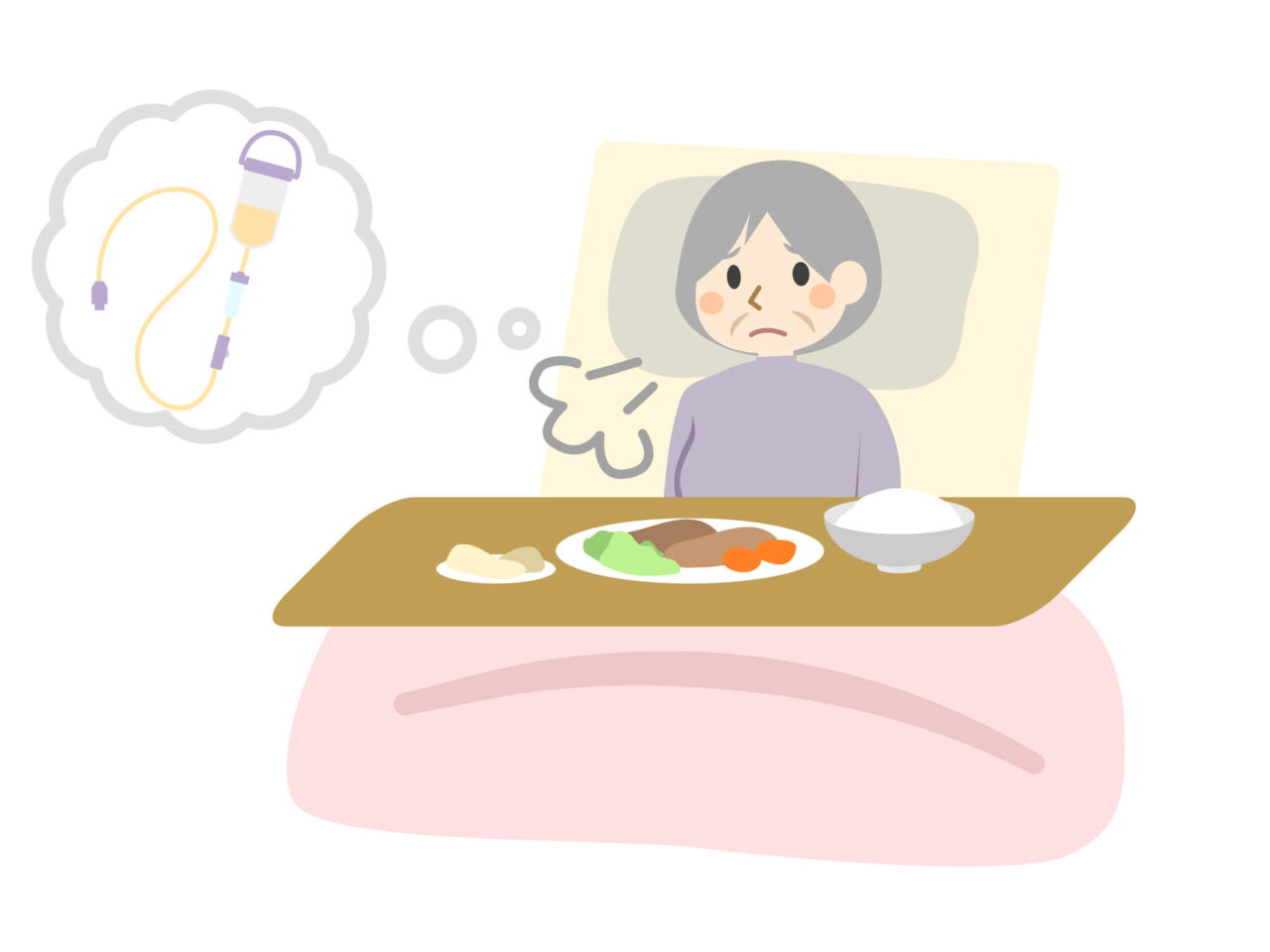
胃ろうとは、口から食べることが難しい方に対して、胃に直接栄養を届ける医療的な方法です。
「どんな人に必要?」
「苦しくないの?」
「家族の介護はどうなる?」
そんな疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、胃ろうとは何かを紹介し、その種類やメリット・デメリット、後悔しないために考えておきたいポイントまでを分かりやすく解説します。
ご家族の選択や、今後のケアについて考える際のヒントになれば幸いです。
胃ろうとは?どんな人に必要?
「胃ろう」と聞いても、どんなものかよく分からない方も多いかもしれません。
ここでは、基本的な仕組みや、必要とされるケースについて分かりやすく説明します。
胃ろうとは
胃ろうは、口から食べるのが難しい方に対して、胃に管を通して栄養を入れる方法の一つです。
PEG(Percutaneous Endoscopic Gastrostomy:経皮内視鏡的胃瘻造設術)と呼ばれる手術により、腹部に開口部を設ける処置を行い、そこから胃へ栄養を送り届けます。
長期間にわたって口からの摂取が難しい方にとって、安全かつ安定した栄養補給手段となります。
胃ろうが必要な人
胃ろうは、基本的に口から飲食物の摂取が難しい方に取り入れられます。
具体的には以下のとおりです。
- 嚥下機能が低下した人
- 誤嚥性肺炎になりやすい方
- なんらかの原因より食道が閉塞している人
- 重度な認知症や障がいにより経口摂取できない人
- 口や喉まわりの手術後により経口摂取できない人
このように嚥下機能が低下した高齢者や、病気や障がいを患っている方、手術後の方などに導入されます。
なお、処置を行った後でも機能回復が見込めれば、取り外して通常の食事に戻すことも可能です。
腸ろうとの違い
胃ろうを聞いたことある方の中には、「腸ろう」という似た言葉を聞いたことがある人も多いかもしれません。
腸ろうは、おなかの下あたりに開けた小さな開口部にチューブを挿入し、腸へ直接栄養を届ける医療手段です。
経管栄養を検討する方の中で、胃になんらかの疾患がある場合に用いられます。
メリットとしては、内容物の逆流を抑えやすいため、誤嚥による肺炎や食道の炎症が起こりにくいといったことが挙げられます。
胃ろう・腸ろう以外の経管栄養方法
胃ろう・腸ろうといった経管栄養には、そのほかに「経鼻経管栄養」と呼ばれる方法があります。
経鼻経管栄養は、鼻の穴から細い管を体の中に通し、胃の中に直接ごはん(栄養)を届ける仕組みです。
外科手術の処置が不要で、管の取り外しも簡単に行えるため、口から食べられない方のために短期的に導入されます。
胃ろうには4種類の方法がある
胃ろうには大きく分けて、体外部の形状が2つ、胃内部の形状が2つの計4種類の方法があります。
体外部には「ボタン型」と「チューブ型」、胃内部には「バルーン型」と「バンパー型」があり、これらを組み合わせて使用されます。
ここでは、4種類の方法や特徴について見ていきましょう。
体外部
体外部の形状には、「ボタン型」と「チューブ型」があり、それぞれ形状や使いやすさなどが異なります。
【ボタン型】
ボタン型は、使用時に蓋を開き、管をつないで使用します。
小さい形状なので、目立ちにくく、体を動かすときにも邪魔になりません。
また、取り外ししにくいため、誤って抜去してしまう方でも装着できます。
しかし、使用時に管を取り付ける手間が必要なことや、開閉しにくいところがデメリットとなります。
【チューブ型】
チューブ型は、腹部に管が取り付けられており、使用時は先端の注入孔バルブを開けて栄養補給します。
使用時の接続は簡単ですが、腹部から管が出ているので目立ちやすく、体を動かすときに邪魔になりやすいです。
また、管の内部が汚れやすく、洗浄の手間がかかります。
胃内部
胃内部の形状には、胃内部で風船を膨らませて固定する「バルーン型」と、突起のような部分で胃壁に引っかけて固定する「バンパー型」があります。
【バルーン型】
バルーン型は、内部に蒸留水を含ませて風船状にして固定します。
交換期間が1~2カ月と短いスパンになるところがマイナス要因となりますが、交換時の痛みが少なく、体への負担が少ないところがメリットです。
【バンパー型】
バンパー型は、突起のような部分で胃壁に引っかけて固定するため、抜けにくいところがメリットです。
また、交換期間も約6カ月と長いところも特徴です。
しかし、しっかり固定できる反面圧迫感を覚えやすく、また交換時に痛みを伴いやすいところもデメリットとなります。
胃ろうのメリット・デメリット
胃ろうには、日常生活の質を保ちながら安全に栄養をとれるといったメリットがある一方で、医療的な処置が必要となるほか、いくつかの注意点やリスクも存在します。
ここでは、導入する際に知っておきたいメリットとデメリットを紹介していきます。
メリット
メリットには、以下の6つが挙げられます。
【利用者の身体的な負担が軽い】
胃ろうは、腹部を切開し管を取り付けるため、見た目的には違和感があるかもしれませんが、実際には不快感や負担は軽く済みます。
一方の経鼻経管栄養では、鼻から喉にかけて痛みや違和感を覚えやすく、長期間の使用によって粘膜が傷ついたり、発声や呼吸に影響を及ぼしたりすることもあります。
手術により一度装着してしまえば、その後は体にかかる負担が軽く済むので、長期的な栄養管理が必要な方にとっては、より快適で安定した生活を送ることが可能です。
【チューブが外れにくい】
胃ろうは、一度装着すると抜ける心配はほとんどありません。
一方の経鼻経管栄養は、鼻や喉の不快感から取り外してしまう方も多く、再び取り付ける手間が発生します。
【口を使って食事できる】
胃ろうを装着すると口から摂取できないと思われがちですが、口からの食事も問題ありません。
そのため、嚥下訓練も並行して行えます。
ただし、嚥下機能が落ちている方や誤嚥のリスクがある方は、肺炎になる可能性もありますので、担当の専門家の方と相談しながら進めることが大切です。
【入浴・運動・リハビリができる】
胃ろうを装着した後も、入浴や運動、リハビリを問題なく行えます。
入浴時は設置部にカバーを掛けない状態で入浴でき、洗浄も装着部を強くこすらない限り問題ありません。
また、過度に行動を制限する必要はなく、本人の体調や状態に合わせて無理のない範囲で活動を楽しめます。
【飲み薬の使用が可能】
胃ろうの方で口から飲食物が摂取できない場合、服薬が難しいと思うかもしれません。
しかし、飲み薬は装着部からも問題なく投薬可能です。
ただし、薬によっては管に詰まりを起こす可能性があるため、投薬手順は必ず確認しましょう。
【感染の危険性が比較的低い】
感染の危険性が比較的低いところも胃ろうのメリットです。
鼻や口を経由しないため、外部から細菌が侵入しにくく、経鼻経管栄養に比べて呼吸器系の感染リスクが低くなります。
ただし、チューブが原因で感染症を起こす可能性があるため、適切なメンテナンスが必要です。
デメリット
デメリットには、次の5つが挙げられます。
【手術を行う必要がある】
胃ろうを行うためには、手術によりおなかに装具を設置する必要があります。
約30分という短い時間の手術なので、そこまで体に負担はありませんが、腹部に穴を開けることはご本人にとって精神的な負担になる可能性があります。
【定期的なメンテナンスが必要】
栄養補給が終わったら、必ず洗い流す処置を行いますが、いくらきれいに洗浄したとしても内部に栄養剤が残ります。
栄養剤が残っていると、そこから細菌やウイルスが増殖し、感染症や汎発性腹膜炎になる可能性が高くなるため、使用している器具に応じたメンテナンスや交換が必要になります。
また、メンテナンスには診察や交換する費用が含まれますので、金銭的な負担があることにも注意が必要です。
【誤嚥性肺炎になる可能性が高くなる】
誤嚥性肺炎を起こすリスクがあって胃ろうをする方も多いですが、肺炎の可能性が決してゼロになるわけではありません。
食べ物が気管に入ることは少なくなりますが、口から出てくる唾液が気管に入ることはなくならないからです。
また、食べ物を摂取しないからといって口腔内のケアを怠っていると、唾液とともに雑菌が気管内に入り、肺炎を起こしてしまいます。
そのため、毎日の口腔内ケアもしっかり行わなければなりません。
【おなかの中のものが逆流することがある】
胃ろうを導入している場合、胃の中に入ったものが食道方向へ戻ってくるケースがあります。
場合によっては、誤嚥性肺炎や逆流性食道炎になる可能性があるため注意が必要です。
逆流を起こさない工夫としては、食中から食後の姿勢に気を付けたり、栄養剤の形状をトロミのついたものに変えたりする対策が必要です。
【肌トラブルが起こりやすくなる】
胃ろうをしている方の中には、肌トラブルを起こしやすい方もいます。
例えば、設置部が皮膚に埋没してしまったり、不良肉芽(にくげ)ができてしまったり、設置部周辺に炎症が起こったりします。
場合によっては、医療処置を必要とする可能性が出てきますので、日頃からよく観察することが大切です。
胃ろうの方の介助方法と食事の種類
胃ろうは在宅でも行えるという大きなメリットがありますが、介助する側には注意が必要です。
特に、適切な方法での介助や、食事の管理が重要となります。
ここでは、胃ろうの介助方法と食事の種類について詳しく見ていきましょう。
胃ろうの介助方法
胃ろうの介助は、以下の手順で行います。
- まずは手洗いを行い、衛生状態を整えます。医薬品を投与する場合は、冷たすぎないように人肌程度に温めておきます。
- 栄養剤をイリゲーター(専用の容器)に注ぎ、チューブと接続します。その後、利用者の体勢を整え、椅子に座るか、ベッドの背もたれを30~90度の角度に調節して、上半身を起こした状態にします。
- 栄養剤を体内に送るため、胃ろうの器具に専用のチューブを取り付けます。その前に、シリンジで軽く陰圧をかけて胃内の空気を抜き、内容物の残り具合を確認します。
- 栄養剤は少量ずつ、ゆっくりと入れます。もし胃に内容物が多く残っている場合は、注入量やスピードを見直してください。
注入中は必ずそばにいて、異常がないか観察しましょう。離れる場合にはモニターを使用することも検討してください。
- 半固形の栄養剤やペースト状のミキサー食を使う際には、シリンジに吸い取ってからゆっくりと入れます。医師から量や注入間隔の指定がある場合は、必ずその指示に従います。
- 投薬する場合は、水で溶かしてシリンジに取り、同じくチューブを通して注入します。すべての投与が終わったら、白湯を使ってカテーテル内に残った成分を洗い流します。
- 最後に、設置部周辺に漏れがないか確認し、清潔に拭き取ります。注入後は逆流を起こさないために、最低でも1時間は上体を起こした姿勢を保ちましょう。
食事の種類
胃ろうの食事は、大きく分けて「食品」と「医薬品」の2種類に分けられます。
それぞれの特徴は、以下の表のとおりです。
| 食品 | 医薬品 | |
| 保険適用 | なし | あり |
| 処方箋の有無 | 不要 | 必要 |
| 注入時間 | 1回/5~10分 | 1回/1~2時間 |
| メリット | ● ミキサー食なら家族と同じものを食べられる | ● 保険適用のため安く済む |
| デメリット | ● 種類が少ない | ● 逆流による誤嚥のリスクがある ● 皮膚トラブルがある ● 下痢・嘔吐・高血糖のリスクがある |
どちらを使用するかは、ご本人の状態を確認しながら選びましょう。
胃ろうの方を介護するときの注意点
胃ろうが必要な方への介護では、いくつかの点に気を付ける必要があります。
ポイントを知ることでよりよいケアにつながりますので、ここで確認していきましょう。
正しい姿勢で介助する
胃ろうで栄養剤を注入する際は、通常の食事と同様に正しい姿勢で行うことが大切です。
正しい姿勢で行わないと、注入した栄養剤が逆流するリスクが高くなります。
具体的には、上半身を30~45度起こし、ご本人に負担がない姿勢に整えましょう。
また、逆流を防止するためにも注入後はすぐに横にならず、30分から1時間程度そのままの状態で過ごすことも大切です。
口の中のケアを丁寧に行う
胃ろうを行うと、口から飲食物を摂取する機会が減ってくるため、唾液が出る量が少なくなってきます。
唾液は口の中の洗浄にも役立っており、少なくなってくると、口腔内に雑菌が繁殖しやすくなります。
口腔内で繁殖した雑菌が唾液や痰とともに気管内に入ってしまうと、誤嚥性肺炎を起こす可能性が高くなるため、日常の口腔ケアは念入りに行いましょう。
清潔さをキープする
胃ろうで使用するチューブや設置した皮膚まわりは、きれいに保ちましょう。
特にチューブは、栄養剤が高カロリーであることから、内部に付着していると雑菌が増えてしまう原因になります。
使用後の洗浄や乾燥はもちろん、保存方法も清潔さをキープできるように気を付ける必要があります。
また、栄養剤はものによって保存方法が異なりますので、適切な方法を確認してから保存しましょう。
本人の健康状態に応じた栄養剤を選ぶ
胃ろうで使う栄養剤には、消化のしやすさに応じた「消化態栄養剤」「半消化態栄養剤」「成分栄養剤」などがあります。
例えば、消化吸収が低下している方には、あらかじめタンパク質が分解された消化態栄養剤が適しています。
また、消化吸収機能に問題ない方であれば、タンパク質がそのままの状態で含まれている半消化態栄養剤がよいでしょう。
さらに、栄養剤の形状も粉末・液体・ゼリーとあり、誤嚥防止や注入機器に応じた使い分けが必要です。
本人の状態に合わせて、医師や栄養士と相談しながら適切な種類を選びましょう。
栄養注入は医療・看護のプロに任せる
胃ろうを行うことは医療行為に該当するため、一般の方は行えません。
行うためには、看護師や介護福祉士といった資格が必要です。
ただし在宅で行う場合は、専門家から指導を受けることで、ご家族が対応できるケースもあります。
皮膚トラブルに注意する
胃ろうを造設すると、設置部分に炎症が起こるケースがあります。
そのままにしておくと、膿が出たり出血を伴ったりする可能性があるため、毎日の観察が重要です。
また、清潔さの保持も重要ですので、入浴時の洗浄はしっかり行いましょう。
胃ろうを抜いてしまったときに備えておく
認知症を患っている方や、意識がはっきりしない状態の方は、誤って設置部を取り外してしまうケースがあります
一度抜いてしまった設置部は、一晩で塞がってしまうほど、短時間で閉じてしまいます。
そのため、抜けてしまった際には迅速な対応が必要です。
すぐに連絡できるよう、かかりつけの病院や訪問看護ステーションの連絡先をあらかじめ控えておきましょう。
また、自己抜去を防ぐために、設置部を衣類や腹巻き、専用の保護カバーなどで覆うといった予防策を、日頃から整えておくことが重要です。
胃ろうを決断する際に考えるべきこと
老化や疾患により、通常の食事をとることが難しくなったとき、延命や栄養補給の手段として胃ろうが提案されますが、検討する方の多くが当事者の家族であることがほとんどだと思います。
医療的な処置である以上、ご本人の生活の質(QOL)や意思をどのように尊重するか、また今後の介護方針にどのように影響するかなど、多くの視点から判断することが必要です。
そのため、決断する前に胃ろうを正しく理解し、本当に胃ろうが必要なのかをご本人や家族で丁寧に話し合っておきましょう。
胃ろうが本当に必要かどうか考える
胃ろうをご家族が望んだ場合、「本人の意思を無視した決断」といわれることもあります。
本人の意思を尊重するためにも、気持ちをくみ取ったり、胃ろうをしなかった場合について考えたりすることが大切です。
【胃ろうを望む方の割合】
厚生労働省が行った調査によると、胃ろうを望まない方の割合が全体の約7割、望む方の割合が全体の1割であったことが分かっています。
また、2012年に「医療経済研究機構」が行った調査では、日常生活の改善や回復が期待できず、さらに経口での食事が将来的にも困難な場合でも望むケースが少ないという結果も出ています。
この結果がすべてではありませんが、望む方は全体的に多くないということです。
【後悔しないためにも本人の気持ちをくみ取ることが大切】
決断するのがご家族であっても、実際に胃ろうを造設するのは本人ですので、気持ちをくみ取らないまま決断してしまうと、後悔につながることになります。
医師や施設の判断だけで進めず、本人の意思や可能性をしっかり確認しましょう。
とはいえ、選択するか悩むケースもあります。
最近では、嚥下リハビリによって改善する事例もあるため、まずは専門医に相談し、ほかの選択肢も視野に入れた上で判断しましょう。
【胃ろうをしなかった場合についても考える】
胃ろうを選択する際は、しなかった場合についても考えましょう。
例えば、経鼻経管栄養や静脈栄養など、そのほかの経管栄養方法を検討するのも一つです。
また、終末期で延命を考えていない方であれば、決断せずに自宅で看取られるのも選択肢に入ります。
どの選択を決断するにしても、メリット・デメリットはありますので、当事者と家族、専門家との間でよく検討しましょう。
胃ろうをやめることはできる?
飲食が再開できる状態に戻れば、胃ろうはやめられます。
しかし、取りやめる人の多くは、一時的な処置として実施されたケースです。
嚥下状態や認知機能が低下している高齢者が抜去するのは難しいでしょう。
なお、設置部を抜去すると一晩程度で穴は塞がります。
胃ろうにかかる費用と保険適用について
胃ろうを決断すると、手術代や栄養剤にかかる費用がかかってきます。
ご家族の金銭的負担となる場合もあるため、金額をよく調べてから決断することが大切です。
具体的には、以下の表の費用がかかってきます。
| 項目 | 費用 |
| 造設手術費用 | 10万円程度 |
| 入院費 | 1万円+食事代+ベッド代など ※75歳以上であれば自己負担上限44,400円 |
| 交換費 | バルーン型:1万円程度 バンパー型:2万2,000円程度 |
| 栄養剤 | 1カ月/2~3.5万円 |
造形手術費用は、高額医療費制度が適用されると自己負担額を減らせます。
栄養剤に関しては、医薬品と食品から選べますが、食品は保険適用とならないことに注意が必要です。
また、自宅療養で利用するケースでは、訪問診療を依頼する必要があるため、管理費と合わせて毎月6万円程度かかるケースもあります。
胃ろうの方が介護サービスを利用する際の施設選びのポイント
在宅でも胃ろうは行えますが、家族の負担が大きく、対応が困難な場合もあります。
その場合は介護施設の検討が必要です。
この章では、胃ろうの方が介護サービスを選択する際、どのような点に注目すべきかをご説明します。
利用を断られるケースもある
胃ろうの方が介護サービスを利用する際、施設によっては利用を断られるケースもあります。
例えば、以下に挙げられる場合は断られる可能性が高いです。
- 看護師が24時間常駐していない
- スタッフが必要な資格を持っていない
- 環境的に対応が難しい
上記に当てはまる場合は、受け入れてもらえないこともあるため、施設側に確認する必要があります。
痰吸引ができる体制か確認する
介護サービスを選ぶ際、胃ろうへの対応が可能かどうかの確認に加え、痰吸引ができる体制があるかどうかも確認しましょう。
胃ろうする方は嚥下機能の低下により、自力で痰を排出できないケースが多いため、吸引処置ができるスタッフは必須です。
排出できない場合、誤嚥性肺炎を引き起こす可能性もあるので、対応できるかは必ず確認しましょう。
なお、痰吸引は医療行為にあたりますので、特定の資格保有者や研修を受けた方しか処置できないことを覚えておきましょう。
認知症や精神疾患がある場合でも対応できるか確認する
認知症や精神的な障害を抱える方では、誤ってチューブを抜いてしまうことや安静を保つのが難しいことがあります。
そのため、対応が可能か事前に確認しましょう。
状況によっては、ミトンの着用や拘束といった対応を求められるケースもありますので、しっかりと理解した上で介護施設と対応方針について話し合っておくことが重要です。
まとめ
本記事では、胃ろうとは何かを詳しく解説し、必要な方や種類、メリット・デメリットなどを紹介しました。
胃ろうは、飲食物を口から摂取するのが難しい方のために、胃から直接栄養補給を行う経管栄養方法の一つです。
検討する際は、ご本人の意思や生活の質(QOL)、今後の介護方針などを総合的に考慮し、必要に応じて医療・介護の専門家と相談しながら最適な判断を行うことが大切です。