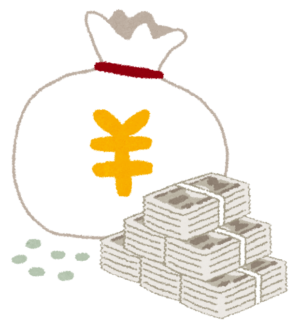臥床とは?介護のポイントや離床との違いについて解説

「臥床(がしょう)」とは介護用語で、介護現場では「臥床介助」という言葉でよく使われます。
介護の仕事を始めて「臥床」という言葉は聞いたことがあっても、具体的に何を指すのかよく分からない方もいるでしょう。
この記事では、臥床とは何か、その種類や「離床」との違いについて分かりやすく解説します。
介護での臥床とは
臥床は、主に介護の現場で使われる言葉で、一般的な意味では寝ていることをいいますが、介護の現場で「臥床介助」として使われる場合には、起きている人を寝かせる動作のことをいいます。臥床や臥床介助、介護と介助の違いなど、「臥床」の基本を詳しく解説します。
臥床とは
臥床とはベッドなどで寝ている状態のことで、読み方は「がしょう」です。介護の専門用語として臥床介助と使われ、起きている要介助者をベッドなどに寝かせることをいいます。
例えば、車椅子を使用している人のオムツ交換をするときに、ベッドに寝かせる必要がありますが、その一連の動作が「臥床介助」です。
介護と介助の違い
介護と介助は、どちらも介護業界では日常的に耳にする言葉ですが、明確な違いが定義されているわけではありません。法的な使い分けは行われていませんが、厚生労働省においては「介助」とは「介護」を提供する時の手段として使われています。
そもそも「介護」とは、サポートが必要な人に対して支援を行うことをいいますが、支援を通して要介護者の方が生活の質を向上させる目的があります。
介護と介助の違いを、分かりやすく表にまとめました。
| 介護 | 介助 |
| 身体介助 生活援助 | 食事介助 排泄介助 入浴介助 歩行介助 移乗介助 更衣介助 |
介護は要介護者の自立を目的としているもので、介助は主に介護を行う手段を指しています。
臥床介助のポイント
臥床介助は一日に何度も行う必要があり、介助を受ける人が安心して介助者に任せられることが大切です。以下に、臥床介助を行う際のポイントを挙げます。どれも重要な内容なので、すべてしっかり押さえておきましょう。
- 要介護者の体に沿う臥位
- 定期的な体位交換
- なるべく自力で体を動かしてもらう
- 腕力ではなく体全体で要介護者を支える
- ムリな体勢で介助しない
寝返りができなくなると、手足のむくみや血栓、床ずれなどが起こりやすくなります。こうした症状を防ぐためには、寝返りのように定期的に体の向きを変えることが必要です。その際に行うのが「臥床介助」で、介助者がサポートしながら安全に体位を変える介護技術の一つです。
臥床介助を行う際は、介助する側の腰や膝に負担がかかりやすいため、正しい姿勢を意識することが大切です。背中をできるだけまっすぐに保ち、無理な体勢を避けて、体への負担を軽減しましょう。
看護での臥床
看護における臥床とは、患者さんがベッドに横になっている状態を指します。起き上がれない理由はそれぞれ異なり、体調が優れず起き上がれない人や、安静にしていなければならない人もいます。
臥床介助は、患者さんがベッドに横になるときの手助けや、横になっている状態で体の向きを変えるといった体位変換も、臥床介助の一つです。
臥床が必要になる主な原因
臥床は高齢者だけでなく、あらゆる年代で必要になることがあります。どのようなときに寝ている状態でいることが必要とされるのか、臥床の原因について解説します。
手術後
手術後は点滴や傷の痛みで体を動かすのがつらく、同じ体勢が続きがちです。しかし、長時間同じ体勢で臥床すると回復が遅れるだけでなく、床ずれのリスクも高まります。そのため、術後の苦痛を長引かせないためにも、適宜体勢を変えることが大切です。
病気療養中
病気やケガをしたとき、症状によっては横になって安静にしなければなりません。しかし、長期間にわたって横になった状態が続くと、心身の機能低下につながるおそれがあります。
しかし、安静な状態を続けると、自立生活が困難な「寝たきり」の状態に陥るおそれがあるため注意が必要です。
高齢による衰弱
高齢による衰弱は、体を動かすことが難しくなるだけでなく、人と会う機会が減ることで脳への刺激が少なくなり、認知機能の低下を招きます。これが寝たきりの生活につながることもあります。
また、心の状態は体の健康に大きく影響します。心が弱ってしまうと、体の衰えも進みやすくなるため、心身のケアが重要です。
臥床の種類
臥床には、仰向けやうつ伏せで寝る姿勢など、その種類はさまざまです。長時間同じ姿勢の臥床は、床ずれである褥瘡や、筋力の低下が見られるなどのリスクがあるため、姿勢を定期的に変える体位交換を行わなければなりません。
ここでは、介護で行う臥床の種類と、姿勢ごとの特徴や注意点を解説します。
仰臥位(ぎょうがい)
仰臥位は、仰向けで寝た状態のことです。顔と腹部が天井を向き、足を真っすぐに伸ばした状態のため、エネルギー消費が少なく休養するための基本姿勢といえます。
仰臥位でベッドが水平だと呼吸がしにくくなることがあるため、枕で頭を少し高くするなど、上半身をわずかに起こすとよいでしょう。
食事の後すぐに仰臥位をとると、食べた物が逆流したり、誤嚥性肺炎を起こしたりすることがあるので、注意しなければなりません。
背殿位(はいでんい)
背殿位は、仰向けで横になった状態で両ひざを曲げた姿勢のことです。腰痛がある場合にこの姿勢をとると、腹部の緊張が緩和され、腰への負担が軽減されるメリットがあります。
仰臥位よりも体の重心が背中から臀部に集中するため、介護職員にとっても介助にかかる体への負担が軽減され、体位交換や離床介助をしやすくなります。
側臥位(そくがい)
側臥位は、仰臥位から体が90度横を向いた状態をいい、左右の区別をつけることが必要な場合には、右側臥位または左側臥位と表現します。
体位交換で側臥位をとる場合、腕が体の下敷きになりがちなので、注意が必要です。体の下敷きになると腕に体重がかかりますが、そのような状態が続くと床ずれになるので、腕を前方に引き出しましょう。
側臥位は仰臥位よりも体が不安定な状態になるため、両腕でクッションを抱えたり、背中にクッションを当てたりすると安定感があります。
半側臥位(はんそくがい)
半側臥位は、仰向けで横になった状態から45度ほど横に傾いた状態のことです。要介護者自身では取りづらい姿勢のため、背中やお尻にクッションを当てると安定します。
半側臥位は体の背面に傷や床ずれがあり、患部に体圧がかかることを防ぐために行うことが多い姿勢です。側臥位で負担がかかると床ずれができやすいですが、半側臥位にすることで患部への圧迫を防げます。
屈曲側臥位(くっきょくそくがい)
屈曲側臥位は両ひざをかかえて、胎児のような姿勢となります。側臥位よりも体が床に接している部分が多いため、バランスを保ちやすいことが特徴です。
手足を抱え込むことで股関節や膝、腕を曲げるため、全身の緊張が緩んでリラックスしやすくなります。
屈曲側臥位は横向きの姿勢で首に負担がかかるため、枕を使い、首と背骨のラインがまっすぐになるように調整が必要です。
腹臥位(ふくがい)
腹臥位は、うつ伏せで寝ている体勢をいいます。首は左右どちらでも自然なほうを向き、上下肢を曲げることでリラックスできるのが特徴です。
しかし、高齢者の場合、長時間うつ伏せ(腹臥位)を続けると、気道が圧迫されて窒息のリスクが高まったり、脊椎の圧迫骨折を引き起こしたりする可能性があるため、十分な注意が必要です。
自分ひとりでは体位変換しにくい姿勢なので、腹臥位の状態で要介護者から離れず、できるだけ短時間で姿勢を変えましょう。
臥床と離床の違い
介護や医療の現場でよく使われる言葉に、「離床」と「臥床」があります。
離床とは、ベッドから起き上がり、ベッドから離れることを指します。離床は、一定の身体機能が維持されている状態であり、リハビリの一環として体力や生活能力の回復に効果的だと考えられています。
一方、臥床は、ベッドなどに横になっている状態を意味します。病気やけが、加齢などによって身体機能が低下すると、自力で起き上がることが難しくなり、横になったまま過ごす時間が増えます。
長時間臥床状態が続くと、筋力低下などにより体を動かすことがさらに困難になり、結果的に長期臥床となることがあります。このような場合は、看護師や介護福祉士による介助が必要となります。
臥床で行われる介助
臥床で行われる介助はさまざまな種類がありますが、どの介助方法も同じように行うのではなく、要介護者の状態を見ながら、適切な方法で行わなければなりません。ここでは3種類の介助について、ポイントを解説します。
起床介助
常にベッドに横になっている状態ではなく、ベッド以外の場所で生活ができる人に対しては、起床介助を行いできるだけベッドから離れるように促すことが大切です。基本的な生活スペースがベッドであっても、トイレに行くなどの行動ができる人にも起床介助を行います。
ベッドで仰向けに寝ている人の起床介助では、まず仰向けのまま両膝を曲げ、膝を抱え込むような体勢で起き上がるようにする介助方法をとります。
急に起き上がらせると血圧が下がりやすく、貧血を起こすことも考えられます。起床介助の注意点は、一つひとつの動作を、急がずにゆっくりと進めていくことです。
排泄介助
トイレに行けない状態の介護では、ベッドに横になったまま排泄介助を行います。排泄介助は、介護者の体に大きな負担がかかるため、腰を浮かせるなど、ご本人ができる動作はできるだけ自分で行ってもらいましょう。
また、横向きの側臥位がとれる場合は、側臥位での排泄介助が介護者の負担軽減につながります。
排泄介助は単なる作業ではなく、介助の方法によっては要介護者の自尊心を傷つけることもあるため、丁寧な配慮が必要です。さらに、プライバシーにも十分配慮しながら排泄介助を行ってください。
体位交換
体位交換は、トイレや着替えといった生活の中で必要なことをする際の介助であるだけでなく、床ずれを防ぐためにも必要です。
体位交換の手順は、両ひざを曲げて体の前で腕を組み、体を小さく丸めます。寝返る方向へと顔を向けると、向けた方向へ体の重心が移動し、介護職員の負担を抑えて体の向きを変えられます。
体位交換は、要介護者の体が大きい場合や、小柄な介護職員でも、必要な力を最小限に抑えられることが大きなポイントです。
注意しなければならないことは、枕の周りに何か置かれていないかを体位交換を行う前に確認することと、体位交換後の体の位置です。ベッドの真ん中あたりが理想的な位置ですが、左右どちらかに大きく移動してしまった場合も、サイドレールとの間に十分な間隔があるかどうかを確認するようにしましょう。
長期間臥床が続いたときのリスク
高齢になると、骨折や病気などによって長期間寝たきりの臥床状態になりやすく、長期間にわたって臥床が続くと、床ずれなどさまざまなリスクがあります。長時間の臥床で起こるリスクについて解説します。
臥床状態による廃用症候群
廃用症候群とは、寝たきりである臥床の状態が長期間続いたことにより、筋力や呼吸機能、認知機能などの低下や、抑うつ状態が起こることをいいます。
若くて健康な人でも、長期間寝たきりの状態が続くと筋力が低下することが分かっています。高齢者の場合は病気でなくても身体機能の低下が起きているため、さらに廃用症候群のリスクが高いといえるでしょう。
筋力の低下や筋萎縮が起きると転倒しやすくなります。また、骨密度が低下すれば骨折しやすくなり、結果的にさらに長期間の臥床が続くリスクが生じます。そうなると影響は体だけでなく、生活の質を低下させてしまい、精神的なリスクにもつながるため、注意が必要です。
定期的な臥床交換が必要
長期間の臥床によるリスクを防ぐには、定期的に体の向きや体勢を変える臥床交換が効果的です。介護職員が一方的に臥床交換をするだけでなく、要介護者にも可能な範囲で積極的に自分で体を動かしてもらうことで、寝たきりになることを防ぐ効果が期待できます。
長期臥床を予防するためにできること
寝たきりの状態が続く長期臥床は、要介護者だけでなく介護職員にとっても大きな負担となります。ここでは、長期臥床を防ぐための効果的な方法について解説します。
要介護者本人も、長期にわたってベッドで過ごすことは避けたいと考えています。そこで、「長期臥床を予防するため」という目的をしっかり伝え、ご本人にできる範囲での協力をお願いしましょう。本人の理解と協力が、自立支援と身体機能の維持につながります。
できるだけ座る時間をつくる
寝ている状態を1週間続けると、筋力や骨量が低下するといわれています。そのほかにも、関節が固くなったり、心肺機能が低下したり、かむ力や飲み込む力が低下したりすることが判明しています。
座ることで、このような機能の低下だけでなく、床ずれも防げるため、横になるよりも座る時間をつくることが大切です。
バランスのよい食事を心がける
介護が必要な高齢者は、栄養不足に陥りやすい傾向があります。低栄養状態になると免疫力が低下し、感染症にかかるリスクが高まるため、適切な栄養管理が重要です。
栄養は必要ですが、だからといって高血圧や肥満になってしまうような食事は避けなければなりません。バランスのよい食事を心がけましょう。
かむ力を保つための工夫をする
かむ動作は脳を活性化させる働きがあり、記憶力の衰えを防ぐ上で非常に重要です。かむことによって脳への血流が促され、認知機能の維持や認知症予防にもつながると考えられています。
そのため、食事の際にはしっかりとかむことを意識し、硬さや食感の異なる食品を取り入れるなど、かむ力を鍛える工夫を日常生活に取り入れることが大切です。例えば、かみごたえのある食材を選んだり、食事中にゆっくり時間をかけて咀嚼してもらったりすることを心がけましょう。
さらに、かむ力を保つことで口腔内の筋肉が衰えるのを防ぎ、誤嚥(ごえん)を防止する効果も期待できます。これらの取り組みは、健康的な生活を維持し、心身の活力を保つためにも欠かせません。
口腔内を清潔に保つ
口腔内を清潔に保つことは、誤嚥性肺炎をはじめとするさまざまな感染症や病気の予防に大きく役立ちます。これにより、結果的に長期臥床のリスクを減らすことが期待できます。
また、口腔ケアは単に清潔を保つだけでなく、かむ力を維持する上でも非常に重要です。口腔内の筋肉や組織の健康を保つことで、かむ機能を支え、食事を安全にとることができるようになります。
そのため、毎日の口腔ケアを丁寧に行い、口の中を清潔に保つことを習慣にしましょう。介護を受ける方も介護する方も、口腔ケアの重要性を理解し、継続的に取り組むことが健康維持につながります。
まとめ
介護現場でよく使われる「臥床介助」について、その意味や種類、離床との違いなどを解説しました。
臥床は、単に「寝る」という行為にとどまらず、介護の現場では身体的な負担や安全性を意識して行う重要な介助の一つです。寝たきりによるリスクを防ぐためにも、臥床に関する正しい知識は欠かせません。
これから介護の仕事を始めようと考えている方にとって、臥床や臥床介助は日常的に起こる場面の一つであり、基本的な知識として身に付けておきたい内容です。
また、介護の現場だけでなく、ご自宅でご家族の介護をしている方にとっても、床ずれの予防や寝たきりの進行を防ぐ上で、大いに役立つ情報といえるでしょう。