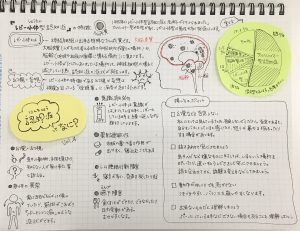介護施設の費用はどのくらい?費用相場や選ぶポイント、負担を減らす方法を解説!

高齢化が進む現代において、介護施設や老人ホームの利用を検討するご家庭が増えています。
しかし、いざ選ぼうとすると「費用はどれくらいかかるのか」「どの施設を選べばいいのか」など、さまざまな疑問や不安が生じるのではないでしょうか。
本記事では、介護施設や老人ホームの費用相場や選ぶ際のポイントに加え、介護費用の負担を減らすための方法などを解説します。
ご自身やご家族の状況に合った最適な施設選びの参考にしていただければ幸いです。
老人ホームや介護施設に必要な費用
まずは、老人ホームや介護施設に必要な費用について詳しく解説します。
入居時費用
有料老人ホームを中心とした一部の施設では、入居時に「入居一時金」や「初期費用」と呼ばれるまとまった金額の支払いが求められることがあります。
これは、一定期間の居住費やサービス費を前払いする仕組みです。
施設によっては月額利用料を抑える代わりに高額の入居金を設定している場合もあります。
支払った入居金は償却方式で少しずつ月額費用に充当され、途中退去時の返金ルールも事前に定められています。
入居金の金額には幅があり、施設によって大きく異なります。
中には、入居金が不要なプランを選べる施設もありますが、その分、月額費用が高く設定されているケースが一般的です。
そのため、選ぶ際は入居金と月額費用を合わせた「総額」で比較することが重要です。
月額費用
老人ホームや介護施設には、以下のような月額費用も必要です。
- 家賃(居住費)
- 食費
- 管理費・共益費
- 介護サービス費(介護保険適用)
- 上乗せ介護サービス費(自由契約)
- 医療費・薬代(実費)
- その他実費費用 など
それぞれ詳しく見ていきましょう。
家賃(居住費)
介護施設における家賃は、施設の種類や運営形態によって大きく異なります。
公的施設では、国の定める「基準費用額」に基づいて日額が設定されており、多床室は比較的安価で、ユニット型個室はやや高めの傾向があります。
一方、民間施設では、立地や設備、部屋の広さ、築年数などにより価格に幅があります。
特に民間運営の施設では、一般的な賃貸住宅と同様に、さまざまな条件によって家賃が変動すると考えておくとよいでしょう。
費用は施設によって大きく異なるため、ライフスタイルや予算に応じて無理のない選択を心がけることが大切です。
食費
介護施設での食費は、施設形態に応じて負担額や計算方法が異なります。
公的施設の場合、食費も国の基準に基づいて定額化されており、原則として1日あたり約1,445円を目安とした費用が必要です。
事情により食事をとらなかった日でも一定の費用がかかる場合があります。
一方で民間施設では、提供スタイルや食材の質、サービス内容によって費用に幅があります。
中には、アレルギー対応や刻み食などの個別対応に応じている施設もあるため、事前の確認が重要です。
食費も入居後の生活に直結する要素の一つなので、無理のない範囲で希望に合う内容を選ぶことが大切です。
参照:厚生労働省「サービスにかかる利用料」
管理費・共益費
管理費や共益費は、施設の運営や維持に必要な費用で、共用スペースの清掃・修繕、水道光熱費、スタッフの人件費、レクリエーションの実施費用などが含まれます。
公的施設でも一定額が発生しますが、比較的抑えられた設定になっています。
一方で、民間施設では、サービス内容やサポート体制によって費用に差があるのが一般的です。
中には、管理費に食費や洗濯代などを含めて一括請求する施設もあるため、契約前に費用の内訳やサービス内容をしっかり確認することが大切です。
介護サービス費(介護保険適用)
入居者が受ける介護サービスには、介護保険が適用される基本的な支援と、施設ごとのサービス加算があります。
加算とは、施設がより手厚いサービスを提供するために加えられる費用です。
例えば、夜間も看護師が常駐している場合や、機能訓練が充実している施設などでは加算が上乗せされます。
これらの費用は1~3割の自己負担となり、サービスの質が高い施設ほど金額も上がる傾向があります。
サービスがニーズと合っているか、加算の内容と金額のバランスが適正かどうかを見極めて選ぶことが重要です。
参照:厚生労働省「サービスにかかる利用料」
上乗せ介護サービス費(自由契約)
上乗せ介護費は、介護保険の対象外となる「自由契約サービス」に対する費用で、手厚いケアや追加オプションを希望する際に発生します。
例えば、基準以上の人員配置や、認知症ケア専門スタッフの常駐、個別リハビリの実施、リネン交換や買い物代行などが対象です。
これらは施設の独自サービスとして設定されているため、利用するかどうかは任意です。
安心や快適さを重視する方にとっては魅力的ですが、その分コストがかかる点を理解しておく必要があります。
契約内容や料金体系は施設ごとに異なるため、事前の説明を丁寧に確認しましょう。
医療費・薬代(実費)
医療費や薬代については、介護保険ではカバーされないため、通常どおりの健康保険適用の自己負担が発生します。
持病がある方や、通院・服薬が定期的に必要な方は、医療機関への受診料、処方箋薬の費用などが毎月の支出に加わります。
また、通院の際に施設スタッフの付き添いが必要な場合は、その分の人件費が別途請求されることも少なくありません。
一部の施設では送迎や付き添いサービスが無料の場合もあるため、医療ニーズが高い方は、サービス内容と費用の有無をあらかじめ確認することが大切です。
その他実費費用
介護施設では、日常生活にかかる細かな出費も自己負担となります。
例えば、石鹸やシャンプー、歯ブラシなどの衛生用品や、新聞、雑誌、お菓子などの嗜好品、衣類や靴の購入費、理美容サービスの利用料などがあります。
また、外部講師による特別イベントや外出レクリエーションなどに参加する際には、材料費や参加費が発生することも少なくありません。
こうした費用は施設によって取り扱いや価格設定が異なるため、入居前に案内資料などで詳細を確認し、想定外の出費が出ないよう備えておくと安心です。
老人ホーム・介護施設の種類別介護費用の相場
老人ホームや介護施設の費用は、施設の種類によって大きく異なります。
ここでは、公的施設と民間施設に分けて、代表的な施設ごとの費用相場を分かりやすく紹介します。
公的施設
公的施設は、自治体や国などの公的機関が主体となって運営する施設で、比較的費用が安く設定されている点が大きな特徴です。
公的施設には、主に以下の4つが挙げられます。
- ケアハウス
- 介護老人保健施設
- 介護医療院(介護療養型医療施設)
- 特別養護老人ホーム
それぞれ詳しく見ていきましょう。
【ケアハウス】
ケアハウスには、大きく分けて「自立型(一般型)」と「介護型(特定施設入居者生活介護)」の2種類があります。
ケアハウスは、比較的軽度の要介護者や自立に近い高齢者を対象とした施設です。
食事や見守り、日常生活支援が中心のサービスが提供されます。
主に60歳以上が対象で、生活に不安を感じる単身者や夫婦での入居にも対応しているケースがあります。
介護保険が適用される場合とされない場合があり、介護が必要になったときには外部サービスを併用するのが一般的です。
月額費用は一般型で約6万~十数万円、介護型で約6万~20万円程度ほどが目安とされており、比較的負担の少ない料金で安心した生活を送れる施設の一つになります。
それぞれ、入居条件や受けられるサービス内容が異なるため、自分の状態や今後の介護の必要度に応じて選ぶことが大切です。
【介護老人保健施設】
介護老人保健施設は、在宅復帰を目指すための中間的な施設です。
主に病院での治療を終えた高齢者がリハビリを受けながら生活する場として利用されます。
医師や看護師、リハビリスタッフが在籍しているため、医療的なケアが必要な方にも対応可能です。
ただし、あくまで一時的な滞在を前提としており、原則3カ月程度の利用が想定されています。
費用は介護保険の適用を受けて月額約9万~20万円程度が一般的です。
医療依存度が高い方にとって、短期間の集中的なケアを受ける場として有効な施設になります。
【介護医療院(介護療養型医療施設)】
介護医療院は、慢性的な疾患や重度の要介護状態にある高齢者を長期的に受け入れる医療と介護の両方を提供する施設です。
医療ケアが常時必要で、かつ自宅での生活が困難な方にとって、入院に近い環境で安心して療養できます。
病床数が限られており、医師や看護師が常駐するなど医療体制が整っている反面、施設数は少なく、地域によっては選択肢が限られることもあります。
月額費用は約10万~20万円程度が目安です。
【特別養護老人ホーム】
特別養護老人ホームは、要介護3以上の高齢者を対象に、長期的な介護と生活支援を行う公的施設です。
入所一時金が不要なことが多く、月額費用も比較的抑えられており、月7万~15万円程度で利用できることから非常に人気があります。
そのため、入所希望者が多く、数年単位の待機が発生することも珍しくありません。
また、要介護度が低下した場合は退居を求められるケースもあるため、継続利用には条件を満たし続ける必要があります。
民間施設
民間施設は、民間企業や医療法人、社会福祉法人などが運営しており、サービスの内容や設備に大きな幅があります。
民間施設には、主に以下の4つが挙げられます。
- グループホーム
- 住宅型有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
- 介護付き有料老人ホーム
それぞれ詳しく見ていきましょう。
【グループホーム】
グループホームは、認知症の診断を受けた高齢者を対象にした、少人数のグループで共同生活を送る施設です。
家庭的な雰囲気の中で、スタッフの支援を受けながら調理や掃除などの生活行為を行い、認知機能の維持を目指します。
1ユニットあたり5~9人程度の小規模運営が一般的で、地域密着型サービスとして展開されています。
費用は地域や運営主体により異なりますが、月額約15万~30万円程度が目安です。
認知症の進行を穏やかにしながら、穏やかな日常生活を送りたい方に適しています。
【住宅型有料老人ホーム】
住宅型有料老人ホームは、主に自立や要支援、軽度の要介護状態にある高齢者向けの施設で、居住と生活支援サービスがセットになっています。
介護サービスは外部の事業所と契約して受ける形が多く、比較的自由な生活スタイルを維持しやすい点が特徴です。
月額費用は約12万~30万円程度と幅があり、施設の立地や設備によって大きく変動します。
入居時の初期費用が発生する場合もありますが、入居金ゼロのプランも存在します。
自由度とコストのバランスを取りたい方に向いているでしょう。
【サービス付き高齢者向け住宅】
サービス付き高齢者向け住宅は、高齢者専用の賃貸住宅に安否確認や生活相談などのサービスが付いた住まいです。
要介護度が低い方や、まだ自立した生活を送りたい高齢者が、見守りを受けながら安心して暮らせます。
介護サービスは外部事業者によって提供されるため、必要に応じて自由に利用できる点も魅力です。
家賃・管理費・共益費・食費などを含めて、月額約10万~30万円ほどが相場です。
バリアフリー設計や緊急通報システムなど、安全面への配慮も整っています。
【介護付き有料老人ホーム】
介護付き有料老人ホームは、施設のスタッフが介護サービスを一括して提供する体制が整った施設です。
要介護度の高い方でも安心して生活できます。
日常生活の支援から、医療ケア、機能訓練までトータルな支援が受けられるため、家族にとっても負担が少なくなります。
その分、費用は高額になりがちで、月額約15~30万円以上になることがあります。
介護施設や老人ホームを選ぶポイント
介護施設や老人ホームを選ぶ際は、サービスの内容や環境が本人に合っているかを見極めることが重要です。
ここでは介護施設や老人ホームの選定時に押さえておきたいポイントを詳しく解説します。
必ず見学する
パンフレットやインターネットでは分からない施設の空気や生活の様子を把握するには、現地見学が欠かせません。
実際に訪れることで、入居者の表情や職員の雰囲気、清潔感などを確認できます。
可能であれば入居希望者本人と一緒に見学することで、「ここでなら過ごせそう」という安心感が得られやすくなります。
スタッフの対応を確認する
入居後の安心・安全な生活は、スタッフの質に大きく左右されます。
介護技術だけでなく、認知症ケアや高齢者との関わり方に関する理解があるかを見極めましょう。
実際の対応を見たい場合は、職員と入居者の会話の様子や表情に注目してみるとよいです。
また、スタッフの人数配置や夜間体制、急な体調不良時の対応体制なども確認しておくと安心です。
家族としても信頼できるスタッフがいるかどうかは、長く付き合う上で非常に重要な判断材料となります。
想定している1日のスケジュールで過ごせるか
施設ごとに生活の時間割が異なるため、本人の生活リズムに無理なくフィットするかを事前に確認しておくことが大切です。
例えば、朝早くからの活動が苦手な方には、ゆったりとしたスケジュールの施設が向いています。
逆に、日中の活動量を重視したい方には、アクティビティが充実している施設が適しています。
見学時には、1日の流れを説明してもらい、本人が心地よく過ごせそうかどうか、細かいところまで目を配るようにしましょう。
食事内容も確認する
食事は施設生活の楽しみの一つで、満足度に直結します。
事前にどのような食事なのか、試食が可能かどうかを確認し、味や食べやすさ、見た目の工夫などをチェックしましょう。
また、嚥下機能が弱い方にはミキサー食や刻み食などの対応があるか、持病がある方には減塩・糖質制限など個別対応ができるかも重要です。
毎日のことだからこそ、自分に合った食事が取れるかどうかを見極めることが、生活の満足度を大きく左右します。
体験で入居してみる
可能であれば、入居前に体験入居を行うことをおすすめします。
実際に1日または数日を施設内で過ごしてみることで、パンフレットや見学だけでは見えない生活感を体感できます。
食事や職員の対応、ほかの入居者との関係性、夜間の過ごし方など、具体的な生活の流れが把握できるため、ミスマッチを防ぐ上でも効果的です。
施設によっては希望日の調整が必要なこともあるため、検討段階で早めに問い合わせておくとスムーズになります。
介護費用の負担を減らす方法
介護施設や老人ホームの利用には、入居費や月額費用など多くの負担が発生しますが、制度を上手に活用することで経済的な負担を減らせます。
ここでは、介護費用の負担を減らす方法をいくつか紹介します。
医療費控除などを活用する
医療費控除とは、一定額以上の医療費を支払った場合に、確定申告を通じて所得から控除を受けられる制度です。
介護施設における医療関連の支出も対象となるケースがあります。
特に特別養護老人ホームや介護老人保健施設では、食費や居住費の一部、さらにはおむつ代などが控除対象です。
家族の支払い分も合算可能なため、確定申告の際には領収書をしっかり保管し、必要な項目を漏れなく申請しましょう。
参照:国税庁「医療費を支払ったとき(医療費控除)」
高額サービス費支給制度を利用する
介護保険を利用して受けたサービスの自己負担額が一定の上限を超えた場合に、超過分が払い戻される制度があります。
これが「高額介護サービス費支給制度」です。
この制度では、本人や世帯の所得に応じて自己負担の上限額が決められており、月ごとの介護費用の負担を軽減する効果があります。
特に所得が低めの世帯では、比較的低い上限額が設定されているため、経済的な負担を抑えやすくなっています。
制度の利用には申請が必要となる場合もあるため、心当たりがある方は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口に相談してみましょう。
参照:国税庁「高額介護(居宅支援)サービス費 」
特例減額措置を受ける
収入や資産が一定以下の高齢者が介護保険施設を利用する場合、居住費や食費が減らせる「特例減額措置」が用意されています。
この制度を利用するには、市区町村から発行される「介護保険負担限度額認定証」が必要です。
この証明書があれば、介護施設での生活費のうち、基準を超える部分が免除・減額され、月々の負担が減ります。
介護が長期にわたる可能性がある方は、早い段階でこの制度について確認し、対象となるか調べておくと安心です。
参照:厚生労働省「特例減税措置」
利用者負担軽減措置を受ける
経済的な理由で介護施設の利用が難しい場合には、社会福祉法人の利用者負担軽減制度を検討するのも一つの方法です。
これは、一定の所得条件を満たした利用者に対し、介護費用の自己負担額を軽減できる制度です。
対象となる施設は限られているため、事前に自治体の福祉課などに相談し、制度の申請方法や対象施設を確認することが必要です。
市区町村や自治体のサポートを受ける
地域によっては、介護費用の負担を軽減するための独自の支援制度が設けられています。
例えば、家族慰労金制度では、一定期間介護サービスを利用せず在宅介護を続けた家族に対し、年間10万円が支給されます。
また、介護保険利用者負担助成制度では、介護保険の自己負担割合が1割からさらに減額が可能です。
これらの制度は市区町村によって異なるため、役所の福祉担当窓口に確認することで、受けられる支援を逃さず活用できます。
まとめ
本記事では、介護施設や老人ホームの費用相場や選ぶ際のポイントに加え、介護費用の負担を減らすための方法などを解説しました。
介護施設を利用するためには、入居時費用や月額費用などがかかります。
しかし、医療費控除や高額サービス費支給制度、特別減額措置など、公的な支援制度を活用することで費用負担を大きく減らすことが可能です。
また、自治体ごとの助成制度や、社会福祉法人による負担軽減制度なども見逃せません。
この記事を参考に事前に制度内容を確認し、自分や家族の状況に合った支援を上手に利用するとよいでしょう。