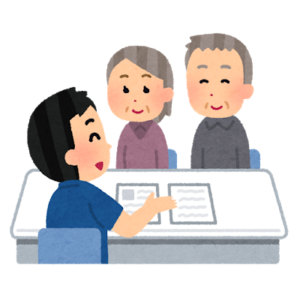一人暮らしの高齢者に潜むリスクとは?早めに知っておきたい支援や対策

一人暮らしの高齢者は年々増加しており、孤独死や社会的孤立、犯罪被害などさまざまなリスクが潜んでいます。
こうしたリスクを事前に知り適切な対策をとることで、高齢者本人はもちろん家族にとっても大きな安心につながります。
本記事では、一人暮らしの高齢者が抱えるリスクとその対策、さらに一人暮らしが困難な可能性がある高齢者を見極めるチェックポイントまで詳しく解説します。
家族の安全を考える方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
増加していく一人暮らしの高齢者の実態
高齢社会の進展に伴い、配偶者との死別や子どもの独立によって、独居となる高齢者は増加の一途をたどっています。
日本の高齢者世帯の実態について、厚生労働省のデータをもとに見ていきましょう。
一人暮らしの高齢者の割合
日本では65歳以上の高齢者の独居世帯は、2020年の時点で男性約231万人、女性約441万人、計約671万人にものぼります。
専門家によると、2040年には約896万人にも達することが予想されており、これは高齢者人口の約4割にも及ぶ数字です。
その背景に影響しているのは、核家族化や「子どもに迷惑をかけたくない」という思いであると見られています。
参照:総務省「一人暮らしの高齢者に対する見守り活動に関する調査 結果報告書」
健康寿命との関係と一人暮らしへの影響
厚生労働省の資料によると、2022年時点での日本人の健康寿命は、男性が72.57歳、女性は75.45歳となっています。
健康寿命とは「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」を示したものです。
一方で平均寿命は男性で81.05歳、女性で87.09歳となっており、健康寿命とは10年ほどの開きがあります。
高齢になると、ケガや疾患、特に認知症の発症リスクが高まり、自立した生活が困難になるケースが多く見られるため、これによって健康寿命との差が生まれているのでしょう。
参照:厚生労働省「健康寿命の令和4年値について」
家族と同居したくない理由は?
身の回りの世話が必要になっても家族との同居を拒む方は多く、「子どもに迷惑をかけたくない」「新しい生活に抵抗がある」といったことから、独居を続けている方も多いことでしょう。
内閣府の平成27年度版高齢社会白書によると、一人暮らしの高齢者に対するアンケートで、現在の生活の満足度は10点満点のうち何点かという問いに対し、7点以上と答えた人の割合は49.2%とほぼ半数を占めていました。
誰かに縛られることなく、自由気ままな生活が満足度につながっていることと考えられます。
しかし、高齢者の一人暮らしには、大きなリスクが潜んでいることを忘れてはいけません。
参照:内閣府「令和7年度版高齢社会白書 概要版」
一人暮らしの高齢者が抱える9つのリスク
昔と比べて地域とのつながりが希薄化している日本において、一人暮らしの高齢者には、困った時に頼れる人が少なくなっています。
そのため、本人も気づかない内に複数の危険要因を抱えていることも珍しくありません。
一人暮らしの高齢者にはどのようなリスクがあるのか、解説します。
社会的孤立
地域とのつながりが密であれば、体調の変化や健康状態の悪化にいち早く気づき、迅速な対処がなされていたこともありました。
しかし現代では、知らない人同士の交流が薄れ、外出などの機会の少ない高齢者は社会的に孤立している状況があります。
言葉を交わす相手がいないことで、生きがいを感じられなくなり、困ったときに手助けしてくれる人もいないことから、老後の生活に不安を感じやすくなることでしょう。
また、会話をしないことで脳の機能が低下し、認知症を発症したり、症状の進行を早めたりしてしまうおそれもあります。
経済的な不安
一人暮らしでは経済的なリスクも高くなります。
総務省統計局が公表している家計調査報告(家計収支編)2024年平均結果の概要によると、65歳以上の単身無職世帯(高齢単身無職世帯)の実収入は13万4,116円でした。
そのうち可処分所得は12万1,469円であるのに対して、消費支出は14万9,286円と、支出が3万円ほど多いことが分かります。
貯金を切り崩そうにも、何歳まで生きられるか分からないことが、経済的な不安を一層強めてしまうことでしょう。
しかしながら、食事を切り詰めたり、エアコンの電気代や病院代を節約したりすると、健康を害するだけでなく、命にも関わるリスクにもなります。
参照:総務省統計局「 〔 家計収支編 〕 2024年(令和6年)平均結果の概要」
食生活の偏り
一人だけの食事であれば自炊では効率が悪くなるため、コンビニなどで簡単に済ませたり、好きなものばかり食べてしまったりすることも多くなります。
また、高齢になると食が細くなり、経済的な不安から食べ物を減らしてしまうことも問題です。
必要な栄養素の確保が困難になり、健康被害や持病の悪化を招き、健康寿命にも影響することでしょう。
生きがいの喪失
家族との交流や社会的なつながりが減少すると、日々の生活にも張り合いを感じにくくなり、生きがいを失ってしまうことがあります。
高齢期は趣味や役割を持つ機会が減少し、「自分は誰の役にも立っていない」といった喪失感や無力感から、うつ状態に陥るケースも少なくありません。
生きがいを見失うことは、心身に多大な影響を与える原因にもなり得ます。
身の回りのことに手が回らず、生活環境が乱れる
年を重ねると、多かれ少なかれ身体機能の低下を引き起こし、これまでできていた家事も難しくなります。
特に肩、腰、膝などの関節に痛みがあれば、庭の手入れやゴミの撤去といったハウスキーピングが負担に感じることでしょう。
認知症から、片付けの段取りが分からなくなったりすると、家はたちまち不衛生になり、見た目が悪いだけでなく健康にも悪影響です。
病気やケガの対応が遅れ、重症化する
高齢者は小さな傷でも治りにくく、適切な治療を施さないと化膿したり、最悪の場合壊死したりすることもあります。
また、軽い風邪からでも肺炎を引き起こし、重症化や慢性化を起こしやすいため、注意しなければなりません。
隠れ認知とも呼ばれる状態では普段は症状が表面化しないため、治療が遅れ、病状が一気に進んでしまうこともあります。
一人暮らしでは、このようなケガや疾患に対して適切な対処が行えず、のちのち重篤な状態で発見されることも少なくないため注意が必要です。
災害時に避難できない
2011年の東日本大震災では死者・行方不明者の半分以上が65歳以上の高齢者でした。
災害が発生したときに、近隣住民とのつながりが希薄であると、いざというときにも周囲の助けを得られず、逃げ遅れてしまうことが考えられます。
特に一人暮らしの高齢者の場合、災害情報や避難場所の認知度が低く、足腰が弱っているせいもあって迅速な対応は困難です。
また、住み慣れた自宅から離れることに抵抗を感じ、避難行動が遅れることで命に関わる事態にもなり得ます。
参照:国土交通省「災害時・緊急時に対応した避難経路等のバリアフリー化と情報提供のあり方に関する調査研究 報告書概要版」
詐欺などの犯罪に巻き込まれるリスクの増加
振り込め詐欺やオレオレ詐欺といった特殊詐欺のうち、65歳以上における被害の認知件数は1万3,707件で、法人被害を除いた総認知件数に占める割合は65.4%にも上ります。
一人暮らしの高齢者は、普段から頼れる人が少ないことから、初対面でも親身になって話を聞いてくれる人を信用しやすい傾向があります。
金融に関する知識の不足や、契約内容を正確に理解することの難しさも詐欺に遭いやすい要因の一つでしょう。
また、鍵をかけ忘れるなど防犯対策が不十分なために、空き巣や強盗にも狙われやすく注意が必要です。
参照:内閣府「令和7年度版高齢社会白書 全体版」
孤独死
警察庁の発表によると、2024年に自宅で孤独死しているのを発見したケースは全国で7万6,020件でした。
都会であるほど孤独死は多く、特に東京では年間1万件以上の孤独死が発見されており、社会的孤立が孤独死の要因となっていることは明白です。
孤独死の約6割が病死で、病気やケガの対応が遅れたり、適切な治療が施されなかったりすることから亡くなってしまうケースは後を絶ちません。
1日でも死後の肉体は腐敗が進み、悪臭や害虫の発生が見られます。
遺族は遺体の処理、遺品の整理、ゴミ出しなどを行い、場合によっては特殊清掃業者への依頼も必要です。
賃貸物件の場合、家主や近隣住民に精神的な負担を与えるとともに、状態によっては床材の張替えやリフォーム代も必要になり、さらに出費がかさむことにもなります。
参照:警察庁「令和6年中における警察取扱死体のうち、自宅において死亡した一人暮らしの者について」
一人暮らしが困難かもしれない高齢者のサイン
高齢者は知らず知らずのうちに認知症を発症していることもあり、本人はうまくできていると思っていても、実際には危ない場面に遭遇していたということもあります。
他者との交流が少なくなると、誰にも気づかれずに症状が悪化し、火事などの大きな問題に発展してしまうかもしれません。
いくつかのチェックポイントを知っておき、家族や近隣の高齢者にあてはまる特徴がないか確認してみましょう。
健康状態
認知症や日常生活による影響で、本人に健康上の問題が生じていることがあります。
以下のチェックポイントを参考にしてみましょう。
- 以前より急激に痩せている、または太ってきているか
- 立ち上がりに時間を要していないか
- 尿臭や体臭が強くなっていないか
- 視力や聴力に異常はないか
- 体に内出血などの外傷はないか
- 元気があるか、うつろな表情をしていないか
- 食べたこと自体を忘れていないか
これらが複数当てはまる方は、場合によっては認知症を含む健康状態に問題があるため、医療機関の受診が推奨されます。
生活環境
生活環境を観察することで、認知症が発症している可能性をつかむことができます。
以下の項目を確認してみましょう。
- コンロの火の消し忘れはないか、鍋やフライパンが焦げついてないか
- 冷蔵庫に期限切れやカビが生えた食品はないか
- 財布の中が小銭だらけになっていないか(計算ができないために、小銭を使って支払うことができなくなっている)
- 同じ商品をいくつも買っていないか(買ったことを忘れて、再び買ってしまっている)
- カレンダーは最新月になっているか
- 布団や衣類は季節に合ったものになっているか
- 飲み忘れた内服薬が残っていないか
- 未払の請求書や郵便物、新聞、ゴミなどがたまっていないか
- 車が傷ついていないか
本人も気づかないうちに、認知症が進行している場合があります。
チェック項目が複数当てはまる場合は、医療機関の受診とともに、今後の対策を考えることが必要です。
一人暮らしの高齢者の生活を支える9つの支援や対策
一人暮らしの高齢者が可能な限り安心して暮らしていくためには、高齢者特有のさまざまなリスクに対して周囲の支援や対策が不可欠です。
安全で安心な生活のために、行政や自治体、民間によるサービスを有効に活用していくことが望まれます。
1.行政や自治体による生活支援
厚生労働省では、医療や介護、住まい、介護予防、生活支援を包括的に提供する「地域包括ケアシステム」の推進が行われています。
地域包括ケアシステムとは、住み慣れた地域でその方らしく最期まで暮らし続けられるように、地域が主体となって高齢者を支援する仕組みです。
具体的には、地域包括支援センターが高齢者の相談に乗り、必要に応じて介護や医療サービスへの連携や、地域の見守り活動による安否確認サービスなどが行われます。
2.民間の訪問型・電話型見守りサービス
自治体が行っている見守りサービス以外にも、民間による見守りサービスが行われています。
警備会社などが行っているサービスには、職員が訪問して安否確認を行うものや、定期的に電話で安否を確認するものがあり、一人ひとりの求めるサービス展開がされています。
価格は月額制で数百円程度と、決して高額ではありません。
ほかには、高齢者の自宅内に人感センサーを設置し、一定期間動きがなければ異変として家族や介護事業者などに通知が届くシステムもあります。
家族が遠方で毎日来られないという場合でも、アプリなどによって離れた家族の様子を確認できるため安心です。
3.家族との連絡や緊急連絡手段の確保
老親が離れて住んでいる場合、社会的な孤立を防ぐために定期的に電話をかけたり、休日に様子を見に行ったりすることはとても重要です。
ちょっとした体調の変化や、認知症の兆しに気づく機会が多くなり、すぐに医療機関につなげることができます。
また、関係性の薄い遠縁の高齢者には、自宅に緊急連絡用のボタンを設置し、何かあればすぐに押して対処できるようにしておくのもよいでしょう。
最近ではセンサー型の家電もあり、一定期間使用されていないと家族へ連絡が入るものもあります。
家族に迷惑をかけたくなくて、緊急ボタンを押すのに抵抗がある方にもおすすめです。
4.孤立防止のためのコミュニティ参加・地域交流
一人暮らしの高齢者を対象とした調査で、生きがいを感じているかという問いに対し、あまり感じていない・まったく感じていない人の割合は、コミュニティの参加や地域での交流がある人と、そうでない人とでは2.7倍もの差がつきました。
また、コミュニティの活動で、さまざまな人とコミュニケーションをとる機会があれば、脳に適度な刺激が加わり、認知症の発生や進行を遅らせることが分かってきています。
自治体が主体となって行われている高齢者サロンやクラブ活動はうってつけともいえるでしょう。
社会活動を通して、社会的孤立を防止し、生きがいを創出することが健康寿命を延ばす上でも大切になります。
参照:内閣府「令和7年度版高齢社会白書 全体版」
5.生活環境の整備
高齢になると、ちょっとした段差でつまずいたり、入浴中に足を滑らせて転倒したりすることが多くなります。
一人暮らしの高齢者の生活環境を見直し、段差の解消や手すりの設置、動線の確保などを行うことは、転倒や転落といったリスクの軽減に効果的です。
要介護認定を受けていれば、要支援1であっても住宅改修費に介護保険を利用できます。
上限を20万円とし、本人の所得によって住宅改修費の7~9割を介護保険で賄うことが可能です。
また、普段から定期的に家族が訪問し、室内の整理整頓を行うことも、物に足がひっかかって転倒することを防げます。
遠くに住んでいてなかなか来られない場合も、介護保険制度の居宅サービスを利用すれば、生活援助による掃除やゴミ出しをヘルパーに依頼することが可能です。
6.医療体制の強化
高齢者は、さまざまな理由から急に体調を崩したり、通院や内服を忘れたりすることがあるため、医療機関との連携は必須です。
健康状態がよいと生きがいを感じやすいというデータもあり、生活の質と医療体制は密接につながっています。
信頼できるかかりつけ医や薬局を決めておくと、治療だけでなく、日々の生活についても指示や助言を得やすくなります。
大きな病院である必要はなく、定期的な通院が容易な地域の診療所・クリニックでも十分です。
内服を忘れたり、間違えたりするリスクがある場合は、薬局に相談し、内服薬の一包化や内服カレンダー、薬ケースなどを利用して間違えにくくする対策も有効になります。
7.介護予防のための運動・食事管理
高齢者は食が細くなりやすく、運動量も若いときに比べて大きく下がります。
食事量の減少や運動量の低下によって、筋肉量や身体機能が衰えることで、さまざまな疾患が発症しやすくなります。
健康寿命を延ばしていくためには、十分な栄養と定期的な運動が欠かせません。
地域で行われている運動や体操のクラブに参加したり、栄養バランスのとれた食事を配達してくれる配食サービスなどを活用したりすることもおすすめです。
8.介護サービス・介護保険による支援
掃除や洗濯といった家事が一人では難しくなってきたと感じたら、地域包括支援センターに相談してみましょう。
生活上の改善策や配食などの地域で実施されているサービスを知ることや、必要に応じて要介護度の認定調査を依頼することができます。
介護度が要支援でも生活援助の依頼や、介護予防デイサービスで他者との交流の機会を創出することが可能です。
要介護認定を行ったからといって、自宅での生活ができないというわけではありません。
むしろ、家に閉じこもって不健康な生活を送るほうが、かえって一人暮らしを困難にしてしまうことにもつながります。
安全で安心できる生活のために必要な支援を利用することは、地域での生活をより長く保つための手段の一つです。
9.詐欺・犯罪に遭わないための防犯対策
高齢者は犯罪の標的になりやすいため、日頃から備えをしておくことが必要になります。
防犯カメラや防犯ブザーの設置も、有効な対策です。
玄関の施錠はもちろん窓も侵入経路の一つですので、防犯フィルムを貼っておき、ガラスが割られないようにしておくとよいでしょう。
地域住民とも普段からコミュニケーションをとって、なにかあれば助けを求められるようにしておくことも大切です。
また、将来的な判断力の低下に備え、任意後見制度を利用しておくと、財産管理や身の回りの世話を依頼することができます。
悪質な契約を結んでしまった場合でも、後から無効にすることが可能です。
一人暮らしの高齢者におすすめの施設サービス
一人暮らしが難しくなった場合に備え、どのような施設サービスがあるか知っておくことはとても大切です。
昔のような老人ホームとは異なり、単独外出も認められる自由度の高い施設も多数あります。
体調の変化があれば、すぐに対応してくれる人が近くにいることは、本人にとっても安心感につながることでしょう。
一人ひとりのニーズや経済状況に合わせて選ぶことも重要です。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
サービス付き高齢者向け住宅とは、60歳以上で介護度が低い、または自立している方が、安否確認と生活相談サービスを受けながら生活できる賃貸住宅です。
建物内はバリアフリーで、見守りサービスや栄養バランスのとれた食事のサービスを受けながら、お一人おひとりのライフスタイルを自由にデザインできることが大きな魅力となります。
医療機関やデイサービスが併設されているものもあり、価格帯もさまざまです。
介護サービスが必要な場合は、外部のサービスや併設の訪問事業所との契約が必要になります。
住宅型有料老人ホーム
住宅型有料老人ホームは、60歳以上の比較的介護度の軽い方を主な対象としている賃貸型の住宅です。
レクリエーションが充実しており、生活援助以外でも体操やカラオケ、季節ごとの催しなどが行われ、他者との交流の機会も確保できます 。
介護サービスが必要な場合は、外部の事業所や併設の訪問事業所を利用します。
施設にもよりますが、将来的に介護度が重くなっても、終身の利用が可能です。
介護付き有料老人ホーム
介護付き有料老人ホームは、介護保険上の「特定施設入所者生活介護」の指定を受けている特定施設です。
要介護1以上でなければ入居できない介護専用型と、要支援1でも入居可能な混合型があります。
介護サービスは施設のサービスとして提供され、基本的に外部のサービスを利用することはありません。
日中は看護師も常駐しており、医療依存度の高い方でも入居が可能です。
シニア向け分譲マンション
シニア向け分譲マンションは、主に60歳以上の自立した生活が可能な高齢者が対象となります。
バリアフリー設計で、プールや温泉、スポーツジム、カラオケルームなどの娯楽設備を兼ね備えているものが一般的です。
緊急連絡システムが居室やトイレ、浴室に設置されており、万が一のときにも安心できます。
要支援、または要介護認定の方でも入居は可能ですが、介護サービスは外部の事業所との契約が必要です。
賃貸とは異なり所有権の購入となるため、不動産と同様、売却や他人への譲渡、相続が可能で、死後は資産としても利用できます。
費用は数千万円から数億円と幅が広いのも特徴です。
まとめ
一人暮らしの高齢者は、社会的孤立や経済的不安、健康リスクなどさまざまに直面する可能性があります。
しかし、行政や民間の支援サービスを活用し、家族や地域とのつながりを持つことで、多くのリスクを軽減することが可能です。
本人の意思を尊重しながら必要な支援や環境整備を行うことで、安心して自立した生活を長く続けることができるでしょう。