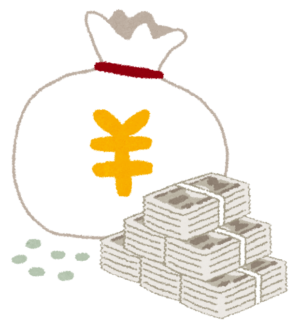ADLとは?介護・看護の現場で必ず知っておくべき基本知識から評価方法を解説

医療や介護の現場で働く方であれば「ADL(Activities of Daily Living)」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。
ADLは利用者が日常生活を自立して送るための指標となり、その向上はQOL(生活の質)の改善にもつながります。
本記事ではADLの基本的な意味や重要性を解説し、ADLを向上させる方法や具体的な実践事例を紹介していきます。
さらに、評価の仕方についても詳しく解説しておりますので、ぜひ最後までご覧ください。
ADLとは
Activities of Daily Livingを直訳すると、「日常生活における動作」となります。これは、普段私たちが行っている食事や入浴、買い物や金銭の管理といった最低限必要な動作のことです。
高齢者の多くは、老化や疾患によってこれらの動作が十分に行えない場合があります。ADLを評価することで、できる動作とできない動作を正確かつ具体的に知ることができ、お一人おひとりに必要な介助や今後の目標がより明確になります。
ADLで評価される項目
ADLの評価方法は複数あり、それぞれで項目や分類が異なります。主な項目としては起居動作、食事、排泄、入浴、更衣、移乗、移動、整容などです。
日常生活における動作は、体の各部位の運動機能だけで判断されるものではなく、いくつかの動作を組み合わせ、行為を実行できるかどうかによって判断されます。そのため、評価される項目も、入浴や更衣といった実際の生活場面が意識されたものです。
また、単なる動作の可否だけでなく、必要な場面で必要な動作を選択できる判断能力や認知能力が評価項目に含まれることもあります。
介護・医療におけるADL評価の重要性
ADLは疾患の回復、または悪化などによって大きく変化します。ADLの評価は、現時点での状態を知るためにとても有効な手段です。しかし、それだけにはとどまらず、定期的な評価を行うことで、これまでの治療やリハビリの効果を計測でき、今後の方針の決定にも活用できます。
【支援計画における目標の設定】
自立支援のため、ケアプランには長期目標、短期目標の設定が必要です。ADLは、現在の状態でできる限りの能力を発揮することで実行可能とされる「できるADL」、普段の生活の中で行っている動作である「しているADL」とに分けられます。
実際には実行可能でも、職員やご家族が代行している動作もあるため、両者は同じではありません。
ADLの正しい評価によって、しているADLからできるADL、さらには未来のADLを獲得できるようにケアプランの設計に生かすことが大切です。
【必要な支援の明確化】
利用者にとってできる動作とできない動作が分かれば、どのような支援や介助が必要であるかが明確になります。
入浴では、手の届く部分は自身で洗い、背中などの届かない部分を職員に依頼するなどで、ご本人の残存能力を最大限生かすことにつながります。
アセスメントシートにADLの評価項目の記入欄を設けることで、職員も必要な介助が分かりやすくなるため、活用していきましょう。
パーキンソン病などの進行性の疾患であれば、現在の状態から将来的にどのようにADLが低下していくかについて、ある程度の想定と対策の構築が事前に可能となります。
【ADL維持加算の取得】
要介護者の増加に歯止めをかけるため、2021年度の介護加算要件の改正により、厚生労働省はADL維持加算を設けました。また、そのための評価にバーサルインデックスを用いることとしています。加算を受けるためには、ADLの定期的な評価によって、日常生活機能の維持を証明することが必要です。
ADLの種類
ADLの評価には、観点によって2つの指標が存在します。それぞれの特徴を解説します。
BADL(基本的ADL)
基本的な生活動作に焦点を当てて評価されるものがBADLです。食事や整容、移動、入浴などの基本的な行為についての能力を意味します。排泄については、トイレの使用や排尿、排便のコントロールについても評価対象です。
BADLが低下した状態では、何らかの介助を受けなければ生命維持ができない状態となるため、最優先の支援が求められます。
BADLは、一般的なADLと同じ意味で使われることが多い言葉です。
IADL(手段的ADL)
BADLと比較して、さらにいくつかの動作を含んだ、日常生活におけるより複雑な遂行能力を表すものをIADLと呼びます。例えば、掃除や料理、洗濯などの家事や、電話をかける、買い物に行くといった行動、服薬や金銭の管理、交通機関の利用などが挙げられます。身体機能よりも認知機能が色濃く現れるADLです。
IADLの低下は人間らしい生活の喪失やQOL(Quality of Life:生活の質)の低下を招くことになるため、支援を必要とします。
「できるADL・しているADL」の評価方法
ADL評価法で代表的なものは6種類です。
BADLの評価法とIADLの評価法の2つに分けられ、いくつかの項目に点数を付けて総合点で判断する方法や、質問に対して、はい・いいえで回答してもらうことで判断する方法があります。
| 評価の名称 | 評価されるADL | 項目の内容 | 特徴 |
| Barthel Index | BADL | 食事やトイレ動作など10項目 | 世界的に普及 |
| FIM(機能的自立度評価法) | BADL、IADL | 13の運動項目と5つの認知項目 | セルフケア能力やコミュニケーション能力で評価 |
| Lawtonの尺度 | IADL | 買い物や食事の準備といった項目 | 細かい評価が可能 |
| Katz Index | BADL | BADLの6項目において自立か介助かで判断 | AからGの指標で総合的に判定 |
| DASC-21 | BADL、IADL | 認知機能と生活機能 | 認知症の有無や程度を評価 |
| 老研式活動能力指標 | IADL | 手段的自立、知的能動性、社会的役割 | 質問に対してはい・いいえで回答 |
Barthel Index(BI:バーセルインデックス)
BIは世界的に普及しているADLの評価法の一つです。食事、車椅子からベッドへの移動、整容、トイレ動作、入浴、歩行、階段昇降、着替え、排便コントロール、排尿コントロールの10項目において、それぞれできる、一部可能、まったくできないといった2~4段階の選択肢の中から1つを選び、点数を集計して評価されます。
例えば、食事であれば「自立(10点)」「部分介助(5点)」「全介助(0点)」の3段階で採点され、整容であれば「自立(5点)」「部分介助または不可(0点)」の2段階です。点数が高ければ自立度が高いとされており、満点となる100点が自立、0点が全介助となります。
FIM(機能的自立度評価表)
高齢者が実際に行っている動作、している動作について、13種類の運動項目、5種類の認知項目を合わせた計18項目においてそれぞれを1~7点で評価し、合計点で評価する方法です。BIと比較すると、「コミュニケーション能力」や「社会的認知」の項目が評価に含まれるという特徴があります。
Lawtonの尺度
IADLを評価する方法で、電話をする能力、買い物、食事の準備、家事、洗濯、移動の形式、服薬管理、金銭管理の8つの大項目があり、それぞれに3~5つの具体的な項目を含んでいます。合計31の項目について0~8段階の尺度で採点されるため、細かい評価が可能です。
Katz Index(カッツ・インデックス)
入浴、更衣、トイレ、移動、排泄コントロール、食事の6つのBADLについて、自立、または介助必要で判定をします。その後、6つの項目の中でどの項目が自立であったか、いくつの項目が自立であったかでAからGに分けられ、総合的に判断される評価法です。
DASC-21
「認知機能」と「生活機能」から認知症の程度を評価する方法で、BADL、IADLのどちらの評価にも使われます。
評価項目は、記憶、見当識、問題解決判断力、身体的ADLなどです。これらを含む21の項目について各1~4点で評価され、合計31点以上であれば認知症の可能性があると判断されます。
老研式活動能力指標
1986年に日本で考案されたIADLの評価方法です。手段的自立、知的能動性、社会的役割の3つの観点から13の項目があり、質問に対して、はい・いいえで答えるだけで採点できるため、ご本人やご家族でも回答を得やすい特徴があります。
主な質問としては、「バスや電車を使って一人で外出できますか」「自分で食事の用意ができますか」などです。
ADLが低下するとどうなる?
日常の生活動作を意味するADLですが、低下によって、介護度の悪化や利用者のQOLの低下が引き起こされます。利用者の生活に特に影響を与えるものについて解説します。
廃用症候群
廃用症候群は、疾患や治療のための静養によって、使われなくなった筋力や関節可動域が弱体する現象です。一度低下すると回復には時間がかかることも多いため、医療の現場ではなるべく早いリハビリの開始が求められます。
特に高齢者は入院が長期化しやすく、廃用症候群を引き起こしやすい上に回復しにくい傾向があるため、注意が必要です。
認知症の進行
ADLの低下はQOLの低下を引き起こし、生活のメリハリや刺激の喪失につながります。刺激の少ない生活は認知症の進行を早めることとなり、ADLをさらに低下させる要因にもなります。
複雑な認知能力を必要とするIADLの低下は特に顕著です。さらに放置すればBADLにも影響を与え、生命維持まで難しくなります。
認知症は一度進行してしまうと回復は困難であるため、早めの対策が必要です。
自立性の減退
今までできていたことができなくなることで、自信の喪失や自己肯定感の低下を引き起こします。
精神的な落ち込みの影響は生活環境の乱れに顕著に現れます。外出や会話を控えたり、できることもやらなくなったりすることで、引きこもりやすくなり、部屋も散らかるようになります。
そして、身体機能の低下や生活習慣病の悪化、認知症の進行を引き起こすなど、影響は多岐にわたり、さらなるADLの低下につながることでしょう。
転倒などの事故の増加
骨折などで歩行状態が悪化すると、今までつまずいたことのない場所でもつまずいたり、短い距離でも疲労を感じたりするため、転倒などの事故の増加には注意が必要です。
認知機能の低下も、段差の認識や危険予測が難しくなるため、外出先での転倒や交通事故に巻き込まれることにつながります。
しかし、外出を控えたり、運動量が低下したりすると、さらにADLを低下させる要因となるため、安全に配慮しながら運動量を上げることが大切です。
ADLを低下させる要因
ADLの低下には複数の要因が絡むことも少なくありません。主な要因は以下になります。
・疾患の進行
・行動制限
・気力の減退
・過剰介護
これらはADL低下の要因であるとともに、ADLの低下によって引き起こされるものでもあるため、悪循環を引き起こしやすいことを覚えておきましょう。
疾患の進行
慢性疾患やケガによって体に障害が発生していると、ADLにも影響を与えます。例えば、高血圧や糖尿病などの生活習慣病、脳梗塞、心臓病、パーキンソン病、関節炎、骨折、認知症などです。
特に脳梗塞による体の麻痺はBADLに直接影響を与える上に回復も困難であり、運動量の低下は再発のリスクを高めることからも注意が必要です。
パーキンソン病や認知症も進行性の疾患であり、身体機能や認知機能に大きな影響を及ぼすため、徐々にADLが低下していきます。
これらの疾患の発症を防いだり、病状の進行を遅らせたりすることが、ADLの維持には不可欠です。
行動制限
身体的、認知的疾患によって一度でもADLが低下してしまうと、今までの生活に比べて、運動量が低下しやすくなります。これまで歩けた距離が歩けなくなったり、車椅子になってしまったりすることで筋肉は衰え、ADLのさらなる低下が引き起こされることでしょう。
認知機能の低下も、危険予測が困難であることから、周囲から外出を控えるよう言われたり、行動を制限されたりすることになりかねません。
このような活動量の減少はADL低下の要因となり、低下したことでさらなる行動制限へとつながる悪循環を生み出します。
気力の減退
精神的な落ち込みややりがいの喪失によって、行動量が減少することでADLが低下しやすくなります。
定年で退職し、社会とのつながりや目的意欲を一度に失うことで気力が減退すると、老化による身体機能の低下をさらに強めることでしょう。そのままの状態が続くと、引きこもりやすくなり、生活の乱れから生活習慣病のリスクも高まります。
何歳になっても趣味に夢中になったり、社会との関わりを持ち続けたりすることで、目的意欲を失わないことが大切です。
過剰介護
ADLの評価が実際より低く見積もられていたり、ご本人にできる能力があるのに介護職員が必要以上にお世話をしてしまったりすることも、ADLの低下を招きます。
実際のADLの評価は動作の一つひとつに対して個別に点数を付けますが、正しい評価がされないと、「これができないから、きっとこれもできないだろう」と周囲から低く見積もられる原因にもなります。
また、忙しい介護の現場では、ご本人に任せていると時間がかかりすぎることから、できることでも職員が代わりに済ましてしまっていることも多いのが現状です。
ADLを正しく評価し、ご本人にできることはお願いして、必要以上の介助を行わないことも、ADLの低下を防ぐ手立ての一つとなります。
介護におけるADL向上のためのアプローチ
一度低下したADLを向上させるのは決して簡単ではありませんが、周囲のアプローチによってADLの維持または向上が可能になる場合もあります。介護の現場において、ADLを向上させる方法を解説します。
身体的リハビリテーション
ADLの向上には、定期的な運動トレーニングが欠かせません。単純な筋力アップのトレーニングも大切ですが、日常生活動作に直結する柔軟性の習得が特に重要です。
例えば、入浴時に頭を洗ったり、ドライヤーをかけたり、髪を結んだりするときには、腕が頭の位置まで上がることが条件になります。
また、トイレでズボンの上げ下げをしたり、排泄の後始末をしたりするときには、手が腰の位置まで届くことが大切です。
これらの動きは結髪動作、結帯動作と呼ばれ、自立した日常生活動作をするために必要な動作となります。
理学療法や作業療法による訓練に加え、家事や趣味の活動を積極的に支援することで生活リハビリテーションを促進することも大切です。
認知リハビリテーション
認知症の改善には脳への刺激だけでなく、運動療法や五感に働きかけるプログラムが効果的です。作業療法士による作業療法には入浴や着替えといった、日常生活を意識したさまざまなメニューがあり、訓練を通して生活動作を取り戻せることもあります。
また、運動療法では体を動かすことでリフレッシュした気分になり、音楽療法や回想法は感性に働きかけることで脳の機能を活性化させます。個別の趣味を行うことも、脳にとってよい刺激を与えることとなり、認知症の改善に期待できるでしょう。
このような活動は認知機能の維持や改善だけでなく、BPSDの低下やQOLの向上にも効果が見込めます。
環境の改善
ADLが低下した状態で行動を制限してしまうと、活動量が不足し、さらにADLが低下してしまいます。行動を制限するのではなく、環境を整えることで活動を維持することが大切です。
例えば、転びそうになったときにすぐにつかむことのできる手すりの設置や段差の解消、トイレまでの動線の短縮などがあります。ポータブルトイレや自助箸、マジックテープで簡単に脱着できる衣類などを必要に応じて利用することも、ご本人の自立した行動を促進し、ADLを低下させない取り組みの一つです。
バランスのよい食事
食事は健康的な生活の基本です。偏った食生活では必要な栄養素が不足し、生活習慣病といった疾患の悪化に直結します。また、エネルギーの元となる糖質やタンパク質が不足すると、活動量が抑えられ、さらなるADLの低下につながるかもしれません。
特に高齢者は、骨や筋肉を作るためのタンパク質やカルシウムが不足しやすいため、積極的に取り入れられるようにしましょう。そのほか、体の調子を整えるビタミンやミネラル、食物繊維などを多く含む食材をバランスよくとることが大切です。
社会的な役割の創出
高齢になると、社会的な役割の喪失や孤独感から、自己肯定感や意欲の低下が見られます。一人での外出ができなくなると、社会との接点も少なくなり、メリハリのない単調な生活になりかねません。
このような生活では栄養状態も悪く、活動量も低下し、疾患の悪化や認知症の進行にもつながり、ADLがますます低下していくことが予想されます。
反対に、いつまでも社会との接点を持ち、なんらかの社会的な役割を担い続けている人は、いつまでも元気でいられることが知られています。
たとえADLが低下しても、ほんの少しの家事やちょっとしたお手伝いをお願いし、ご本人の意欲や自己肯定感を引き出すようにアプローチすることが、ADLの向上につながることでしょう。
転倒などの事故や長期入院の防止
骨粗鬆症によって骨がもろくなっている高齢者は、軽い転倒でも、骨折といった大きなケガにつながってしまいます。一度骨折してしまうと、いつまでも痛みが引かなかったり、以前のようには歩けなかったりするため、活動量の低下や社会とのつながりの希薄化が一層強まることでしょう。
また、入院中は活動量を制限されることが多く、入院期間が長くなればなるほど廃用症候群を引き起こしやすくなります。
運動療法や環境の改善などで転倒を防ぐとともに、栄養状態に留意して病気にならないように注意することが大切です。
ADLが向上した実際の事例
ADLの向上は、単にできることを増やすだけにとどまりません。利用者本人のやりたいことや楽しみを増やすことで、QOLの向上が見込まれます。そのためには周囲との協力が欠かせません。
さまざまな取り組みによって、ADLが向上した実際の事例を2つ紹介します。
ケース1:機能訓練とレクリエーションによって歩行を可能に
【本人像】
70代 男性 認知症
高齢による身体機能の低下があり、歩行は不安定なため車椅子を使用。起居動作も自力では十分に行えない。
認知症の進行により、短期記憶の忘却が顕著で、直前のことも忘れてしまう。尿意、便意の訴えもないためオムツを着用。昼夜逆転の傾向があり、夜間に歩き出してしまうため転倒リスクが高い。同居中の奥様の介護負担が大きく、有料老人ホームに入居となる。
【対応】
本人は口数が少ないので、職員は傾聴の姿勢を重視する。カラオケやイベントは好まれるため、施設のレクリエーションには積極的に参加を募った。
理学療法士による機能訓練にも意欲的に取り組まれ、立ち上がりができるようになったことから、オムツを外して定期的なトイレ誘導を行った。
早食いの傾向があるため、食事は小さめのスプーンを使用し、誤嚥しにくいように工夫した。
【結果】
ほかの入居者との関わりによって社会的なつながりを再構築したことで、ご本人の自信や意欲の向上につながり、笑顔を取り戻すことができました。尿意、便意の訴えはないものの、職員の定期的なトイレ誘導によってトイレでの排泄が可能になり、ご本人も自信を取り戻せたようです。また、職員が時間をかけて促すことで、起き上がりも自力でできるようになり、ついには歩行ができるまでに回復し、ADLが大きく向上する結果となりました。
ケース2:経口での食事摂取を可能に
【本人像】
80代 男性
グループホームに入所。食事量が日によってムラがあり、嚥下能力の低下も影響して体重が大きく減少した。
一日中活気がなく、活動への意欲が見られない。職員への依存も強く、自発的な行動はほとんどない状態だった。
【対応】
主食の粥にご本人の好物を入れて提供し、一口でも多く食べてもらえるように工夫した。
高栄養のゼリーを1日1個提供し、栄養面を補うようにした。
生活リズムをつくるために、離床時間を増やし、カラオケなどでほかの入居者との交流も図った。
昼寝は1時間程度と決め、職員間でも声かけを統一した。
【結果】
体重は大きく増加し、BMI値も標準体型まで改善しました。歯の治療が進んだことで好物の固いお菓子も食べられるようになり、楽しみが増えたことから意欲の向上にもつながったのでしょう。
現在はカルタやぬり絵などをほかの入居者と行いながら、会話も楽しまれています。
食事による栄養改善と生活リズムの構築、他者との活発なコミュニケーションがADLを向上させ、好物を食べられるまでにQOLを上げた事例です。
BI(バーセルインデックス)での具体的な評価方法
ADLを評価する方法は複数ありますが、介護報酬におけるADL維持加算では、BI(バーセルインデックス)による評価が選定されています。本記事でもBIによる評価方法を解説します。
BI(バーセルインデックス)とは
病院や介護現場で用いられるADLの評価法で、利用者の日常生活動作を客観的な指標で判断することが可能です。食事や整容、トイレ動作などの10項目からなり、それぞれの評価項目に2~4段階の点数が付けられ、満点が100点となるように設計されています。
比較的短時間で、誰でも簡単に評価ができるため、世界的に広く利用されている評価法です。
BIを用いたADLの計算方法
BIによる評価シートには、10項目についての質問内容と各点数が割り振られています。
100点が自立、60点が部分介助、40点が大部分介助、0点が全介助です。
| 項目 | 質問内容 | 点数 | 採点 |
| 食事 | 自立、自助具などの装着可、標準的時間内に食べ終える | 10点 | |
| 部分介助(たとえば、おかずを切って細かくしてもらう) | 5点 | ||
| 全介助 | 0点 | ||
| 車椅子から ベッドへの移動 | 自立、ブレーキ、フットレストの操作も含む(非行自立も含む) | 15点 | |
| 軽度の部分介助または監視を要する | 10点 | ||
| 座ることは可能であるがほぼ全介助 | 5点 | ||
| 全介助または不可能 | 0点 | ||
| 整容 | 自立(洗面、整髪、歯磨き、ひげ剃り) | 5点 | |
| 部分介助または不可能 | 0点 | ||
| トイレ動作 | 自立(衣服の操作、後始末を含む、ポータブル便器などを使用している場合はその洗浄も含む) | 10点 | |
| 部分介助、体を支える、衣服、後始末に介助を要する | 5点 | ||
| 全介助または不可能 | 0点 | ||
| 入浴 | 自立 | 5点 | |
| 部分介助または不可能 | 0点 | ||
| 歩行 | 45分以上の歩行、補装具(車椅子、歩行器は除く)の使用の有無は問わず | 15点 | |
| 45分以上の介助歩行、歩行器の使用を含む | 10点 | ||
| 歩行不能の場合、車椅子にて45分以上の操作可能 | 5点 | ||
| 上記以外 | 0点 | ||
| 階段昇降 | 自立、手すりなどの使用の有無は問わない | 10点 | |
| 介助または監視を要する | 5点 | ||
| 不能 | 0点 | ||
| 着替え | 自立、靴、ファスナー、装具の着脱を含む | 10点 | |
| 部分介助、標準的な時間内、半分以上は自分で行える | 5点 | ||
| 上記以外 | 0点 | ||
| 排便コントロール | 失禁なし、浣腸、坐薬の取り扱いも可能 | 10点 | |
| ときに失禁あり、浣腸、坐薬の取り扱いに介助を要する者も含む | 5点 | ||
| 上記以外 | 0点 | ||
| 排尿コントロール | 失禁なし、収尿器の取り扱いも可能 | 10点 | |
| ときに失禁あり、収尿器の取り扱いに介助を要する者も含む | 5点 | ||
| 上記以外 | 0点 | ||
| 合計点 | 100点 |
まとめ
ADLはBADLとIADLに分けられ、生命維持やQOLに深く関係している日常生活動作です。
疾患の進行や認知症の悪化、気力の減退、活動量の減少などによってADLは低下し、さらに悪循環から次第にできることが減少してしまいます。
しかし、運動療法や栄養状態の改善、社会的な役割の創出といった適切なアプローチによって、失われた能力を取り戻すことも可能です。
BIをはじめとしたいくつかの評価法は、利用者のADLを客観的に評価し、アプローチの効果測定や方針の修正にも活用できます。
この記事の内容が、皆さまのお役に立てたら幸いです。