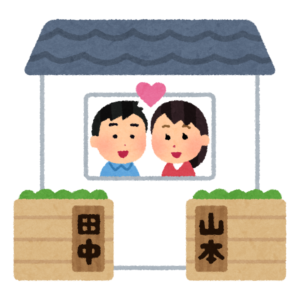介護タクシーとは?福祉タクシーとの違いや条件、かかる料金についても紹介

介護が必要な家族の移動手段として、「介護タクシー」について気になっていませんか?
一般的なタクシーや福祉タクシーとの違い、利用条件や料金が分からない方も多いでしょう。
本記事では介護タクシーの基本情報から利用できる人の条件、かかる費用、依頼方法まで詳しく解説していきます。
介護タクシーがよく分からない方や福祉タクシーとの違いを知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
介護タクシーとは?
介護タクシーとは、介護が必要な方や体に障がいがある方が利用するためのタクシーのことです。
通常のタクシーとは異なり、車椅子のまま乗車できる車両で、介護福祉に関する資格を持つドライバーが対応することが特徴です。
まずは介護タクシーの特徴や利用方法、メリットから確認していきましょう。
訪問介護サービスの一つ「通院等乗降介助」
介護タクシーの正式名称は「通院等乗降介助」と呼ばれ、訪問介護サービスの一つとされています。
タクシーによる移動のほかに介助サービスが含まれるため、乗務員は「介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)」などの資格を取得しなければなりません。
また、介護サービスであるということから、利用する方は要介護認定で定められた自己負担割合に合わせた費用(1~3割)を支払う必要があります。
受けられるサービス内容
介護タクシーが行うサービスには、大きく分けて次の3つが挙げられます。
- 出発時のサポート
- 目的地での介助サポート
- 帰宅時のサポート
それぞれの業務内容を詳しく紹介していきます。
【出発時のサポート】
出発時のサポートでは、出発までの準備や介助、移動などを行います。
- 自宅へ迎車
- 靴を履く
- 車椅子への移乗
- タクシーまでの移動 など
このように、外出に必要な介助や移動を行います。
なお、自分で着替えすることが難しい方は、「更衣介助」を依頼することになります。
【目的地での介助サポート】
目的地に到着したら、以下の介助を行います。
- 降車介助や移動介助
- 病院での受診手続きや支払い補助
- 薬の受け取り
介護タクシーがもっとも利用されるのは、病院への通院です。
後ほど詳しく紹介しますが、介助サポートにはできることとできないことがあります。
【帰宅時のサポート】
帰宅時のサポートでは、出発時のサポートと同様に、主にタクシーからの降車と玄関までの介助を行います。
- 降車介助
- 玄関までの移動
- 室内までの移動
- 着替えやおむつ交換(必要時)
利用者の体調や状態に合わせた柔軟な対応が求められます。
車椅子や寝台車のまま乗車可能な介護タクシーもある
介護タクシーの大きな特徴の一つが、車椅子や寝台車のまま乗車できる車両が用意されていることです。
移乗の必要がないため、移動に負担を感じる利用者や介助者にとって、非常に便利なサービスです。
ほとんどの車両にはリフトやスロープが標準装備されており、スムーズな乗り降りをサポートします。
また、身体状況に応じて回転シートタイプの車両が使われることもあり、立ち上がりやすさや乗り込みやすさが格段に向上します。
セダンタイプの介護タクシーもありますが、ワンボックスカーが主流です。
一般的なタクシーや福祉タクシーとの違い
介護タクシーを検討される方の中には、一般的なタクシーや福祉タクシーとの違いが気になる方もいると思いますが、それぞれ特徴が少し異なります。
一般的なタクシーは、車両もドライバーも介助に対応しておらず、さらに介護保険は利用できません。
一方で福祉タクシーは、高齢者や障がいがある方に対して移動支援を行うサービスです。
介護タクシーと異なる点としては、福祉タクシーは介護保険適用外となるため、利用料金はすべて自己負担となるところです。
また、対象者や利用できる用途の幅も広く、要介護認定されていない方でもサービスを受けられます。
介護タクシーを利用できる人と利用目的
介護タクシーは、利用できる人に当てはまるか、また利用目的に含まれているかなど、いくつかの条件を満たしていなければ利用できません。
詳しく紹介していきますので、ここで一緒に確認していきましょう。
利用できる人
介護タクシーを利用できる人は、以下の条件を満たす必要があります。
- 自宅や有料老人ホーム、サ高住、ケアハウスなどに住んでいる方
- 要介護1~5の認定を受けた方
- 公共交通機関を1人で利用できない方
基本的に利用できる方は、在宅介護サービスを受けている方となります。
また、要介護認定で要支援と判定された方は対象外となるため、覚えておきましょう。
利用目的
介護タクシーを利用するためには、利用範囲にも注意が必要です。
- 通院(リハビリも含む)
- 補装具、補聴器、メガネの調整
- 必要最低限の買い物
- 預金の引き出し
- 役所への届出や選挙投票
上記のように、日常生活や社会生活を送る上で必要な外出でしか利用できないと決まっています。
買い物や趣味では利用できない
1つ前で紹介したように、介護タクシーを利用できるのは日常的もしくは社会的な生活を送る上で必要な外出のみです。
個人的な買い物や趣味、旅行などでの利用はできないため注意してください。
もし、個人的な用途で利用したい場合は、この後で紹介する介護保険適用外で利用するか、福祉タクシーを検討するとよいでしょう。
介護保険適用外でも利用できる
介護タクシーは、介護保険が適用されない場合でも利用できます。
介護保険適用外で利用する場合はケアプランの作成は必要なく、利用目的にも制約はありません。
また、要介護認定1~5以外の方でも利用できるので、どなたでもサービスが受けられるようになります。
ただし、介護保険は適用されないため、かかる料金はすべて自己負担となることに注意が必要です。
介護タクシーを利用する際にかかる料金と内訳
介護タクシーを利用する際にかかる料金は、以下の3つです。
- 運賃
- 介助費用
- 介護器具レンタル料
基本的には、介護保険が適用されるのは上記3つの中で「介護費用」だけです。
そのほか2つは自己負担となりますので注意しましょう。
運賃
運賃は事業所によって異なりますが、一般的には時間によって料金を計算する「時間制」と、距離によって料金を計算する「距離制」の、どちらか一方が設定されます。
また、場合によっては「時間距離併用制」が設定される場合があります。
料金の目安は以下のとおりです。
| 時間制 | 500~1,000円/30分 |
| 距離制 | 300~500円/1km |
| 時間距離併用制 | 300~500円/1km + 時速10km以下で90秒ごとに100円 ※渋滞時や待機時など |
上記はあくまで目安となっており、事業所によって金額が変わるため必ず確認しましょう。
介助費用
介助費用に関しては、どの程度のサービスを利用したかによって料金が違ってきます。
料金の目安は以下のとおりです。
| 基本介助料 | 無料~1,000円 |
| 移乗や室内での介助 | 500~1,000円 |
| 階段昇降の介助 | 1,000~2,000円 |
| 付き添い介助 | 1,000~2,000円/30分 |
| 複数名での介助 | 2,000~5,000円/1名追加につき |
上記のように、介助費用は介助基本料に加えて、サービスを受けた数が加算されます。
場合によっては高額となる可能性もあるため、ケアプラン作成時に予算に合わせたサービスを依頼しましょう。
介護器具レンタル料
介護器具レンタル料は必要器具によって料金が異なりますが、目安は以下のとおりです。
| 車椅子 | 無料~1,000円 |
| ストレッチャー | 3,000~6,000円 |
| 酸素吸引機 | 3,000~5,000円 |
レンタルできる種類は車椅子やストレッチャーのほかに、酸素吸引機などの医療器具も借りられます。
ただし、事業所によって借りられるものが異なるため、借りたい方は必要な器具があるか確認しましょう。
もしも自身で持っている器具がある場合は、使用が可能なため費用を抑えられます。
一部医療費控除の対象にできる
介護タクシーは、一部サービスが医療費控除の対象となっています。
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税の一部が軽減される制度です。
介護タクシーの中で医療費控除の対象となるのは、医療機関を利用したときであり、例えば以下のシーンで対象となります。
- 入院や退院、転院の際に利用したとき
- 病院を受診するとき
- 医師の指示によって行われた鍼治療やマッサージ など
基本的には、上記以外の買い物や旅行といった個人的なものは対象となりません。
なお、介助費用に関しては実際に支払った自己負担額のみ医療費控除の対象となるため、覚えておきましょう。
介護タクシーの依頼方法
介護タクシーを利用するためには、いくつかの手順を踏む必要があります。
ここで詳しく紹介するので、確認してから依頼しましょう。
①要介護申請・認定
介護タクシーを介護保険を適用して利用する場合、要介護認定を受けなければ利用できません。
利用できる要介護度は1~5であり、要支援と判断された場合は利用できないため覚えておきましょう。
申請は、お住まいの地域の市区町村の窓口にて行い、1~2カ月ほどかけて、判定を経て結果が通知されます。
判定は、訪問調査や主治医の意見書などをもとに判断されます。
②ケアマネージャーに相談
認定を受けて要介護1~5の判定が出れば、次にケアマネージャーに相談します。
ケアマネージャーは、お住まいの地域の市区町村の介護保険課や、地域包括支援センターから居宅介護支援事業所のリストをもらい、そこから探すのが一般的です。
そのほかにも、かかりつけの医師がいる場合は、その病院と連携しているケースもあるので、一度相談してみるとよいでしょう。
③ケアプランの作成
ケアマネージャーが決まれば、ケアプランの作成に移ります。
介護タクシーを使いたいことを伝えて、利用できるかどうか、どのような事業所があるかなどを相談します。
相談する際は「利用シーン」や「スケジュール」などを細かく聞かれるため、事前に決めておきましょう。
④介護タクシー事業者を選ぶ
ケアマネージャーに相談すると、条件に合った事業所をいくつか紹介してもらえるため、本人に合ったところを選びます。
選び方は後述しますが、料金や運転手との相性などをチェックしましょう。
どうしても決められない場合は、ケアマネージャーに選んでもらうのも一つの方法です。
⑤介護タクシー事業所と契約
事業所が決まれば、契約手続きに移ります。
ほとんどの手続きは、ケアマネージャーと介護タクシー事業所の間で行われるため、本人が直接やり取りする必要はありません。
⑥利用内容・乗車予定日を決める
契約を結んだら、実際に利用する日時を決めます。
日時を決める際は以下の内容を聞かれるため、スケジュールを事前に決めておきましょう。
- 利用日時
- 行き先
- 迎え場所
- 連絡手段
- 自宅環境
- 車椅子の使用有無
- 帰宅の送迎
なお、介護タクシーは通常のタクシーと異なり予約が必要です。
何日前から予約が可能なのかは事業所によって違ってくるため、利用する場合は早めに予約することをおすすめします。
⑦実際にサービスを利用する
利用日時が決まれば、実際にサービスを利用します。
なお、利用時に忘れ物があると自宅に戻るための料金が発生しますので、準備はしっかりと行いましょう。
介護タクシーを利用する際の注意点
介護タクシーを利用する際は、いくつか注意点もあります。
場合によってはサービス利用料が増えてしまう可能性もあるため、事前に確認しておきましょう。
基本的に家族の同乗はできない
介護タクシーは、基本的に家族が同乗して利用するのは許可されていません。
あくまで契約されたご本人のみの利用となるため、覚えておきましょう。
例外的に家族の同乗が認められるケースもある
原則として家族の同乗は許可されていませんが、状況次第では可能なケースもあります。
例えば、以下のケースは許可される場合があります。
- 認知症や精神疾患により家族が近くにいないと安心できない方
- たん吸引が必要な方
- 本人だけでは通院の目的が果たせない場合
上記のケースに当てはまる場合は、担当のケアマネージャーや事業所に相談しましょう。
病院内での付き添いや介助はできない
介護タクシーは通院時の送迎や受付サポートなど、移動に関わる介助には対応できますが、原則として病院内での診察の付き添いや、検査時の介助などは行うことができません。
病院内でのサポートは基本的に病院職員が担いますが、特別な事情がある場合には例外的に認められるケースもあります。
例えば、認知症や精神疾患によって単独行動が難しい方、広い院内での移動が困難な方、またトイレ介助が必要な方などは、医療機関との調整の上で付き添いが許可される場合があります。
事前にケアマネージャーや医療機関に相談し、必要なサポート内容と対応範囲をしっかり確認しておくことが重要です。
介助時間が増えると別のサービスが適用される
介護タクシーでは移動や乗降時の介助など、一定範囲のサポートが提供されますが、介助の時間や内容によっては、別の介護サービスが適用される場合があります。
例えば、自宅での掃除・洗濯・調理・ゴミ出しといった日常生活の支援や、買い物の代行などを依頼する場合は「生活援助」に該当します。
また移動や排泄、更衣など、体に直接触れる介助が長時間に及ぶ場合は「身体介護」です。
利用料金の計算方法やサービス内容が変わる場合もあるため、事前にケアマネージャーへ相談しておくと安心です。
移動だけでは利用できない
介護タクシーは、通院や福祉施設への送迎など、介護が必要な方の移動を支援する目的で運行されています。
そのため、単なる移動手段としての利用は許可されていません。
特に、買い物や外食など、私的な目的での利用は制限されてしまうので注意しましょう。
介護タクシーの探し方と選ぶ際の判断ポイント
介護タクシーを利用する際は、自分に合ったサービスを選ぶことが大切です。
事業所を決める前に料金や設備などを確認し、安心して利用できるタクシーを見つけましょう。
ここからは、介護タクシーの探し方と選び方のポイントを紹介していきます。
ケアマネージャーに相談する
ケアマネージャーならニーズに合った介護タクシーを紹介してくれます。
自分で事業所を見つけて依頼することもできますが、車椅子の有無や利用者の体の状態など、細かな詳細を伝える必要があります。
基本的に、ケアマネージャーに任せるのがよいでしょう。
どれくらいの料金がかかるか事前に聞いておく
介護タクシーの料金は事業所によって異なり、基本料金のほか介助費用や待機時間の加算など、利用内容によっても変動します。
そのため、事前に料金の目安や詳細な内訳を聞いておくことが大切であり、見積もりを出してくれる事業所を選ぶと安心して利用できます。
運転手についてもチェックしておく
場合によっては長時間の利用も考えられるため、運転手との相性もチェックしておきましょう。
運転技術や介助のスキルに加え、対応の丁寧さなども含めて選ぶことが大切です。
初回の利用時に様子を見て、相性が合わないと感じた場合は遠慮せず事業所に相談し、別のスタッフに変更してもらうのも一つの方法です。
安心して利用するためにも、信頼できる運転手がいる事業所を選びましょう。
家族の協力も検討しておく
介護タクシーの利用は、場合によって利用する回数が多くなります。
利用回数が増えるほど料金も高くなるため、家族と話し合い、必要に応じて送迎をサポートしてもらうことも検討しましょう。
保険適用範囲外で利用したいなら福祉タクシーも検討する
ここまで紹介してきたように、介護タクシーはいくつかの条件や目的に合っていなければ利用できません。
しかし、福祉タクシーであれば利用可能な範囲や条件が広がります。
ここでは、福祉タクシーの詳細を紹介していきます。
利用できる人
福祉タクシーを利用できる人は以下のとおりです。
- 要介護もしくは要支援を判定された方
- 身体障害者手帳や療育手帳を交付されている方
- 身体的もしくは知的に障がいがあり、公共交通機関を1人で利用できない方
上記のように幅広い方が利用可能であり、加えてケアプランの作成も必要ありません。
利用目的やサービス内容
利用目的やサービス内容は、介護タクシーと異なり幅広い範囲で利用可能です。
例えば、介護タクシーでは許可されなかった個人的な買い物や食事、旅行、ドライブなどでも利用できます。
目的地や用途に関係なく利用できるので、利用者のニーズに合った使い方ができるところが大きなメリットといえるでしょう。
福祉タクシーの費用と補助金
福祉タクシーの費用に介護保険は適用されず、基本的にはすべて自己負担となります。
費用の内訳は「運賃」や「介助費用」など、介護タクシーと同様になりますが、料金はすべて自分で支払うことになるので、高額となりやすいことに注意が必要です。
ただし福祉タクシーでは、各自治体が割引券の配布など、負担額を軽減する措置をとっている場合があります。
市区町村によって異なりますので、お住まいの地域の役所に確認しましょう。
福祉タクシーを利用する際の注意点
前述のとおり、福祉タクシーを利用する際は介護保険が適用されない点に注意しましょう。
また、もう一つの重要なポイントとして、運転手が介護福祉に関する資格を持っているかを確認しましょう。
介護タクシーの場合は、運転手が「介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)」などを取得しなければなりませんが、福祉タクシーは介護福祉に関する資格がなくても運転できます。
つまり、介助が必要な方にとってはサポートが不十分な可能性があるため、事前に運転手の資格や介助対応が可能かを確認しておくと安心です。
まとめ
本記事では介護タクシーの詳細を解説し、利用できる人や利用目的、かかる費用、選ぶポイントなどを紹介してきました。
介護タクシーは移動が困難な方にとって便利なサービスですが、事前に料金や対応エリア、必要な手続きを確認することが大切です。
また、運転手の資格や車両の設備にも注意し、自分に合ったタクシーを選ぶことが重要です。
家族やケアマネージャーと相談しながら、安心して利用できるサービスを見つけましょう。