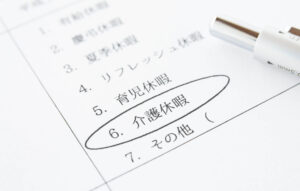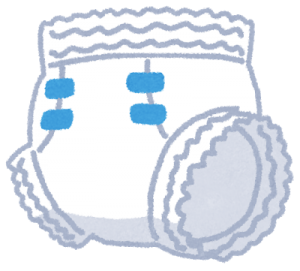介護福祉士試験の合格率情報まとめ!難易度・勉強法・資格取得ルートなど徹底解説

介護福祉士試験の合格率は、比較的高めに推移しています。
とはいえ、これから受験を考えている方は数字だけを見て安心せずに、しっかりと対策して試験に向かうのが得策でしょう。
そこで本記事では、第37回介護福祉士試験の合格率を紹介しつつ、試験の難易度や勉強法のコツなどを網羅的に解説していきます。
資格取得後のキャリアアップ方法や、目指せる職種も紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。
介護福祉士の合格率(第37回)データ
冒頭で述べたとおり、まずは第37回介護福祉士国家試験の合格率データを見ていきます。
試験が行われたのは、2025年1月26日です。
全体の合格率はもちろん、受験資格や年齢別のデータをまとめました。
(出典:厚生労働省「第37回介護福祉士国家試験合格発表について」)
第37回介護福祉士試験の合格率
第37回介護福祉士試験の合格率は、以下のとおりです。
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 75,387人 | 58,992人 | 78.3% |
試験問題の難易度に応じた補正の結果、合格点は70点とされています。
受験資格別合格率
介護福祉士試験の受験資格を得るには、「介護福祉士養成施設を卒業」や「介護業務の実務経験」といった条件を満たす必要があります。
以下は、受験資格別合格率をまとめたものです。
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
| 介護福祉士養成施設を卒業 | 6,955人 | 4,638人 | 66.7% |
| 社会福祉施設の介護職員 | 46,864人 | 36,771人 | 78.5% |
| 訪問介護員 | 9,761人 | 8,542人 | 87.5% |
| 介護老人保健施設、介護医療院の介護職員 | 4,852人 | 3,405人 | 70.2% |
| 医療機関の看護補助者 | 4,767人 | 3,661人 | 76.8% |
| 福祉系高等学校(専攻科を含む)を卒業 | 2,122人 | 1,917人 | 90.3% |
| その他 | 66人 | 58人 | 87.9% |
年齢別合格者の割合
以下の表は、介護福祉士試験の合格者を年齢別にまとめたものです。
| 年齢の区分 | 人数 | 割合 |
| 20歳以下 | 4,209人 | 7.1% |
| 21~30歳 | 15,746人 | 26.7% |
| 31~40歳 | 10,831人 | 18.4% |
| 41~50歳 | 13,659人 | 23.2% |
| 51~60歳 | 11,769人 | 20.0% |
| 61歳以上 | 2,778人 | 4.7% |
介護福祉士試験の合格率推移データ
介護福祉士国家試験の合格率は、毎年変動しています。
以下の表は、過去10年間の試験結果をまとめたものです。
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
| 第28回 | 152,573人 | 88,300人 | 57.9% |
| 第29回 | 76,323人 | 55,031人 | 72.1% |
| 第30回 | 92,654人 | 65,574人 | 70.8% |
| 第31回 | 94,610人 | 69,736人 | 73.7% |
| 第32回 | 84,032人 | 58,745人 | 69.9% |
| 第33回 | 84,483人 | 59,975人 | 71.0% |
| 第34回 | 83,082人 | 60,099人 | 72.3% |
| 第35回 | 79,151人 | 66,711人 | 84.3% |
| 第36回 | 74,595人 | 61,747人 | 82.8% |
| 第37回 | 75,387人 | 58,992人 | 78.3% |
過去10年間の累計データは、以下のとおりです。
- 受験者数:896,890名
- 合格者数:644,910名
- 合格率:73.3%
介護福祉士試験の出題内容と形式
次に、介護福祉士国家試験の概要を見ていきましょう。
具体的な科目内容や出題数、合格基準などを紹介していきます。
筆記試験の科目と出題数
介護福祉士国家試験は、広範囲にわたる専門知識が問われる内容です。
以下の11科目群から出題され、総問題数は125問にまで及びます。
| 人間の尊厳と自立・介護の基本、人間関係とコミュニケーション・コミュニケーション技術、社会の理解、生活支援技術、介護過程、こころとからだのしくみ、発達と老化の理解、認知症の理解、障害の理解、医療的ケア、総合問題 |
具体的な介護技術や医療に関する知識まで、幅広く理解しておく必要があります。
合格ライン
介護福祉士試験に合格するには、総得点(125点)の60%以上を取得し、かつ、11科目群すべてで得点を取得しておく必要があります。
具体的な合格ラインの目安は75点になりますが、全体の点数を満たしていても、いずれかの科目で0点を取ってしまえば不合格です。
また、問題の難易度に応じて合格点が補正される仕組みもあるため、75点という数値が絶対的な合格ラインではないことを理解しておきましょう。
実技試験の廃止
以前は筆記試験のほかに実技試験も課されていましたが、第37回の試験より筆記試験のみで合否が判定される形に変更されました。
実技試験を受けなければならない受験者は一部だったことが廃止の一因とされています。
2026年度から新制度を導入
2026年度の介護福祉士国家試験より、「パート合格制度」と呼ばれる新たな試験制度が導入される予定です。
主題範囲である11科目を3つのパートに分割し、それぞれのパートごとに合否が判定されます。
不合格のパートのみを次年度より受験できる形に変更されるため、合格しやすくなる効果も期待できるでしょう。
なお、合格しているパートの免除期間は2年とされています。
介護福祉士試験の難易度
ここからは、介護福祉士試験の難易度について客観的に評価していきます。
合格率から見た難易度の評価
介護福祉士国家試験の合格率は、例年70~80%前後で推移しており、福祉系資格の中では比較的高い水準です。
合格率が高くなる要因を分析すると、以下のような理由が挙げられます。
- 総得点の60%という合格基準が満たしやすい
- 回答形式が5肢択一式
- 実務経験が生かせる
- 問題集や講座が多い
ほかの福祉系国家資格との比較
介護福祉士は、社会福祉士や精神保健福祉士といったほかの福祉系国家資格と比較すると、合格率が高い傾向です。
例えば、社会福祉士の合格率は29~58%前後、精神保健福祉士の合格率は64~70%前後で推移していて、介護福祉士試験の合格率が高めであることが分かります。
合格率は高くても油断はできない
介護福祉士国家試験の合格率は高いですが、決して簡単な試験とはいえないでしょう。
特定科目で0点を取ってしまえば合格できないため、広い試験範囲すべてをしっかりと押さえておく必要があります。
漠然と勉強を進めるのではなく、出題傾向を分析し、計画的に学習していくことが必要不可欠です。
介護福祉士試験に合格するためのコツ・勉強法
介護福祉士国家試験の合格を目指すには、効率的な学習方法としっかりとした戦略が必要です。
ここからは、合格するための具体的なコツや、効果的な学習方法について解説していきます。
合格のコツは3つ
介護福祉士試験に効率的に合格するためには、いくつかのコツを押さえることが重要です。
特に意識したいポイントとして、以下の3点が挙げられます。
【得意分野を伸ばす】
介護福祉士試験は出題範囲のすべてで得点する必要があるため、全体的に学習を進めなければなりません。
試験勉強では、どうしても苦手な科目に時間を割きがちですが、得意分野をさらに強化し、得点できる点数を増やしていく学習方法がおすすめです。
苦手分野を完全に克服する必要はなく、得意分野で満点を狙ってカバーするほうが合格への近道といえます。
【本番と同じ条件で問題を解いてみる】
試験本番で実力を発揮するためには、過去問を実際の試験時間に合わせて解く練習が非常に有効です。
これにより、時間配分の感覚を養い、焦らずに問題を解き進めることが可能になります。
本番の試験で、落ち着いて臨むための自信にもつながるのでおすすめです。
【体調管理を怠らない】
どれだけ勉強しても、試験当日に体調が優れなければ実力を十分に発揮できません。
試験までの期間は、十分な睡眠とバランスの取れた食事を心がけ、ストレスをためないようにしましょう。
試験は冬場に実施されるため、かぜやインフルエンザなどの感染症予防も重要です。
体調を万全に整えることも、合格するためのコツといえます。
一般的な勉強方法は3種類
介護福祉士試験の勉強方法には、大きく分けて3つの選択肢があります。
通学して学習する方法、自宅で進められる通信教育、市販のテキストや問題集を使った独学です。
自身のライフスタイルや学習ペースに合わせて、最適な方法を選ぶことが効率的な学習につながります。
【通学して学習】
専門学校や大学などの養成施設に通学して学習する方法は、体系的に知識を習得できるだけでなく、講師に直接質問できる点が大きなメリットです。
同じ目標を持つ仲間と出会えるため、モチベーションを維持しやすいという利点もあります。
ほかの学習方法と比較して、費用や時間の制約はありますが、手厚いサポートが期待できる選択肢です。
【通信教育で学習】
通信教育は、自分のペースで学習を進められる点がメリットです。
テキストや問題集、DVDなどの教材を利用しながら、高い自由度で順を追って学習できます。
通学に比べて費用を抑えられる場合が多いですが、自己管理能力が求められる学習方法です。
【独学で学習】
独学は、市販のテキストや問題集を使い、自分の力だけで学習を進める方法です。
費用をもっとも安く抑えられる点が最大のメリットですが、学習計画の立案から進捗管理、疑問点の解決まですべて自分で行う必要があります。
強い意志と自己管理能力が求められますが、自分のペースで集中して学習したい方には適した選択肢です。
学習効率を高めるには?
介護福祉士試験の出題範囲は非常に広いため、学習効率を最大化していく工夫も必要です。
以下に挙げた方法を実践して、効率よく学習を進めていきましょう。
【先に全体のイメージをつかむ】
具体的な学習に入る前に、試験範囲全体の概要や各科目の関連性を把握し、学ぶ知識の全体像をつかんでおくと、より学習効率を高められるでしょう。
個々の知識がどこに位置づけられるのかが明確になり、理解度を深めることにもつなげられます。
自分の得意科目と苦手科目を知るきっかけにもなるので、率先して取り組んでみましょう。
【暗記はポイントを絞る】
介護福祉士試験では覚えるべき項目が多いですが、すべてを丸暗記しようとせず、ポイントを絞って記憶することが大切です。
語呂合わせや図解・イメージなどを活用して、楽しみながら覚える工夫を試してみましょう。
【過去問を解く】
出題傾向を把握し、自分の弱点を発見するために効果的な学習方法が、過去問を繰り返し解くことです。
実際の試験形式に慣れることで本番での焦りを減らし、時間配分の練習にもなります。
間違えた問題をしっかり分析し、関連部分を復習することで、知識の定着を進めることが可能です。
介護福祉士の職種情報
介護福祉士は、高齢者や障がいを持つ人々の生活を支える重要な専門職です。
ここからは、介護福祉士の具体的な役割や業務内容など、さまざまな要素について深堀していきます。
介護福祉士とは?
介護福祉士は、介護を必要とする人々に対し、身体介護や生活援助を行う専門職です。
利用者の尊厳を尊重し、自立を支援することを目的としています。
食事、入浴、排泄の介助といった直接的なケアだけでなく、精神的なサポートや利用者の家族に対応する役割も担っています。
資格取得のメリット
介護福祉士の資格を取得することは、キャリアアップや安定した就労において、以下のようなメリットをもたらします。
【年収アップに期待できる】
介護福祉士の資格を持つことで資格手当が支給されるようになり、これまで以上に年収アップが期待できます。
実際に無資格の介護職員と比較すると、平均月給で7万円ほどの差が見られるデータも存在します。
安定した収入を得ながら、専門職として長く活躍したい方にとって大きなメリットです。
【リーダー職に就ける】
介護福祉士の資格を取得できると、介護現場でリーダーや指導者といった責任あるポジションに就ける可能性が生まれます。
専門的な知識と経験を持っているとされ、現場での信頼が厚くなるからです。
チームをまとめたり、ほかの職員の指導にあたったりと、重要な役割を担う機会が増えていきます。
【転職で有利になる】
介護福祉士の資格は国家資格であることから、転職活動において非常に有利に働きます。
その専門性は全国どこでも通用するため、介護施設での即戦力として期待されやすくなり、選択肢も広がる傾向です。
【活躍できる場所が広がる】
介護福祉士の資格を取得できれば、高齢者施設だけでなく、病院のような医療機関など、より幅広い場所で活躍できる可能性が生まれます。
福祉用具専門員や教員など、直接的な介護とは関わらない別の分野で働くことも可能です。
介護福祉士試験の受験資格を得る主なルート
介護福祉士国家試験を受験するには、特定の資格要件を満たす必要があります。
受験資格を得るための主要なルートを紹介し、それぞれの特徴についても詳しく解説していきましょう。
実務試験ルート
介護福祉士試験の受験資格を得る方法で、もっとも選ばれているルートが「実務経験ルート」です。
指定された施設で3年以上の実務経験を積むことと、介護福祉士実務者研修を修了することで受験資格が得られます。
現場での実践的なスキルと知識を身に付けられるため、働きながら資格取得を目指したい方におすすめです。
養成施設ルート
養成施設ルートは、厚生労働大臣が指定する介護福祉士養成施設(専門学校や大学など)で学び、必要なカリキュラムを修了することで受験資格を得る方法です。
体系的に専門知識と技術を学べるため、介護に関する基礎から応用までをしっかりと身に付けたい方に選ばれています。
福祉系高等学校ルート
福祉系高等学校ルートは、文部科学大臣および厚生労働大臣が指定する福祉系高等学校を卒業することで、受験資格を得る方法です。
高校在学中に専門的な知識と技術を習得できるため、早期に介護福祉士の資格取得を目指したい方に向いています。
卒業後、すぐに国家試験に挑戦できる点が特徴です。
経済連携協定(EPA)ルート
経済連携協定(EPA)ルートは、インドネシア、フィリピン、ベトナムなどの国から日本に受け入れられた介護福祉士候補者がたどるルートです。
所定の施設で働きながら、国家試験の合格を目指します。
日本国籍の人材や、EPAの枠組みに属さない外国籍の人材は、対象としていません。
介護福祉士のキャリアアップに役立つ資格
介護福祉士としてのキャリアをさらに発展させるためには、関連する資格の取得が有効です。
ここでは、介護福祉士のスキルアップやキャリアアップに役立つ資格を紹介します。
認定介護福祉士
認定介護福祉士とは、介護福祉士の上位資格として位置づけられ、より専門的で実践的な介護を提供できる人材を指します。
高度な介護実践能力やチームマネジメント能力、地域連携能力などの資質が必要です。
資格を取得することで、介護現場でのリーダーシップを発揮できるようになり、介護リーダーや施設長へのキャリアアップが期待できます。
社会福祉士
社会福祉士は、福祉に関する幅広い相談に応じ、支援計画の策定や関係機関との連携を行う専門職です。
介護福祉士が身体介護や生活援助を直接行うのに対し、社会福祉士はより包括的な視点から支援を行います。
介護福祉士の資格を持つ人が社会福祉士の資格も取得することで、ダブルライセンスによる収入アップが期待できます。
介護福祉士の資格を生かせる職種
介護福祉士の資格は、多岐にわたる職種でその専門性を発揮することが可能です。
最後に、介護福祉士の知識と経験を生かして活躍できる、代表的な職種について解説していきましょう。
介護支援専門員
介護支援専門員(ケアマネジャー)は、要介護者や要支援者が適切な介護サービスを受けられるよう、ケアプランを作成する専門職です。
介護福祉士からのステップアップ資格として認識されており、介護福祉士として実務経験を積んでから、介護支援専門員の資格取得に挑戦するケースが多く見られます。
生活相談員
生活相談員は、介護施設において利用者やその家族の相談に応じ、生活上の問題解決やサービスの調整を行う職種です。
介護福祉士とは異なり、生活相談員になるための試験はありません。
必要な要件は自治体ごとで異なるため、介護福祉士の資格によって生活相談員になれる場合もあります。
サービス責任提供者
サービス提供責任者(サ責)は、訪問介護事業所で、利用者へのサービス計画の作成や、ホームヘルパーの指導・管理を行う職種です。
質の高いサービス提供体制を構築し、利用者が安心して在宅生活を送れるようサポートします。
介護福祉士の資格があれば、サービス提供責任者になることができます。
まとめ
介護福祉士の合格率は高い傾向にありますが、決して楽に合格できる試験ではありません。
すべての科目で得点する必要があるため、試験の出題内容を把握し、自分に合った学習方法で計画的に準備を進める必要があります。
介護福祉士の資格を取得できたなら、専門職としてのキャリアアップや待遇改善にも期待できるでしょう。
この記事の内容を参考にして、ぜひ介護福祉士への第一歩を踏み出してください。