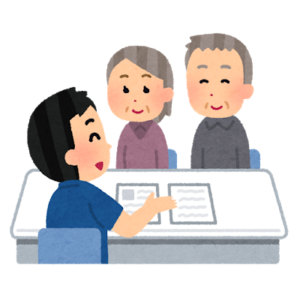【事例あり】介護現場での事故報告書の書き方を詳しく解説

介護現場での事故報告書は、安全な業務運営を支えるために欠かせない重要な書類です。
施設で事故が起きた際には市町村など関係機関への報告義務があるため、正確で適切な内容の記載が求められます。
本記事では介護における事故報告書の目的や役割、事例をもとにした記入例をご紹介します。書き方のコツについても解説するので、業務に役立ててください。
介護の事故報告書を書く目的
事故報告書の作成は、単に介護施設の義務というだけではありません。報告書作成の目的は、事故の再発を防ぐことで安全・安心な施設運営を可能にし、利用者やご家族との信頼関係を構築することです。目的を理解することで何をどのように記載するべきかが明確になり、報告書としての役割も向上します。まずは事故報告書作成の目的を理解しておきましょう。
事故の原因を分析して再発を防ぐため
介護の事故報告書を作成する一番の目的は、原因の追求と再発防止のための対策を立てることです。事故の発生時は慌てていたり気が動転していたりして、発生状況の詳細な理解が難しいかもしれません。事故への対応を終えた後、落ち着いたときに改めて事故の状況を詳しく記録することで、頭の中が整理され、より原因が明確になります。さらに適切な対策を講じ、同じ事故を繰り返さないようにすることで、利用者にとって安心した生活を実現することが可能です。
職員全員に事故後の対応を共有するため
事故が発生したときの状況を職員全員が理解し、対策に沿った業務を行うことが、事故の再発防止に不可欠です。事故の詳細や対策が過不足なく整理して記載された報告書は、他職員の事故に対する理解も深めることで、新たな事故を未然に防ぐことにつながります。事故報告書の内容が読みやすく簡潔にまとめられていれば、職員への共有もスムーズになります。
事故発生後に行った対応の証明のため
重大な事故が発生した後は、事故が起きた原因やその後の緊急対応が適切であったかどうかを利用者の家族から説明を求められることがあります。場合によっては、施設側の対応不備から裁判に発展する可能性もゼロではありません。事故がなぜ起きたのか、その後の対応が適切であったかどうかを記録しておくことで、真摯に対応できるでしょう。事故が起きた状況や対応の詳細な記録が、施設や職員を苦情や訴訟から守ることにつながります。
市町村へ報告する義務があるため
介護施設でのサービス提供中の事故は、その内容を事故報告書に記載し、市町村に提出する義務があります。厚生労働省の「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」では、下記のとおり定められています。
介護老人保健施設は、入所者に対する介護保健施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
重大な事故とその他各自治体が定める事故については、市町村への報告が必要です。これは介護施設が事故に対する原因や対応、再発防止策を適切に実行できているかを確認し、介護サービスの質の向上と改善につなげることを目的としています。事故報告書の作成は、介護施設を運営していくために必須の業務です。
介護事故と見なされるケースとは?
介護事故に含まれる範囲は、市町村の規定によっても異なります。ここでは、一般的な基準で介護事故とされるものを紹介しましょう。
一般的な介護事故の範囲
主に介護事故とされるものには以下のようなものがあります。
- 転倒・転落
- 誤嚥
- 異食・誤飲
- 誤薬
- 火災・火傷事故
- 物損事故
- 施設外への無断外出
- 介助ミスによるケガ
- 送迎中の事故
全国社会福祉協議会が作成した「福祉サービス事故事例集」では、事故の定義を下記のように定めています。
施設における福祉サービスの全過程において発生するすべての人身事故で身体的被害及び精神的被害が生じたもの。なお、事業者の過誤、過失の有無を問わない。
ケガを伴う転倒や、介助時に爪が当たって傷を負わせたなどの事故はもちろん、外傷を伴わない転倒など、身体上の被害はなかったとしても安全面で問題があったものは介護事故に含まれるのが一般的です。
ヒヤリハットとの違い
事故報告書と同様に新たな事故を未然に防ぐものとして、ヒヤリハットが思い浮かぶかもしれません。ヒヤリハットに含まれるものは、転倒や異食といった事故には至らなかったものの、もう少しで転倒していた、もう少しで間違えるところだったとされる事象です。事故に至らなくても、原因の追及や対策の徹底によって事故の発生を未然に防ぐことが可能であるため、事故報告書とともに安全な施設運営のために重要視されています。
介護の事故報告書の様式
事故報告書には厚生労働省によって定められた様式があり、それを使用するか同じ内容の様式を準備することが必要です。作成後は市町村への提出が義務であるため、記載内容の不備や提出漏れがないように内容を確認しておきましょう。また、事故報告書の様式はこれまでも法改正によって変更されています。今後も改定されることがあるため、厚生労働省からの通達には注意しておきましょう。
事故報告書様式の改定
以前は事故報告書の様式や報告の基準が市町村によって違いが生じていましたが「令和3年度介護報酬改定に関する審議報告」によって、事故報告書の様式が統一されて情報の収集と傾向の分析が容易になりました。令和6年には事故報告書の様式が一部改定され、チェックボックスや独自項目欄の追加、電子的な報告の推奨が明記されています。
参照:厚生労働省「令和3年度介護報酬改定に関する審議報告」
参照:厚生労働省「介護保険最新情報 介護保険施設等における事故の報告様式等について(通知)」
事故報告書の記載項目
厚生労働省が実際に推奨している事故報告書の様式を見てみましょう。項目は主に9つです。
- 事故状況:事故によって入院や死亡が発生した場合、該当箇所にチェック。死亡の場合は死亡年月日を記入。
- 事業所の概要:事業所の名称や所在地などの情報を記入。
- 対象者:事故に遭った利用者の介護度といった情報を記入。
- 事故の概要:事故が発生した日時、場所、種別、状況の詳細を記入。
- 事故発生時の対応:事故が発生したときにどのような対応をしたか、医療機関を受診した場合は診断の内容を記入。
- 事故発生後の状況:事故発生後の利用者の状況やご家族などへの報告日時などを記入。
- 事故の原因分析:事故の原因となった要因を「利用者側」「職員側」「環境」の3つの視点から分析して記入。
- 再発防止策:事故の再発を防止するための具体的な対策を記入。対策が有効であったかを評価する期間と、その結果も記入。
- その他特記事項:そのほかに共有しておきたい情報がある場合に記入。
市町村への報告が必要な事故
原則として、介護保険施設のサービス提供中の事故で、下記についてはすべて市町村への報告義務があります。
- 死亡を伴う事故
- 医師による診断を受け、投薬や処置などなんらかの治療が必要となった事故
上記以外の事故に関しては、市町村の規定によって異なるため確認が必要です。
【5日以内にメールで送付】
市町村への提出は電子メールを使用し、事故発生から5日以内と定められています。もし、5日以内にすべての項目を埋めることができない場合は、9つの項目のうち、①から⑥までを可能な限り記載して5日以内に提出します。その後、状態の変化や原因の分析、対策の内容や有効性の評価結果を記入して再度提出が必要です。
【自治体ごとの違い】
報告が必要な事故は市町村の規定によって異なり、自治体によっては食中毒や感染症、職員の犯罪や不法行為についても、事故として報告が義務付けられている場合もあります。施設の管理者は必ず施設のある市町村の条例を参照し、報告義務のある事故を確認しておきましょう。
介護の事故報告書の書き方
事故報告書は再発防止と職員への周知が目的であるため、事故の状況を正確に記載する必要があります。読み手が意味を誤解しないようにするためには、具体的に記録することや客観的な視点で記入することが大切です。
5W1Hを意識する
介護記録は5W1Hで記載することが推奨されていますが、事故報告書においても同様です。いつ(when)・どこで(where)・誰が(who)・何を(what)・なぜ(why)・どのように(how)したかが分かるように記載しましょう。例えば、転倒事故があった際は利用者がベッドサイドで倒れていたのか、それとも離れたところで倒れていたのか、車椅子の位置や向きはどうなっていたかによって、考えられる原因や対策が異なります。転倒した利用者の行動理由を聞き取ることも大切です。普段の記録から5W1Hを意識して取り組んでいれば、自然と身に付くようになるので、意識して継続してみましょう。
客観的事実を書く
介護の事故報告書には、客観的な事実だけを記入するようにしてください。自分が見ていない、聞いていない部分を主観で補うように書いてはいけません。主観が入ってしまうと、職員で対策についてのカンファレンスをしても、本来の原因とは異なった対策になるかもしれません。どうしても不明瞭な部分を補わないと全容を記載できない場合は「◯◯の理由から✕✕と思われる」という形式で、記録者の想定であることが分かるように記載しましょう。
誰にでも分かりやすい表現で書く
事故報告書は市町村への提出が必要なことが多く、さらには利用者やご家族から要請があれば内容を開示する必要もあるため、誰にでも理解できるように記載しなければなりません。具体的には専門用語や略語は記載せず、介護に詳しくない人でも理解できるようにすることが大切です。例えば、ポータブルトイレを「PT」としたり、「いつもと同じ介助で」と記載したりすると、読んでいる人がPTの意味を間違える可能性や、どのような介助が「いつも」なのか分からないことが想定できます。職員間だけでなく、誰が読んでも誤解なく理解できる言葉を選ぶことが大切です。
実例から学ぶ介護の事故報告書の記入例
事故報告書の書き方を、実際に介護現場で起こりやすい内容を参考に解説します。5W1Hが意識されていることと、客観的視点で書かれていることを確認しましょう。
事例①転倒事故
事故報告書を書く際は、転倒によるものが多いのではないでしょうか。まずは転倒事故を例に、基本的な事故報告書の書き方を覚えていきましょう。
【事故の概要】
夜間の巡視のため訪室すると、居室トイレにて体の左側を下にして倒れているA様を発見する。A様に状況を聞くと、ベッドから起き上がり、トイレに行こうとしたときにふらついて転倒したとのこと。足元につまずくようなものはなかった。
【事故発生時の対応】
意識清明。本人様への聞き取りにて、左の腰を床に打ったとのこと。看護師に報告。全身の外傷チェックを行うが、異状なし。バイタルチェックを行い、血圧142/84、脈拍82、体温36.1℃、SPO2は97%。往診医に電話で報告し、痛みの箇所に湿布を貼り様子を見るようにとの指示。
【事故の原因分析】
- 本人様要因:22時に眠剤を内服しており、ふらつきがあった。
- 介護者側要因:ほかの業務のため、本来23時の巡視が30分遅れていた。
- 環境要因:照明がすべて消えており、居室内が真っ暗だった。ベッドからトイレまでの導線上には、支えとなるものが何もなかった。
【再発防止策】
- 22時の眠剤内服時にトイレ誘導をする。
- 居室の入口とトイレの照明はつけておく。
- 据え置き型の手すりの設置を検討する。
事例②誤薬
誤薬は発生件数こそ少ないものの、死亡事故に至る可能性もある極めて重大な事故です。ほかの人の薬を間違えて内服する以外にも、薬を落下させる、飲み忘れる、紛失するといったことも誤薬の一種です。
【事故の概要】
朝食時にB様の内服介助のため、薬ケースから内服薬を取り出す際、誤って同じ名字のC様の薬を取ってしまい、そのまま内服介助をしてしまう。その後、C様の内服介助のため薬ケースを見ると、C様の薬がなく、B様の薬が残っているのを見て誤薬に気づく。
【事故発生時の対応】
看護師に報告。B様が内服したC様の食後薬の内容を確認すると、血圧を下げる薬が含まれていることが判明する。往診医に電話で報告し、1時間おきの血圧測定を12時間実施とのこと。また低血圧症状に注意しながら様子観察の指示あり。
【事故の原因分析】
- 利用者様要因:高齢による認知機能の低下により、いつもより錠数が多いことに気づかなかった。
- 介護者側要因:内服前には薬袋に記載された名前の読み上げを行うことになっていたが、名字しか読み上げず、そのまま内服介助をしてしまった。
- 環境要因:同じ名字を持つ利用者様の薬が隣同士で置かれていた。
事例③誤嚥
高齢者に食事を提供したり、食事介助を行ったりしている介護施設では、嚥下機能の低下による誤嚥の事故が発生する可能性があります。
誤嚥性肺炎の原因になるので、亡くなってしまうケースも少なくありません。
【事故の概要】
昼食時に利用者A様の食事介助をしていたところ、誤嚥によりむせるような激しい咳が発生した。
【事故発生時の対応】
即刻食事と水分の摂取を中止し、看護師に連絡した。
背中をタッピングして、ゆっくりと呼吸を促す。
その後医師の診察を受け、異常が見られなかったため、経過観察となった。
【事故の原因分析】
- 利用者様要因:まだ飲み込んでいないのに、焦って次の食べ物を口にした
- 介護者側要因:飲み込みの確認を怠った
- 環境要因:飲み込みにくい状態の食事を用意した
【再発防止策】
- 利用者の嚥下機能に合った色形状への調整
- 飲み込んだことを確認しながら一口ずつ食事を介助する
事例④FAXの宛先間違い
FAXの宛先間違いは、利用者の個人情報が漏洩し組織の信用が低下するリスクがあります。
介護施設では事務作業も多いため、十分な注意が必要です。
【事故の概要】
M事業者宛に利用者S様のサービス提供実績をFAXした。
その後M事業者の担当者から連絡が来て、S様がこちらの担当ではないことを伝えられ、宛先を間違えてFAXを送信したことが発覚した。
【事故発生時の対応】
誤送信先への謝罪と資料回収依頼、本来の送信相手への謝罪と説明、利用者家族への報告と謝罪を行った。
【事故の原因分析】
- 利用者様要因:なし
- 介護者側要因:慌てていた
- 環境要因:FAXの番号入力パネルの操作がしにくい
【再発防止策】
- 短縮ダイヤルを登録する
- 短縮ダイヤルの登録時に職員2人以上でダブルチェックを行う
事例⑤内出血(痣)の発見
介護中に内出血を発見した場合は、介護施設の検討会で原因を推察するのが一般的です。
介護事故以外に虐待の可能性も考慮して、関係機関に連絡する場合もあります。
【事故の概要】
入浴介助のため利用者のC様に下半身の衣服を脱いでもらうと、脛の部分に3cm×3cmの内出血を発見した。
【事故発生時の対応】
看護師に報告して、痣の状態を診てもらう。
痛みはなく、ほかに症状もないため、保護テープを貼って経過観察となった。
【事故の原因分析】
- 利用者様要因:ベッドや車椅子にぶつけた可能性
- 介護者側要因:移動介助を行う際にぶつけた可能性
- 環境要因:ベッドに柵が設置されていない
【再発防止策】
- 適切な移乗介助を職員内で共有する
- 施設内で足をぶつける可能性がある箇所を保護する
事例⑥熱中症
夏の介護で気を付けたいのが、熱中症の発症です。
熱中症による事故は、介護者と利用者の双方にリスクがあります。
【事故の概要】
S様の自宅を訪問した際に呼び掛けに応じず、ベッドの上で横になったまま顔が赤くなっていた。
室温計を確認すると30℃あり、エアコンはつけておらず、扇風機だけが稼働していた。
意識はあるが、起き上がることができない。
【事故発生時の対応】
水にぬらしたタオルで体を拭き、エアコンをつけた。
水分摂取が困難だったため、事業所の責任者に報告して救急車を要請した。
病院では軽度の熱中症と診断され、点滴による水分補給が行われた。
【事故の原因分析】
- 利用者様要因:エアコンをつけていなかった
- 介護者側要因:訪問前の電話で体調不良に気付けなかった
- 環境要因:温度と湿度が高かった
【再発防止策】
- 介護者と家族に熱中症予防の知識を共有する
- 利用者の水分摂取状況を訪問前に確認する
事例⑦物品破損
物品破損は、訪問介護利用者の自宅で発生しやすい事故です。
介護サービスを提供する過程で、介護事業所の備品や利用者の私物を破損してしまう事故のことを指します。
【事故の概要】
T様の自宅でベッドから車椅子への移動介助を行う際に、ベッドからメガネが床に落ちてしまい、レンズが少しだけ割れてしまった。
【事故発生時の対応】
すぐに利用者や家族に丁寧な謝罪を行った。
速やかに施設の管理者に報告し、後日賠償責任保険による補償を行った。
【事故の原因分析】
- 利用者様要因:ベッドの上にメガネを置きっぱなしにした
- 介護者側要因:周囲への注意義務を怠った
- 環境要因:メガネを置く場所が決まっていない
【再発防止策】
- メガネを装着してから移動介助を行うように徹底する
- メガネを置く安全なスペースを作る
事例⑧尻もち事故
利用者が尻から転倒して床に座った状態で発見される事故を、尻もち事故と呼びます。
尻もち事故は、浴室や利用者の居室内で起こりやすくなります。
【事故の概要】
K様の居室内からうめくような声が聞こえたため、訪室するとベッドサイドに尻もちをついた状態で発見された。
「腰が痛い」との訴えがあるが、こちらの呼びかけには反応できている。
【事故発生時の対応】
動かさずに即刻看護師に連絡して、バイタルの測定を実施した。
体温:〇〇
血圧:〇〇
血中酸素飽和度:〇〇
看護師の判断によりTクリニックを受診し、胸部打撲と診断され、湿布薬が処方された。
【事故の原因分析】
- 利用者様要因:靴のかかとを踏んだまま歩こうとしていた
- 介護者側要因:靴の履き方を日頃からチェックしていなかった
- 環境要因:ベッドサイドの手すりが不足している
【再発防止策】
- 見守りの体制を強化する
- ベッドサイドに手すりを導入する
事例⑨表皮剥離
表皮剥離とは、摩擦によって皮膚の表面が剥がれてしまう外傷のことです。
介護の現場では、車椅子のフットレストとの接触が原因で、表皮剥離が起こるケースがあります。
【事故の概要】
N様の居室に伺った際、右前腕部に2cm×3cmの表皮剥離を発見した。
痛みはないが、少量の出血を確認。
【事故発生時の対応】
表皮剥離の発見後すぐに看護師に連絡した。
感染予防の目的で生理食塩水による清浄を行った後、創部を消毒してガーゼで保護した。
【事故の原因分析】
- 利用者様要因:周囲の確認を怠った
- 介護者側要因:危険な箇所の認識が不足していた
- 環境要因:ベッドの柵が保護されていない
【再発防止策】
- ベッドの柵にクッション材を装着する
- 定期的な訪室を実施する
事例⑩設備破損
介護施設の設備が破損し、介護者にケガを負わせてしまうケースも少なくはありません。
設備そのものに不備があった場合は、設備破損となります。
【事故の概要】
職員とS様が車椅子で移動中に車椅子のブレーキが作動せず、壁に軽く衝突してしまった。
S様にケガはなく、車椅子にも大きな破損はなかった。
【事故発生時の対応】
利用者に異常がないことを確認した。
乗っていた車椅子を利用停止にし、修理を手配した。
【事故の原因分析】
- 利用者様要因:使い方に問題はない
- 介護者側要因:車椅子の状態を把握していなかった
- 環境要因:車椅子のメンテナンス不足
【再発防止策】
- 車椅子の点検を月に1度行う
- 利用者を乗せる前に車椅子の状態を確認する
介護事故報告書とは
介護の現場で事故が発生した際に、事故の内容を詳細にまとめた書類が介護事故報告書です。
自治体によって様式は異なりますが、事故の原因や状況、対応を記入し、自治体や利用者の家族に提出します。
介護事故報告書を提出する目的は、再発防止策を考えるためです。
事故の原因を分析し、事故を防ぐ方法や、事故が起こった場合の対応方法を記録するためでもあります。
事故が発生したことにより管理不足を疑われた場合でも、介護事務所の評判を守るための証拠になるでしょう。
介護事故報告書の作成手順
介護事故報告書を作成するまでの手順は、次のとおりです。
- 介護事故を発見する
- 利用者の状態を確認する
- 周囲にいる職員を呼ぶ
- 上司やリーダーに事故を報告する
- 看護師や主治医に報告して指示を仰ぐ
- 利用者の経過を観察する
- 職員間で事故の防止策を検討する
事故発生時にもっとも優先すべきことは、利用者の安全を確保することになります。
頭を強く打っている場合や、窒息して呼吸が止まっている場合は、命を守るための緊急対応が必要です。
また、事故が発生したときは一人で対応するべきではありません。
できるだけ多くの仲間を集めて、複数人で対応しましょう。
適切な行動がとれるように、緊急時のマニュアルを頭に入れておくことも大切です。
事故報告書の作成だけで満足してはいけません。
介護事故の原因と対策をすべての職員に共有し、再発防止に努めましょう。
介護事故が起こる原因
介護事故が起こる原因は、次の3つに分類することが可能です。
- 職員・事業所側
- 利用者側
- 環境的な要因
介護事故の原因を詳しくチェックしていきましょう。
職員・事業者側
職員や事業所側に原因があるのは、次のようなケースです。
- 人手不足による職員の疲労
- 職員同士の情報共有がない
- 介護技術の不足
- ルールやマニュアルがない
介護事業所の人手が不足していると、業務負担が重くなるので職員に疲労がたまりやすくなります。
職員同士の連携が密に取れなくなると、行ってはいけないサービスを提供してしまう、などの介護事故につながりやすくなります。
疲労やストレスが蓄積すると、正常な判断力が低下してしまいます。
介護職員の技術力の低さが原因で、介助が必要な利用者にケガを負わせてしまうこともあるでしょう。
ルールやマニュアルが整備されていないことも、介護事故につながります。
利用者側
利用者側に原因があるのは、認知症や身体機能の障害により、身体的な制約がある場合です。
制約のある利用者は基本的に職員による介助が必要になりますが、頼みにくかったり、自分でやりたかったりすると、介助なしで対応しようとします。
無理な動作をした結果、転倒や誤嚥などの介護事故を引き起こしてしまうのです。
環境的な要因
環境的な要因によって介護事故が引き起こされるのは、次のようなケースです。
- 浴室の床が滑りやすい
- 照明が足りていない
- 適切な場所に手すりがない
浴室は特に滑りやすいので注意が必要ですが、利用者が床に水をこぼしたことにより、転倒事故が発生した事例もあります。
介護事故の責任
介護事故の原因が事業所側にあった場合は、責任を負う必要があります。
どのような責任が発生するのかを、詳しく見ていきましょう。
損害賠償
注意義務違反が認められた場合は、民事上の責任として、介護事業者に損害賠償義務が生じます。
損害賠償義務が生じるのは、介護事業者が利用者との間で締結した利用契約に基づいて負う債務を履行しなかった場合です。
指定取り消し
介護保険を利用した介護事業を行うためには、都道府県または市区町村からの指定が必要で、行政からも監督を受けています。
介護事故の発生により、介護保険法77条1項に該当した場合は、指定の取り消しや、指定の効力を一時停止する処分が下される可能性があります。
指定の取り消しは介護事業所の運営に直結するため、非常に厳しい処分といえるでしょう。
業務上過失致死傷
職員が業務上必要な注意を怠って利用者を死傷させた場合は、業務上過失致死傷の罪に問われる可能性があります。
業務上過失致死傷の罰則は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
裁判では、業務に求められる注意義務違反があったか、その結果負傷につながったかが争点になります。
介護事故が発生した場合の対応
介護事故が発生した場合の正しい対応について解説します。
利用者の安全確保
一番に優先すべきことは、利用者の安全確保です。
声がけを行い、必要であれば救命措置や病院、警察への連絡を行います。
利用者家族への連絡
利用者へ家族の連絡も忘れずに行ってください。
遅くなればなるほど、相手に不信感を与えてしまいます。
事故状況を丁寧に説明し、速やかに謝罪することが大切です。
関係各所への連絡
事故報告書を作成した後は、市区町村の保険者へ提出が必要です。
必要に応じて、居宅介護支援事業所やかかりつけ医への連絡を行いましょう。
賠償責任保険に加入している事業所の場合は、保険会社への連絡も行います。
責任者への状況説明
事故の発見者は、周囲の職員に連絡をしたり、責任者に状況の説明をしたりしなければなりません。
責任者は、事故の目撃者や関係者から話を聞き、冷静な分析を行います。
再発防止のため、すべての職員に事故を周知し、注意喚起を行ってください。
介護事故発生時の間違った対応
介護事故発生時の間違った対応について解説します。
介護事故を報告しない
事故が発生した場合は、どんなに小さな事故でも報告する義務があります。
職員個人で解決したと判断し、報告を怠るというのは絶対にやめてください。
介護事故を隠蔽する
事故の責任から逃れたり、事業所の評判が悪化したりするのを防ぐため、介護事故を隠蔽するようなことは絶対にやめましょう。
隠蔽の事実が発覚した場合は、営業停止などの行政処分が課せられる場合もあります。
介護事故を防ぐための対策
介護事故を防ぐための対策について解説します。
原因が職員や事業者にある場合
人員不足により事故が発生した場合は、勤務時間の変更を行い、業務負担の重い時間帯に人員を集中させましょう。
働き方を変更し、見守りを途切れさせないことが重要になります。
人員の不足はすぐに解消できない場合がほとんどです。
今いる人員で、見守り不足による事故の発生を防ぐ工夫が必要になります。
原因が利用者にある場合
利用者が原因で転倒事故が発生した場合は、歩行状態を安定させるために積極的なリハビリテーションを活用してください。
日常生活の中でも、職員が付き添いながら歩く機会を増やしていきます。
また、薬の副作用によりふらつきがある場合は、薬の種類や内服の時間をかかりつけ医に相談してみましょう。
原因が環境にある場合
浴室の床が滑りやすい場合は、転倒予防対策が必要です。
具体的な予防対策として、職員の付き添いや滑り止めマットの設置、滑り止めスプレーの使用などがあります。
常に見守りができない居室内の転倒対策は、こまめな訪室やセンサーマットの利用が有効です。
転倒事故の予防ができる見守りシステムの導入を検討しましょう。
介護事故報告書に関するよくある質問
最後に、介護事故報告書に関するよくある質問に回答します。
誰が書くのか?
介護事故報告書を書くのは、介護事故が発生した現場を目撃したスタッフや、対応したスタッフです。
その場にいない人が書いてしまうと、事実と異なる報告がなされてしまう可能性があります。
まったく関係のない第三者が、憶測や曲解のもとに作成するのは絶対にやめましょう。
介護事故報告書が正確に作成されないと、事故の共有がなされず、再発防止策を考える機会も失われてしまいます。
介護事故報告書は事故に関わったスタッフが作成し、管理者や主任が客観的に編集して完成させるのが基本です。
保存期間は?
介護事故報告書の保存期間は、自治体によって2~5年と決められています。
保存期間が長いのは、行政指導や法的対応の際に使用する可能性があるからです。
介護事故報告書の保存は、厚生労働省の指導に基づいて行われています。
テンプレートやマニュアルはある?
介護事故報告書のテンプレートは、厚生労働省や各自治体の公式ホームページからダウンロードできます。
インターネットで検索すれば、介護施設が独自に作成したテンプレートを無料でダウンロードすることが可能です。
介護事故の対応マニュアルについても、厚生労働省や自治体のホームページにまとめてあるので、対応に困った場合は上手に活用しましょう。
書き損じた場合は?
介護事故報告書を手書きで作成しているときに書き損じてしまった場合、修正テープや修正ペンは使用できません。
二重線で消してから自分の印鑑を押すのが、正しい修正のやり方です。
どのように書き損じてどのように修正したのか分からないと、不正を疑われる可能性があります。
書き損じが多くなってしまった場合は、新しい紙に書き直すようにしましょう。
ケアリッツでは訪問介護スタッフの正社員を募集中
訪問介護サービスを提供しているケアリッツでは、介護スタッフの正社員を募集しています。
正社員の比率が多く、安定して働くことができます。
男女比も均等で偏りがなく、幅広い年齢層の方が在籍しています。
ケアリッツで安心・安全な働き方を実現しましょう。
【再発防止策】
- 服薬介助時の読み上げはすべてフルネームで行うこととし、マニュアルの徹底を共有する。
- 同じ名字を持つ利用者様の薬がある場合はマーカーで印をつけ、注意を促すようにする。
介護の事故報告書作成時の注意点
最後に、事故報告書を書く際の注意点について解説します。事故の概要や発生時の対応について、表現があいまいであったり、記載内容に不備があったりすると、再発防止のための対策になるどころか、最悪の場合は裁判で多額の損害賠償を請求されることにもなりかねません。以下の点に注意して書き進める必要があります。
原因を十分に洗い出し、事故の要因を分析する
原因と対策を一人で考える必要はありません。必要に応じてカンファレンスを行い、複数名がさまざまな視点から原因を追求することで、最適な再発防止策にたどり着くことでしょう。そのためには、事故の概要には事故発生時の状況をできるだけ詳しく書くことが求められます。例えば、転倒時にはどの向きで倒れていたか、靴を履いていたかどうか、車椅子のブレーキはかかっていたかどうかなどは原因の分析において重要な情報です。事故が起きた状況を詳しく記載し、得られた情報によってあらゆる角度から原因を突き止めることが大切です。
裁判の証拠になる可能性もあることに留意する
たとえ事故発生時に適切な対応をしていても、記録に不備があるとご家族から説明を求められた際に正確に答えられなかったり、裁判に発展した場合施設側に不利な証拠として取り上げられたりする可能性があります。特に事故発生時の対応については、その後の経過によっては誤った処置が病状の悪化を招いたと疑われるかもしれません。対応の記録は時系列に沿って詳しく残すことで、ご家族への正確な説明が可能となり、対応した職員自身を守ることにもなります。
対策は実現可能で具体的なものにする
事故報告書を作成する際、再発防止策は実現可能で具体的な内容にすることが重要です。「今後気を付ける」「チェックを強化する」「改善に努める」といったあいまいな表現では、実際に何をどう改善するのかが伝わらず、再発防止策としては不十分です。ヒューマンエラーは完全にゼロにはできませんが、組織としてミスが起きにくい仕組みや環境を整備することが大切です。例えば次のような具体策を盛り込みましょう。
- 手すりを新たに設置する。
- 利用者の名前を必ず声に出して確認する。
- 介助手順をマニュアル化して全職員に周知徹底する。
こうした積み重ねが、施設全体の安全意識の向上にもなります。
まとめ
介護の事故報告書は単なる記録ではなく、利用者の安全を守るとともに、職員同士の情報共有を図り、施設全体の質を高めるための重要なツールです。事故の原因について客観的に分析し、再発防止につながる具体的な対策を講じることが、利用者やご家族からの信頼につながります。簡潔で正確な記録は、ご家族や行政への説明責任を果たすためにも必要不可欠です。事故報告書の作成に苦手意識を持つ方も多いかもしれませんが「5W1Hを意識する」「事実のみを書く」「誰にでも分かる言葉を使う」といった基本を押さえれば、誰でも適切に記録ができるようになります。今回紹介したポイントや事例を参考に、日々の業務に役立ててください。