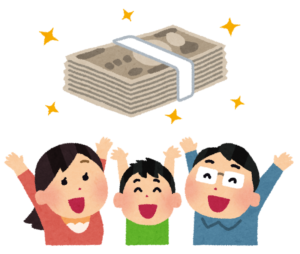介護職の給料は上がる?2025年以降の賃上げ動向についても解説

「介護職の給料が上がる」という話を、ニュースや噂で耳にしたことはありませんか。
すでに政府は介護職の賃上げ政策を実施していますが、実際に介護職の給料はいつから、いくら上がっているのでしょうか。
本記事では、介護職の賃上げのタイミングと推移、また賃上げが実行された理由について解説していきます。
介護職の給料が低い理由や、介護職の給料を上げる方法についても解説していくため、ぜひ最後までご覧ください。
介護職の給料が上がったタイミングや推移
介護職の給料を上げる取り組みは、これまでにいくつか実施されています。
給料が上がったタイミングとその理由、また賃上げ政策の推移について解説していきます。
2024年2月:介護職員処遇改善支援補助金
2024年2月から、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(2023年11月2日閣議決定)に基づき、新たな賃上げの取り組みとして介護職員処遇改善支援補助金が支給されています。
介護職員一人あたり月平均6,000円相当の賃上げが可能となるように設計されており、補助金の対象期間は2024年2月~5月分までの4カ月間です。
この補助金を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 介護職員ベースアップ等支援加算を取得している事業所
- 2024年2月・3月分から実際に賃上げを行う事業所
- 補助額の2/3以上を介護職員等の月額賃金の改善に使用すること
なお、補助金は「一人あたり月平均6,000円相当」とされていますが、事業所ごとの計算方法や職員への配分方法によって、実際の支給額は異なる場合があります。
全員に一律で6,000円が支給されるわけではなく、下回るケースもあるため注意しましょう。
補助金の対象は介護職員ですが、事業所の判断により、ほかの職種の処遇改善に充てることも可能です。
参照:厚生労働省「令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金について」
2024年6月:介護職員等処遇改善加算
2024年6月以降は以下の3つの加算制度が統合され、新たな「介護職員等処遇改善加算」として一本化されます。
- 介護職員処遇改善加算
- 介護職員等特定処遇改善加算
- 介護職員等ベースアップ等支援加算
この新加算には、加算要件や加算率が異なる加算Ⅰ~Ⅳの4種類が設定されており、それぞれの事業所が要件を満たした範囲で加算を受けることができます。
すぐに新加算Ⅰ~Ⅳへ移行できない事業所向けには、2025年3月までの経過措置として新加算Ⅴ(1~14)が設置され、段階的な移行をサポートする仕組みです。
新加算を取得するためには、以下の3つの要件を満たすことが必要です。
- キャリアパス要件
- 月額賃金改善要件
- 職場環境等要件
これらの要件をクリアした事業所には加算金が支給されるため、介護職員の基本給アップにつながります。
参照:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」
2024年以前の賃上げ政策の推移
介護職の賃上げ政策は、2024年以前にも行われています。
これまでに実施された、賃上げ政策の推移もチェックしていきましょう。
【2022年:介護職員処遇改善支援補助金】
2022年に実施された介護職員処遇改善支援補助金は、介護職員の月額給与を約9,000円引き上げることを目的とした施策です。
政府は収入の約3%に相当する金額を補助金として交付しましたが、交付率が異なるため実際の支給額にはばらつきが生じました。
この補助金の導入により介護職員の給与は上昇したものの、補助金を受け取るための事務手続きが煩雑で、介護事業者の負担が増えたことが課題として指摘されました。
また、すべての職員に一律9,000円が支給されるわけではなかったため、不満の声も上がった施策です。
【2019年:特定処遇改善加算】
2019年10月の介護報酬改定により、経験や技能を持つ介護職員の処遇改善を目的とした特定処遇改善加算が創設されました。
この制度は介護職員の確保と定着を促進し、長く働ける環境を整えることを目的としています。
特定処遇改善加算を受けるための基本条件は勤続10年以上の介護福祉士が対象ですが、他法人や医療機関での経験も通算できるため、各事業所の裁量で柔軟に運用が可能です。
また、加算の配分についても一定のルールが設けられており、特に経験や技能のある介護職員に重点的に配分される仕組みです。
具体的には、対象となる介護福祉士の給与を月額8万円以上引き上げる、もしくは年収440万円以上を維持することが求められます。
事業所が要件を満たした上で都道府県に申請し、受け取った資金は介護職員の処遇改善手当として支給されます。
経験豊富な介護職員の待遇向上を図ることで、介護業界全体の人材確保と質の向上につながる取り組みです。
【2012年:処遇改善加算】
2012年に導入された処遇改善加算は、介護職員の給与を引き上げて働きやすい環境を整えることを目的とした制度です。
2009年から実施されていた、介護職員処遇改善交付金に代わる仕組みとして設けられました。
一定の要件を満たした介護事業者は、介護職員一人あたり月12,000円から37,000円の加算額を受け取れます。
加算額は、事業所が満たしているキャリアパス要件(Ⅰ)から(Ⅴ)の区分によって決定されます。
2025年以降も介護職の給料は上がる?
2025年以降も介護職の給料は上がるのでしょうか。
今後も賃上げが期待できるのかどうか、解説していきます。
2.0%のベースアップが目標
厚生労働省は、2024年度に続き、2025年度も介護職員の給与を2.0%引き上げることを目標に掲げています。
日本は高齢化の影響により、要介護者がこれから年々増えていくことが予想されます。
よって、これまでと同様に介護職の人材確保のため、2025年以降も給料のベースアップを進めていく可能性が高いでしょう。
介護職の待遇改善が強化される見込み
日本の総人口が減少する一方で、65歳以上の高齢者人口は増加を続けており、2037年には国民の3人に1人が65歳以上になると予測されています。
特に2025年以降は団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となり、介護サービスの需要は急速に拡大すると考えられます。
その結果、介護業界の人材不足がさらに深刻化し、現場の負担も増大していくでしょう。
こうした状況を踏まえて、政府は介護職の確保と定着を目的に、賃金の引き上げや職場環境の改善を含めた待遇改善の強化を進める方針です。
今後の政策によって、介護職の処遇がさらに改善される可能性があります。
介護職の給料が上がった理由
介護職の賃上げが実施された背景には、高齢化の進行による介護需要の増加と、人材確保の必要性があります。
介護業界では慢性的な人手不足が課題となっており、その大きな要因の一つが給与水準の低さです。
この問題を解決するため、政府は処遇改善加算や補助金の支給を通じて賃金引き上げを推進し、人材の確保と定着を図る施策を展開してきました。
特に、介護職員処遇改善加算や特定処遇改善加算などの制度を整備し、介護職の待遇改善に取り組んでいます。
また、コロナ禍を経て介護士や看護師、保育士などのエッセンシャルワーカーの社会的な重要性が再認識されたことも、介護職の賃上げが進められた理由の一つです。
介護職の賃上げ対象施設と対象者
介護職員等処遇改善加算は、具体的にどのような事業所や職員が対象となるのでしょうか。
ここでは、介護職の賃上げ対象施設や対象者について解説していきます。
対象施設
2024年6月に実施された介護職員等処遇改善加算の対象となる施設は、介護職員処遇改善加算の(Ⅰ)~(Ⅲ)を算定する事業所です。
2025年6月以降は要件を再編・統合により新加算(Ⅰ)~(V)に一本化し、加算率も引き上げられます。
新加算を算定するためにはキャリアパス要件と月額賃金改善要件、職場環境等要件の3つを満たすことが必要です。
2025年度中は激変緩和措置として、現行の要件を継続することも可能ですが、2026年度以降は新加算に完全移行します。
2025年6月からの介護職員等処遇改善加算(新加算)の加算率は、次のとおりです。
| 介護職員等処遇改善加算(新加算) | 加算率 |
| Ⅰ | 24.5% |
| Ⅱ | 22.4% |
| Ⅲ | 18.2% |
| Ⅳ | 14.5% |
なお、上記の加算率はすべて訪問介護の例です。
今回の報酬改定で、事業者は2026年度分の賃上げを前倒しして行うことも可能で、前倒しした2025年度分の加算額の一部は、2026年度内に繰り越して賃金改善に充てることができます。
対象者
2025年6月以降の介護職員等処遇改善加算の支給対象者は介護施設で働く職員ですが、事業所内で柔軟に配分することが認められています。
パートやアルバイト、派遣社員などの雇用形態も問われないため、非正規職員も受給できる可能性があります。
また介護施設の事務職や看護職、リハビリ職も支給の対象とすることが可能です。
ただし、地域によっては介護施設の代表者や役員を支給の対象外としている場合もあるため、支給対象者を知りたい場合は自治体に直接問い合わせてみましょう。
【対象外の介護職】
介護職でも、交付の対象とならない場合があります。
介護職員等処遇改善加算が対象となる介護職は、次のとおりです。
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 福祉用具貸与
- 特定福祉用具販売
- 居宅療養管理指導
- 居宅介護支援
- 介護予防支援
業務として介護を専門に行わない職員は、処遇改善手当を受け取ることができません。
受け取れない職場環境の場合は、異動や転職などのキャリアパスを模索するのも、一つの手段でしょう。
事務所判断による賃上げも可能
賃上げの対象は基本的に介護職員とされていますが、事業所の裁量によっては介護職員以外の職種にも、処遇改善加算を活用することが可能です。
処遇改善加算は介護現場の環境向上を目的として支給されるものであり、一定の範囲内で事業所が柔軟に運用できる仕組みだからです。
そのため、本来は賃上げの対象ではない職員でも、施設の判断によって支給額の一部が配分されるケースもあります。
介護職の平均給料
そもそも、介護職員は給料をいくらもらっているのでしょうか。
介護職の平均給料は、勤続年数や雇用・施設形態、保有する資格によって異なります。
それぞれの月給の平均給料を紹介するので、チェックしていきましょう。
全体・男女別
介護職の給与には、性別による差が見られます。
厚生労働省の「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果」によると、男性介護職の平均給与は33万4,250円、女性介護職の平均給与は30万8,880円となっており、男性のほうが約3万円高いことが分かります。
年齢別に見ると、男女ともに40~49歳の平均給与がもっとも高いです。
参照:厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果 p163」
勤続年数別
介護職に限定される話ではありませんが、平均給料は勤続年数によっても変動します。
厚生労働省の「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果」によると、1年目の平均給与は約28万円です。
しかし、5年目には約30万6,000円、10年目には約32万3,000円、20年以上では約37万2,000円と、勤続年数の増加に伴い給与も上がっています。
同じ事業所で長く勤務することで昇給の機会が増え、安定した収入を得やすくなるでしょう。
また、介護職の給与は夜勤の有無や役職の有無によっても変動するため、キャリアアップの機会を生かしながら働くことが大切です。
参照:厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果 p139」
雇用形態別
介護職の給与は、雇用形態によっても違いがあります。
厚生労働省の「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果」によると、常勤の介護職員の平均給与は32万2,550円、非常勤の介護職員は20万4,440円となっており、約12万円の差があります。
また、同じ常勤でも職種によって平均給与が異なるのが特徴です。
例えば、常勤の介護支援専門員(ケアマネジャー)の平均給与は36万5,180円で、介護職員と比較すると約4万円高いです。
一方、非常勤の介護支援専門員の平均給与は29万9,250円と、非常勤の介護職員と比べて約9万円の差があります。
資格を取得して介護支援専門員などの専門職にキャリアアップすることで、大幅な給与アップが期待できます。
安定した収入を得るためには、資格取得や常勤としての勤務を視野に入れることが重要でしょう。
参照:厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果 p269」
施設形態別
介護事業者の施設形態によっても、介護職の給与額は変動します。
「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果」をもとに、施設形態別の平均給与額を比較していきましょう。
- 介護老人福祉施設:34万7,520円
- 介護老人保健施設:33万8,280円
- 介護療養型医療施設:28万5,100円
- 介護医療院:32万1,120円
- 訪問介護事業所:31万7,800円
- 通所介護事業所:27万6,680円
- 通所リハビリテーション事業所:3万5,100円
- 特定施設入居者生活介護事業所:31万3,850円
- 小規模多機能型居宅介護事業所:29万1,440円
- 認知症対応型共同生活介護事業所:29万3,270円
平均給与額が高い施設は、24時間介護が必要で夜勤が多いという特徴があります。
通所介護事業所など、日中の勤務がメインの場合は給与が低めになることを把握しておきましょう。
参照:厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果 p197」
保有資格別
保有している資格によっても、給与額に違いが発生します。
「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果」による保有資格別の平均給与額は、次のとおりです。
- 介護支援専門員(ケアマネージャー):37万6240円
- 介護福祉士:33万1,690円
- 社会福祉士:35万2,560円
- 実務者研修:30万250円
- 介護職員初任者研修:30万2,910円
介護職は保有資格によって携われる仕事が異なるため、給与額にも差が生じます。
保有資格の中でもっとも平均給与が高いのは、介護支援専門員(ケアマネージャー)です。
介護支援専門員の資格は、ほかの介護系の資格と比較しても難易度が高いですが、収入アップを目指すなら取得したい資格でしょう。
参照:厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果 p232」
平均年収の推移
介護職の平均年収は本当に上がっているのでしょうか。
「令和5年賃金構造基本統計調査」による介護職員(医療・福祉施設等)の平均年収の推移は、以下のとおりです。
- 2020年:360万400円
- 2021年:352万8,000円
- 2022年:362万9,300円
- 2023年:371万3,800円
2020年から2021年では給料が下がっているものの、それ以降は上昇傾向にあります。
介護職の待遇改善政策により、2024年以降も平均年収は上昇していくことが予想されます。
参照:厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」
都道府県別のランキング
介護職の平均年収は、都道府県によっても違いがあります。
介護職(施設勤務)の平均年収が高い都道府県トップ5は、次のとおりです。
- 広島県:404万1,800円
- 東京都:394万7,400円
- 神奈川県:392万1,600円
- 千葉県:391万6,700円
- 愛知県:388万7,100円
都道府県の平均年収では、広島県が唯一400万円台でした。
広島県は介護職の平均賞与でも、全国平均より約20万円高めです。
全体としては都市部の平均年収が高く、地方の平均年収が低い傾向があります。
参照:厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」
介護職の給料が低い理由
なぜ介護職は給料が低いのでしょうか。
給料が低くなる要因について解説します。
専門性の高さが評価されにくい
介護職は無資格でも働ける職場が多いため「誰にでもできる仕事」と誤解されることが少なくありません。
そのため専門性が正しく理解されず、給与が低いというイメージにつながっています。
しかし、実際には高齢者一人ひとりの生活を支えるために、身体介助の技術や医療・福祉に関する知識、コミュニケーション能力など、多くのスキルが求められます。
専門性の高い職種ほど給与が上がる傾向があるため、介護職の待遇改善には社会全体がその重要性を認識することが必要です。
介護の専門性が正しく評価されることで職業としての価値が高まり、給与の向上にもつながるでしょう。
介護報酬に上限がある
介護職の給与が上がりにくい要因の一つに、介護報酬の上限があることが挙げられます。
介護事業者は利用者に提供したサービスの対価として国から介護報酬を受け取りますが、この金額は介護保険制度によって定められており、自由に設定できるものではありません。
報酬の枠が限られている以上、事業者が独自の判断で大幅な給与アップを行うのは難しいのが現状です。
さらに、利用者に対して必要な職員の配置基準が決められているため、人員を削減して一人あたりの給与を増やすこともできません。
こうした仕組みにより企業努力だけでは給与の引き上げが難しく、介護職の待遇改善には介護報酬の見直しが求められています。
赤字の施設が多い
介護業界では人手不足や物価高による経費の増加、介護報酬の改定が追いついていないことなどが要因となり、赤字経営に陥る施設や事業所が増えています。
近年では、感染症の影響による利用控えや営業停止により収益が減少し、施設の閉鎖や廃業に追い込まれるケースも珍しくありません。
特に中小規模の事業所では、経営の厳しさが顕著になっています。
経営が悪化すれば従業員の給与を引き上げる余裕はなくなり、長期的に赤字が続けば人件費の削減も避けられません。
その結果、介護職の給与がさらに低くなる可能性があり、現場の人材流出を加速させる要因となっています。
求人が集まりやすい
介護業界は人手不足が問題視される一方で、求人を出せば一定数の応募が集まる傾向があります。
その理由の一つに、資格や経験がなくても働ける職場が多いことが挙げられます。
未経験者でも採用されやすいため、低賃金であっても応募する人が一定数いるのが現状です。
また、こうした求人の多くは非正規職員向けであり、正規職員に比べて労働時間が短く、給与水準も低い傾向があります。
結果として、介護業界全体の平均給与が上がりにくい要因となります。
待遇の改善と安定した雇用環境を整えることで、人材の定着と質の向上にもつながるでしょう。
非正規の割合が高い
経営が厳しい介護施設では、人件費を抑えるために非正規職員の割合が高くなる傾向があります。
特に赤字経営の施設では、正規雇用への登用を積極的に行わず、低コストで労働力を確保しようとするケースもあります。
非正規職員で資格や経験がない場合は昇給の機会が限られてしまい、長期間働いても収入が上がりにくいのが現状です。
また、正規雇用の基準が不明確な施設では、何年勤めても正社員として雇用されない可能性もあります。
そのため、パートやアルバイトの割合が極端に高かったり、給与水準が相場よりも低かったりする施設では、働く前に雇用条件をしっかり確認することが大切です。
安定した収入やキャリアアップを目指すなら、正規雇用への道が開かれている職場を選ぶのが望ましいでしょう。
介護職の給料をアップさせるには
給与を上げるために、個人では何ができるのでしょうか。
最後に、介護職の給料をアップさせる方法を紹介していきます。
資格を取得して資格手当をもらう
介護に関わる資格を取得すれば、給与に加えて資格手当をもらえる可能性があります。
給与アップが期待できる介護系の資格は、次のとおりです。
- 介護福祉士
- 介護支援専門員(ケアマネージャー)
- 社会福祉士
- 認知症ケア専門士
- 実務者研修
- 介護職員初任者研修
これらの資格の中で、比較的平均年収が高いのは介護支援専門員(ケアマネージャー)です。
介護支援専門員(ケアマネージャー)は利用者のニーズを把握し、適切なケアプランを作成します。
介護系資格の中でも上位の資格で、業務の幅が広がることにより待遇がよくなる可能性があります。
夜勤を増やす
可能であれば夜勤の回数を増やすのも、一つの方法でしょう。
夜勤手当は1回あたり4,000~8,000円程度が相場ですが、労働基準法で具体的な基準額は定められていません。
そのため、施設や地域によっては「深夜割増賃金」や「時間外割増賃金」として支給されることもあります。
シフトの希望を調整して夜勤の回数を増やすことで、手当の分だけ給与を上げることが可能です。
ただし、夜勤が増えすぎると生活リズムが崩れて、体調に支障をきたすリスクもあります。
疲労が蓄積して仕事のパフォーマンスが低下する可能性もあるため、収入と健康のバランスを考えながらシフトを組むことが大切です。
事業所の福利厚生を活用する
働いている介護施設や事業所によっては、生活を豊かにできる福利厚生が利用できる場合があります。
介護施設によくある福利厚生は、次のとおりです。
- 各種社会保険(健康保険、厚生保険、介護保険)
- 通勤手当
- 食事補助
- 住宅手当
- 退職金制度
- 特別休暇制度
- 産休・育休制度
- 資格取得支援制度
手当や制度が充実している施設や事業所であれば、安心して働き続けることができます。
医薬品の割引や予防接種など、独自の福利厚生がある場合もあるので、チェックしておきましょう。
給与が高い施設に移る
介護施設の給与水準は、施設の経営状況や地域によって大きく異なります。
経営が赤字の施設では給与の引き上げが難しい一方で、黒字経営の施設では比較的給与が上がりやすい傾向があります。
また、都道府県によっても介護職の給与に差があり、都市部では比較的高い水準にあることが多いです。
現在の職場の給与に不満がある場合は、給与水準の高い施設や地域への転職を検討するのもよいでしょう。
給与面だけでなく福利厚生や労働環境のよさも考慮しながら、よりよい条件の職場を選ぶことが重要です。
管理職を目指す
介護職で給与を上げる方法として、管理職を目指すことも挙げられます。
管理職になると責任は増えますが、その分給与のアップも期待できます。
管理者としての役職に就くためには、一定の実務経験や専門知識が求められるほか、マネジメント力や職員との信頼関係も重要な要素です。
現在の職場で昇進を目指す場合は業務の幅を広げたり、リーダーシップを発揮したりすることで管理職への道が開ける可能性があります。
転職を考えている場合は、管理職候補としての採用を目指すのもよい選択肢でしょう。
まとめ
本記事では、介護職の給料がどのように変動するのかについて、詳しく解説しました。
介護職の人材確保や定着を目的に、政府は介護職員処遇改善支援補助金の支給や、介護職員等処遇改善加算の加算率引き上げを実施しています。
さらに2025年以降も賃上げ目標を2.0%アップとしており、今後も給与の引き上げが継続される可能性が高いでしょう。
給与の向上には政府の施策に頼るだけでなく、待遇のよい施設への転職や資格取得、キャリアアップなどの個人でできる工夫も大切です。
今回紹介した方法を参考にしながら、よりよい労働環境を目指しましょう。