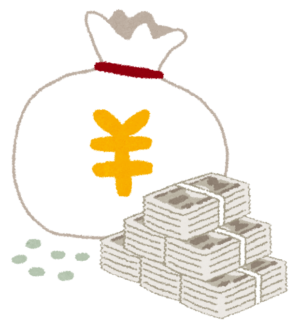【薬の知識】認知症に関わる薬 Vol.1 – 中核症状に使われるお薬① アリセプト

以前にマガジンでご紹介した、認知症の記事(こちら)にもあるように、認知症の症状には大きく、中核症状と呼ばれるものと周辺症状と呼ばれるものがあります。
中核症状は、いわゆる認知症としてだいたいの人が思い浮かべるような、代表的な症状です。例えば、記憶障害や見当識障害、失語・失認や判断力の障害などが挙げられます。
一方周辺症状とは、鬱状態のような陰性の症状だったり、暴力・徘徊、妄想、過眠といった統合失調症のような陽性の症状であり、一般的には精神疾患と近い症状を示すものです。

認知症の薬物治療
認知症の薬物治療は、中核症状に対応する薬剤と、周辺症状に対応する薬剤を組み合わせて行っていきます。
中核症状に主に使われる薬剤は、現在では4種類存在します。
①アリセプト(一般名; ドネペジル)
②レミニール(一般名; ガランタミン)
③イクセロンパッチ・リバスタッチパッチ(一般名; リバスチグミン)
④メマリー(一般名; メマンチン)
今回はその中でも代表的かつ最古参の薬、アリセプトについてまとめてみました。
概要
- 認知症に関わる薬 中核症状に使われるお薬
- 認知症に関わる薬 Vol.1 – 中核症状に使われるお薬① アリセプト
- 認知症に関わる薬 Vol.2 – 中核症状に使われるお薬② レミニール
- 認知症に関わる薬 Vol.3 – 中核症状に使われるお薬③ イクセロン
- 認知症に関わる薬 Vol.4 – 中核症状に使われるお薬④ メマリー
- 認知症に関わる薬 周辺症状に使われるお薬
アリセプトは、エーザイが1999年に発売開始した、日本で最初の認知症治療薬です。
その後長い期間、唯一の治療薬として広く使われてきました。
アルツハイマー病やレビー小体型認知症においては、神経伝達物質である「アセチルコリン」という物質が足りなくなることが研究からわかっています。
このアセチルコリンは「アセチルコリンエステラーゼ」という酵素によって分解されるのですが、この酵素に先にくっつき働きを阻害することによってアセチルコリンの量を増やす、というのがこの薬の仕組みです。
そのため、コリンエステラーゼ阻害剤、というカテゴリーに分類されています。
剤型と服用方法
歴史の長い薬でもあるため、患者の状況にあわせてさまざまな剤型が用意されています。
①フィルムコート; 普通の錠剤で、表面がつるつるしているため飲み込みやすい
②OD錠; 見た目は普通の錠剤だが、口内で溶けるようになっている。水なしで飲める
③細粒; いわゆる粉薬。量の調整がしやすい
④内服ゼリー; ゼリー状になっているため、嚥下障害のある方向け
⑤ドライシロップ剤; ペースト状にして、上あごに塗り付けて飲んだりすることが可能
それぞれの剤型に、3mg, 5mg, 10mg の3種類が用意されています。
通常1日1回3mgからスタートして副作用が起きなければ2週間後から5mgに増量、進行していて5mgで4週間以上服用が続いている場合には10mgに増量することができます。
薬の効果
あくまで、根本原因にアプローチする薬ではないため、根治治療とはならず、効果としては中核症状の進行を食い止める、といった効果にとどまります。ですので、できるだけ早い段階から飲み始めることが肝要です。効果が表れるまで、理由は諸説ありますが3か月ほどかかります。
また、中核症状の進行を食い止める以外に興奮系の作用もあるため、抑うつや無気力、無関心といった症状に効果がある反面、2割程度の人では暴言や徘徊などといった副作用がみられることもあるため、注意が必要です。
他にもアセチルコリンが増えることにより、徐脈や失神、ふらつき、めまいといった副作用や、パーキンソン病様症状がみられることが報告されています。